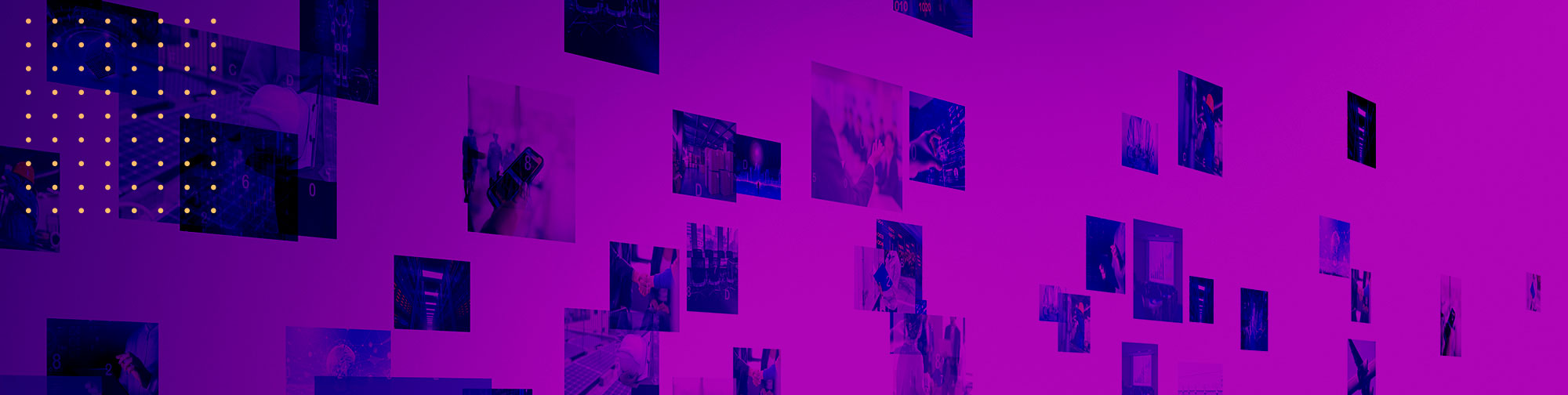記事一覧

災害時に頼れるIT技術を解説!
はじめに
自然災害が頻発する現代において、防災DXの進化が注目されています。
デジタル庁は、災害を「平時」「切迫時」「応急対応」「復旧・復興」の4つの局面に分け、
それぞれの局面で優れたサービス・アプリを「防災DXサービスマップ・サービスカタログ」として整理し、公表しています。
今回はこの局面別に有効な防災DXについて紹介します。
目次
1.平時
2.切迫時
3.応急時
4.復旧・復興時
1.平時
平常時においては、避難意識の醸成が主な課題です。
「自分は災害に遭うはずがない」、「自分だけは大丈夫」と言った意識では、
実際に災害に遭った時の被害がより大きくなってしまう恐れがあります。
そこで大切になるのが日頃の防災に対する意識と備えです。
ハザードマップの確認や、食糧や生活用品の備蓄に加えて平時に行っておきたいのが、シミュレーションです。
災害リスクを想定した防災学習に効果的な防災DXも多く開発されています。
中でもARやVRを活用した災害体験は、リアリティがあるため、実際の防災訓練にも使用されています。
「普段自分がいる場所が浸水したらどうなる?」「泥水で足元が見えない中、どう歩けばいい?」
「消火器の使い方ってどうするの?」このような体験をあらかじめARやVRで体験しておくことで、
いざという時に慌てずに行動することが可能になります。
2.切迫時
切迫時とは、自然災害がもうすぐ発生するという時のことで、
ここでどう行動するかは命に直結することもあります。
このフェーズで大切になってくるのが、正確な被害予測をベースにした避難促進です。
災害時により多くの人々に正確な情報を届け、適切な行動を促すことに特化したシステムやアプリが数多く開発されています。
AIチャットボットで市民の問い合わせに答えてくれるものや、
災害状況・避難所の開設情報をリアルタイムで取得できるもの、
日本語を母国語としない人たちに向けた多言語対応のもの、
耳が聞こえにくい人向けにテキストで情報提供してくれるものなど、多様な情報共有システムが開発されています。
3.応急時
災害発生直後の混乱期に有効な防災DXも多く開発されています。
逃げ遅れている人がいないかなどを確認することはとても重要なことです。
一般的に被災後の3日(72時間)を過ぎると生存率が著しく低下すると言われており、
行方不明者を発見するのに有効な防災DXの1つに、正確なGPSが挙げられます。
GPS発信機(携帯可能な高精度の発信機)は、子供から高齢者まで多くの人に安心を与えてくれます。
モバイルバッテリーのようにコンパクトで持ち運びが簡単なうえ、
豊富なデザインのものが発売されています。お値段も比較的リーズナブルですので、ぜひ一度チェックしてみてください!
GPS発信機は、スマホなどの端末で位置情報を受信することができ、Bluetoothで最後の0cmまで位置を特定することが可能です。
また、公助用の電波も有するため、公的救助機関の捜索時も早期発見に繋がる可能性も高くなります。
発信機は防水性と耐久性も備えているため、塗れたり、
瓦礫の下などの見つかりにくい場所にいても位置情報を発信し続けることが可能です。
災害時のほか、迷子や貴重品の置忘れ防止にも有効で日常生活でも重宝しますね。
4.復旧・復興時
災害の後の、被害状況の把握にはとても時間と労力を必要とします。
特に高所や海中などの人間が立ち入る安全が保障されていない場所の点検は、
リスクを伴うため、被害の把握が難しいとされています。
そこで活躍するのが、高性能ドローンです。
中には、コンクリートのミリ単位のひび割れを判別できるものや、
スピーカーを搭載し上空から取り残された人がいないか声掛けをして行うもの、狭い・危険な場所でも入って
調査できる上、その映像から3Dデータを生成して構造物内部の状況をより多角的に把握することができるもの等、
用途も性能も多岐に渡り、復旧・復興に貢献しています。
まとめ
今回は防災DXについて紹介しました。
大掛かりなものから個人レベルで取り入れられるもの等、多種多様な防災DXが存在しています。
もしもの時のために、自分に合ったシステムやアプリを事前に選んで導入しておくと、
災害発生時にも慌てることなく行動することができそうですね。
🏷️タグ
#防災DX
#災害体験
#AR・VR