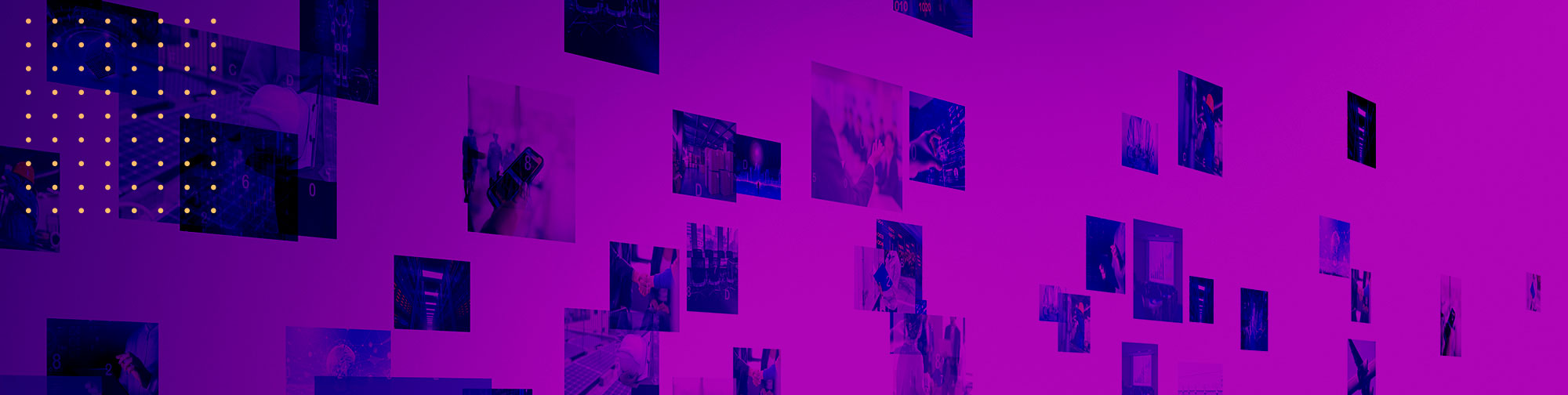記事一覧

歴史ロマンの探求!文化財の非破壊分析!
はじめに
読者の皆さんは美術館や博物館に、足を運ぶ機会はありますか?
最近はゲームなどの影響で、刀剣や浮世絵などの、文化財への注目が高まっています。
各々の時代の超絶技巧で作られた文化財を見て、どうやって作られたのか、どんな材料でできているのか、気になることもあるのではないでしょうか。
それらを解明するのに欠かせないのが、表面を削ったり切断したりせずに分析を行う、非破壊分析です。
今回は文化財の非破壊分析について、解説していきます。
目次
1.非破壊分析の進歩
2.主な非破壊分析の方法
3.文化財の非破壊分析の実例
1.非破壊分析の進歩
①非破壊分析が普及する以前
文化財に限らず原料物質や構造などの分析は、破断して断面を観察したり、薬品で溶かして化学的構造を解析するといった、破壊的分析が一般的です。
しかしこのような手法は、文化財のような希少性の高いものには適用できません。
そのため技術の継承が途絶えたものの分析に関しては困難を極め、やむを得ず微量の破片を用いたサンプリング検査(破壊検査)も行われてきました。
➁技術の進歩とともに変化する分析方法
技術の進歩によりX線などの電磁波、量子ビームを用いた分析方法が開発され、非破壊分析が可能になりました。
また歴史学者や技術者が協業し努力を重ねた結果、各種分析装置の小型化・可搬化が進められ、遺物など動産文化財だけでなく、遺構など不動産文化財の非破壊検査も可能になりました。
しかし非破壊検査は現在でも、測定誤差が大きい、定性的であるという欠点があり、正確な分析にはサンプリング検査と組み合わせて行う必要があります。
「定性的」とは数値化できない物事を表し、これに対して「定量的」とははっきりと数値化できる物事を表します。
参照や注釈
先端技術が解き明かす考古学の過去・現在・未来 精密工学会誌. https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjspe/88/8/88_601/_pdf (参照2025-02-06)
2.主な非破壊分析の方法
現在では大きく分けて、X線や赤外線などの電磁波を用いた装置と、量子ビームを用いた装置とがあります。
①X線CT
X線を照射し透過した像を撮影し、これを数百~数千の方向から行い、コンピューターで処理して3D画像を得ます。
汎用性の高さから、文化財以外にも様々な物の非破壊分析に利用されています。
➁テラヘルツ波非破壊検査装置
電磁波のうち、電波と光の境界領域にある周波数(1THz前後)である、テラヘルツ波を使用した測定装置です。
テラヘルツ波はプラスチックやセラミック、紙などを透過し、金属などは透過しないという特性があります。
この特性を利用して、油絵などの絵画の分析に使用されています。
③ハイパースペクトルカメラ
可視光から赤外線くらいまでの範囲を、非常に細かい周波数で細分化(分光)して撮影するカメラです。
通常のデジタルカメラは、3バンドに分光して検知しますが、ハイパースペクトルカメラは100~200バンド以上に分光するため、より細かい波長情報が得られます。
測定対象の素材により、光の周波数ごとの反射特性が違うのを利用して、文化財の素材同定を非破壊・非接触で行うのに使用されます。
④蛍光X線分析装置
原子にX線を当てると、物質ごとに違うエネルギーのX線が放出されます。
これを蛍光X線と言い、この性質を利用して対象の物質を同定する分析方法を、蛍光X線分析と言います。
近年では装置が小型化され、ハンドヘルド型のものもあり、古墳内壁画や絵画の顔料素材特定などに使用されています。
⑤ミュオンビームを用いた鋼鉄中の炭素量分析
こちらはまだ研究段階の手法ではありますが、将来有望な非破壊分析方法として、注目されています。
ミュオンは素粒子の一つで、宇宙線として地球に飛来したり、加速器で人工的に作られたりすることで利用でき、本測定方法においては、後者を利用します。
また寿命が短く、発生してから2.2マイクロ秒で、他種類の素粒子に崩壊・消滅してしまいます。
ミュオンビームを試験体に打ち込むと、含まれる物質の原子に捕らえられ、その種類により寿命が異なる特性があります。
この性質を利用して、鋼鉄中の鉄と炭素を検出し、炭素の含有量を測定します。
参照や注釈
X 線CTの概要 Rigaku. https://rigaku.com/ja/products/imaging-ndt/x-ray-ct/learning/x-ray-computed-tomography-brief-introduction (参照2025-02-06)
テラヘルツ波を用いた非破壊検査の原理やメリットを徹底解説 FA Products. https://jss1.jp/column/column_230/ (参照2025-02-06)
ハイパースペクトルカメラとは? ケイエルブイ株式会社 https://www.klv.co.jp/hyperspectral/whats_hsi/ (参照2025-02-06)
[XRF]蛍光X線分析法 材料科学技術振興財団 https://www.mst.or.jp/method/tabid/168/Default.aspx (参照2025-02-06)
ミュオン実験. J-PARC MLF. https://mlfinfo.jp/ja/aboutmlf/muon.html (参照2025-02-06)
3.文化財の非破壊分析の実例
①ゴッホ作「ドービニーの庭」の分析
(1)調査の背景
本作品はゴッホ本人が、同じ作品を2枚描き、1枚は現在スイスのバーゼル市立美術館に、もう1枚は日本のひろしま美術館に所蔵されています。
しかし2枚の絵画には違いがあり、バーゼル美術館所蔵の物には、左下に猫が描かれていますが、ひろしま美術館の物には無く、代わりに同じ場所が茶褐色に変色しています。
どちらも贋作でないことが確認されましたが、猫がいない理由がわかっていませんでした。
(2)分析結果
蛍光X線分析装置で、ひろしま美術館の「ドービニーの庭」を分析したところ、変色した部分から猫の形に、絵具の成分が分布しているのが確認されました。
また塗り重ねられたと思われる部分からは、「シルバーホワイト」の成分が検出されましたが、その周囲の白い部分には、ゴッホが多用した「ジンクホワイト」が使用されていました。
これにより、猫の描かれた部分を塗りつぶしたのは、ゴッホ本人ではない可能性が高まりました。
➁ミュオンによる非破壊微量軽元素分析法の開発
先述したミュオンビームを用いて、鋼鉄中の炭素量を測定する実験が、大阪大学で行われました。
(1)実験の背景
日本刀など鋼鉄には微量の添加物が混じっており、その種類や含有量によって鋼鉄の性質が大きく変化します。
中でも炭素の量は特に重要で、炭素量が多いほど硬くなり、少ないほど柔軟になります。
良質な日本刀の性質とされる、「斬れる、折れない、曲がらない」を実現する、ちょうどよい炭素量や構造の解明につながるとされ、注目を受けています。
(2)実験結果
今回は実験のため、あらかじめ炭素量のわかっている鋼鉄に、ミュオンビームを照射しました。
その結果、鉄成分と炭素成分それぞれのシグナルが、はっきり分かれて検出され、本分析法が有効であることが確認できました。
またそれだけでなく、ミュオンビームの出力を使い分けることで、試験体の内部の炭素量を見分けることができることもわかりました。
専用の機器を開発することで、精度や感度をさらに向上させられることが期待されます。
参照や注釈
文化財をはかる[3] 文化財をはかることは、文化財から教えてもらうこと”. HORIBA. https://www.jp.horiba.com/hakaruba/archives/1474/index.html (参照2025-02-07) ”\鋼鉄の品質管理・日本刀など文化財の非破壊分析も/ 鋼鉄中のわずかな炭素を素粒子で透視する”. 大阪大学. 2024-02-09 https://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2024/20240209_2 (参照2025-02-07)
まとめ
文化財には謎や伝説が付き物ですが、非破壊分析によりそれらの解明につながるかもしれません。
しかし謎をひとつ解けば、また新たな謎が表れ、またそれを解明する研究が始まります。
読者の皆さんも本記事を読んで、ぜひ歴史のロマンを感じてみてください!
🏷️タグ
#文化財
#非破壊分析
#X線
#ミュオンビーム