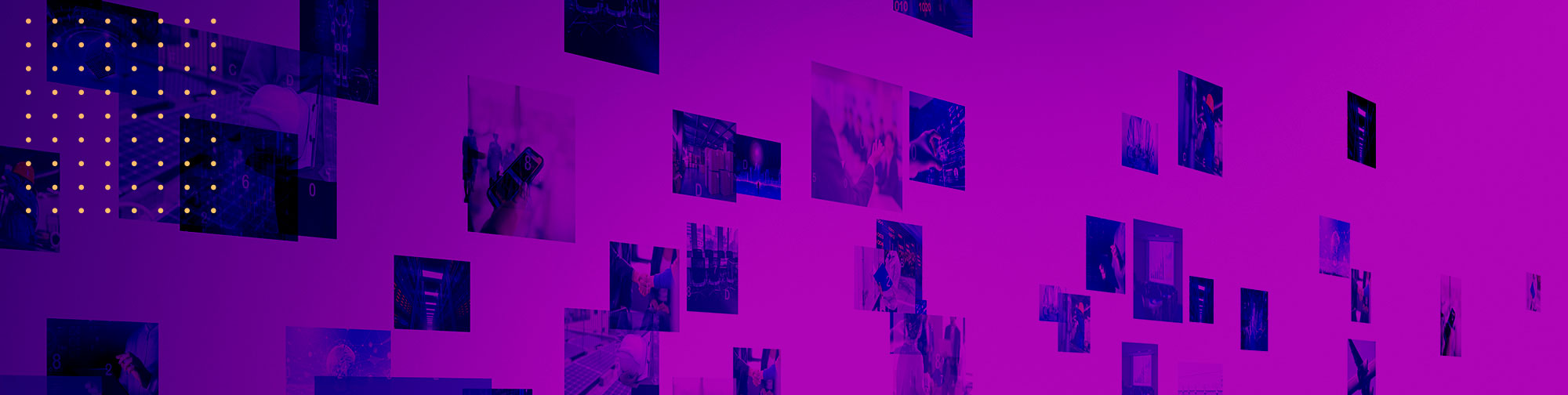記事一覧

SNSに疲れた方へ!SNS絶ちの方法を解説
はじめに
現在、世界中で「SNSの利用による健康被害」への関心が高まっています。
たとえば2024年11月、オーストラリアでは16歳未満のSNSの利用を禁止する法案が可決され、大きな話題となりました。
施行は1年後がめどとなっているため、現在(25年1月時点)適応されている訳ではありませんが、国家レベルでSNSに対する規制が行われるのは世界初なので多くの人々から注目されています。
この記事では、SNSの利用は私たちにどのような健康被害をもたらすのか、健康被害を避けるために私たちが出来ることについて解説していきます。
参照や注釈 NHK - どうすべき?子どもとSNS オーストラリアでは禁止へ https://www.nhk.or.jp/radio/magazine/article/my-asa/myk20241223.html#:~:text=して下さい。-,工藤:,されるわけではありません。 (25年2月6日参照)
目次
1.SNSが私たちのメンタルヘルスに与える影響
2.SNS依存になってしまう人の特徴!
3.SNSに疲れた時におすすめしたいこと
1.SNSが私たちのメンタルヘルスに与える影響
LINE、Instagram、XなどのSNSは、もはや知らない人の方が少ないと言えるほど私たちの生活に浸透しています。
自分らしく居られるコミュニティを探したり、自己表現を楽しんだり、ビジネスに活用したり、SNSには多くの魅力があります。
しかし、SNSが原因でメンタルの不調を訴える人が後を絶たないのも事実です。
特に近年では、SNS依存の症状に悩む方が増加傾向にあると言われています。
SNS依存(ソーシャルメディア中毒と同義)とは、高頻度でSNSを利用することで日常生活に支障をきたす状態をを指します。例えば以下のような症状があります。
・職場での会議中、友人との会話、育児などSNSの利用を中断すべきタイミングでも辞められない
・自身の投稿に対して「いいね」や「コメント」などの反応がないか過度に気になってしまい、常にアプリの画面を更新したくなってしまう。
・他人の目を意識した投稿を繰り返したり、過激な発言をしてしまう。
・他人に良い面ばかりを見せたくなり、見栄を張って高価なものを購入したと報告したり、理想化した自分を見せようとしてしまう。
2.SNS依存になってしまう人の特徴
SNS依存になりやすい人には以下のような共通点があるといわれています
①共感力が低い
共感性が高いと、SNS上の暗いニュースを見て苦しくなってしまうので、自然とSNSを見なくなるという見方があります。
逆に共感性が低い人は、ネガティブな情報を見ても心に葛藤が生じ辛いです。
人は本来ネガティブな情報に関心を向けやすい傾向があるため、共感性が低い人ほどSNSにのめり込みやすいと言えます。
②抑うつ傾向がある
抑うつの傾向がある人は、SNS上の他人と自身を比較してしまい「自分は周囲よりも劣っている」と感じやすくなります。
自分の無価値さを証明するように、SNSでグルグルと巡回してしまうようになり、メンタルヘルスに深刻なダメージを与える可能性があります。
参照や注釈
ひだまりこころクリニック - ソーシャルメディア中毒とは?SNS依存症に陥る心理と対策を解説します https://nagoya-hidamarikokoro.jp/blog/social-networking-addiction/ (25年2月6日参照)
3.SNSに疲れた時におすすめしたいこと
依存とまではいかないけど、「SNSを見過ぎているな」と自覚のある方も多いでしょう。
そんな方向けに手軽に始められるアクションをまとめましたので参考にしてみてください!
①スクリーンタイム機能を活用してアプリの使用時間を制限する
「スクリーンタイム」機能が搭載されたスマホでは、どのアプリをどのくらいの時間使用したかをチェックしたり、各アプリの使用時間に上限を設けて制限することが可能となっています。
無自覚に長時間SNSを見てしまう方は、スクリーンタイムを導入してみることをオススメします。
また、制限を設けなくても、SNSをどのくらい使用したかチェックするだけでも、時間の使い方を見直すきっかけになるかもしれません。
自分がいかにSNSに多くの時間を割いているか自覚し、驚愕する方も居るかもしれません!
②意識的にデトックスタイムを設ける
四六時中SNSの通知が来ないかそわそわしてしまう方は、SNS依存症に片足を踏み入れているかもしれません。
そんな方におすすめしたいのは、SNSから意識をシャットアウトするために、今日はSNSを一切見ない!という意識でSNSから離れる時間を設ける方法です。
いきなり1日SNSをチェックしないなんて無理、という方は、お友達との外出中だけロッカーなどに預ける、などの工夫を取り入れると一気にハードルが下がるでしょう。
目の前のことに集中できるようになるので、1日の充実度も上がるはずですよ!
③SNSのアプリを見えにくい場所に格納する
スマホの画面を開いて1アクションでアクセスできる位置にSNSアプリを置いておくと、ついついチェックしてくなってしまうもの。
フォルダを作成し、奥の方にアプリを格納するだけでも手間が増えて、SNSをチェックする頻度を下げることが可能です。
他の方法はハードルが高いと感じる方にまず取り入れてもらいたいです。
参照や注釈
品川メンタルクリニック - SNSとうつ病の関係とは~メンタルヘルスに与える影響を知ることが大事~ https://www.shinagawa-mental.com/column/psychosomatic/sns/ (25年2月6日参照)
@Living - 社会問題化するSNS依存と“SNSデトックス”のコツ https://at-living.press/life/40190/ (25年2月6日参照)
まとめ
SNS依存していると自覚のある方は、一人で抱え込まずに、行政が設置している相談窓口やプロのカウンセラー、病院の利用を検討してみてください。
依存症は、個人の努力だけではどうにもならないケースもあります。
難しい問題であること理解し、SNSを辞められない自分を責めずに、適切なサポートを受けてみることを推奨します。
🏷️タグ
#SNS依存
#デジタルデトックス
#スマホ依存
#メンタルヘルス