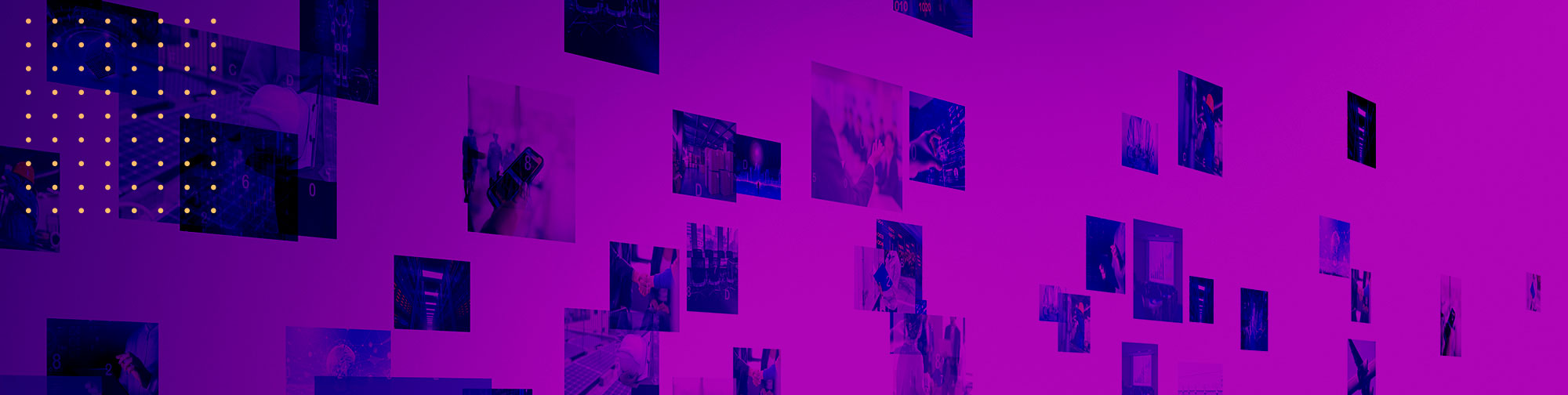記事一覧

自治体のVtuber活用事例9選!活用法や注意点を解説
近年、自治体のPR活動に新たな風を吹き込んでいるのが「Vtuber(バーチャルユーチューバー)」の活用です。従来の広報手段では届きにくかった若い世代へのアプローチや、地域の魅力を新たな形で発信する手段として注目を集めています。しかし、「具体的にどう活用すれば良いのか」「どんな事例があるのか」と悩む自治体担当者も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、全国の自治体が取り組む実際のVtuber活用事例を9つ紹介しながら、メリットや効果的な活用方法、導入時の注意点まで幅広く解説します。地域の魅力発信や住民とのコミュニケーションに新たな可能性を見出したい自治体担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
この記事でわかること
- 自治体公式Vtuberの基本と主なメリット
- Vtuberを活用した効果的な自治体PR方法
- 全国9自治体の具体的な活用事例と成功ポイント
- Vtuber導入・運用時の重要な注意点
- Vtuber活用に関する費用や効果測定など実務的な疑問解決
目次
自治体公式Vtuberとは
自治体公式Vtuberとは、地方自治体が公式に認定・運営するバーチャルキャラクターで、主にYouTubeやSNSなどのデジタルプラットフォームで活動し、地域の魅力や行政情報を発信する存在です。従来の広報誌やホームページでは届きにくかった若年層へのアプローチや、地域のブランディング強化を目的に導入される例が増えています。
自治体がVtuberを活用するメリット
自治体がVtuberを活用することで得られるメリットは多岐にわたります。その効果的な側面について詳しく見ていきましょう。
若い世代へのアプローチができる
自治体公式Vtuberの導入により、従来の広報手段では届きにくかった若年層への効果的なアプローチが可能になります。特に10代から30代の若者は従来の広報誌やホームページを自発的に閲覧する機会が少ない傾向がありますが、YouTubeやSNSを主な情報源としている世代です。
親しみやすいキャラクターを通じて行政情報を発信することで、硬質になりがちな行政コンテンツを柔らかく伝えることができます。また、若者が日常的に利用するプラットフォームで継続的に情報発信することで、自治体と若年層の接点を増やし、地域への関心や愛着を育む効果も期待できます。
SNS・動画プラットフォームでの拡散力が高い
Vtuberコンテンツは、その視覚的な魅力やエンターテイメント性から、SNSでの自発的な拡散が起こりやすいという特徴があります。自治体の公式アカウントが発信する通常の情報よりも、キャラクターを通じた発信の方がシェアされやすく、地域外へも情報が広がりやすいのです。
特にファンアートの制作や二次創作活動が起こると、さらなる拡散効果が期待できます。これにより、地域の魅力や情報が自治体の想定を超えて広範囲に届けられる可能性が高まります。
地域ブランディングができる
Vtuberの活用は、地域の個性や魅力を効果的に表現し、地域ブランディングに貢献します。地域の歴史、文化、特産品、観光スポットなどを、キャラクターの個性やストーリーに織り込むことで、地域の魅力を印象的に伝えることができます。
例えば、茨城県の「茨ひより」は服装の青はネモフィラ、黄色は干し芋、ピンクは偕楽園の梅花をイメージし、頭には県名産のアンコウの髪飾りを付けるなど、県の特徴を視覚的に表現しています。このように地域の特色を取り入れたキャラクターデザインは、地域のアイデンティティを強化し、他地域との差別化を図る効果があります。
自治体のVtuber活用方法
Vtuberを活用した自治体PRには、様々な方法があります。目的や対象に合わせた効果的な活用例を見ていきましょう。
観光地・名産品のPR
Vtuberは観光地や名産品のPRに非常に効果的です。実際に現地を訪れて紹介する動画や、地元の特産品を使った料理動画など、視聴者の興味を引くコンテンツを制作できます。キャラクターの個性を生かした体験レポートは、公式サイトの情報よりも親近感があり、視聴者の行動喚起につながりやすいのが特徴です。
また、観光地の魅力を伝える際に、歴史背景や地元ならではの楽しみ方など、ガイドブックには載っていない情報を含めることで、視聴者の訪問意欲を高める効果も期待できます。
イベント告知・レポート
地域のお祭りやイベントの告知、そしてイベントレポートにVtuberを活用することで、より多くの人々の関心を集めることができます。事前告知では参加方法や見どころを分かりやすく伝え、イベント後にはハイライトや感想を共有することで、次回の参加意欲を高める効果が期待できます。
また、リアルタイム配信を活用すれば、イベント会場にいない人々もバーチャル参加が可能となり、地理的な制約を超えた地域PRが実現します。
防災・安全啓発
防災情報や安全啓発といった、重要ながらも住民の関心を得にくい情報も、Vtuberを通じて伝えることで視聴率や理解度の向上が期待できます。避難訓練の実演や災害時の行動指針、防犯対策など、親しみやすいキャラクターが説明することで、特に若年層の記憶に残りやすくなります。
また、定期的な防災情報の発信によって、日常的な防災意識の醸成にも貢献します。災害リスクや対策について、硬質な行政情報ではなく、身近なキャラクターからの情報として伝えることで、受け入れられやすくなるのです。
移住・定住促進
Vtuberは移住希望者に向けた地域情報の発信にも効果的です。地域の生活環境、住宅情報、子育て支援、就労機会など、移住検討者が知りたい情報をVtuberを通じて発信することで、より親しみやすく具体的に地域の暮らしをイメージしてもらうことができます。
実際の移住者へのインタビューや、移住体験談をVtuberが聞き手となって紹介するなど、移住のハードルを下げるコンテンツも効果的です。
採用活動・地域おこし協力隊募集
人材募集や地域おこし協力隊の募集においても、Vtuberの活用は有効です。自治体職員の仕事内容や魅力、地域おこし協力隊の活動事例などを、キャラクターを通じて紹介することで、応募者の興味を引きやすくなります。
また、職場環境や地域での生活スタイルなどをVtuberのルポルタージュ形式で伝えることで、応募者がよりリアルに将来の自分の姿をイメージしやすくなり、ミスマッチを減らす効果も期待できます。
ふるさと納税PR
ふるさと納税の返礼品や地域の取り組みをVtuberが紹介することで、全国の潜在的寄付者の注目を集めることができます。返礼品の魅力や使い心地、地域での活用事例などを視覚的・体験的に伝えることで、寄付の意欲向上につながります。
また、寄付金の使途や地域への貢献について、Vtuberがレポート形式で伝えることで、寄付者との継続的な関係構築も可能となります。
自治体のVtuber活用事例
実際に自治体のVtuberとして活躍されている事例を9つ紹介します。
茨ひより:茨城県
茨ひよりは、茨城県公認のバーチャルYouTuber(VTuber)で、2018年8月3日に「いばキラTV」公式アナウンサーとしてデビューしました。県庁のバーチャル広報課・VTuberチームに所属する県職員という設定で、茨城県の観光地や県産品、イベント情報などを動画や生配信で発信しています。
キャラクターデザインは茨城県出身のイラストレーター・ハルタスクが担当し、服装の青はネモフィラ、黄色は干し芋、ピンクは偕楽園の梅花をイメージ、頭には県名産のアンコウの髪飾りを付けています。
活動内容は、県の魅力紹介動画や選挙啓発、eスポーツ大会やニコニコ超会議などのイベント出演、BBCやNHKなどテレビ番組への登場、成人式への動画メッセージ、海外向け(英語・中国語)の観光・県産品紹介動画配信、他VTuberとのコラボ、グッズ展開など多岐にわたります。2023年からはChatGPTと連携した「AI茨ひより」として音声対話型AI化され、県庁やイベントで来場者と会話できる新たな取り組みも始まっています。
自治体公式VTuberの先駆けとして、若年層への情報発信や県のイメージアップ、観光・産業振興に大きく貢献しています。
参考:茨ひより(ひよりんの部屋)/茨城県
X:茨ひより@茨城県公認VTuber (@ibakira_Vtuber)
YouTube:IBAKIRA TV - YouTube
岩手さちこ:岩手県
岩手さちこは、岩手県公認のバーチャルYouTuber(VTuber)で、岩手県の魅力や県の取り組みをSNSや動画で発信しています。出身は岩手町で、父が警察官、母がなぎなた部出身という家庭に育ち、自身もなぎなたでインターハイや国体に出場した経験を持ちます。性格は明るく真面目で好奇心旺盛、ちょっとおっちょこちょいな一面もあります。
2020年2月14日に岩手県公認VTuberとして情報公開され、YouTubeやX(旧Twitter)、Instagramなどを活用し、主に若年層に向けて岩手の観光情報や移住者向け情報、県の施策などを分かりやすく伝える活動を行っています。また、「いわてまるごと売込み隊」の宣伝部員としても活動し、県内外へのPRに努めています。
外見は武道の道着をベースに、岩手の伝統工芸品や県章、県花「キリ」などを身にまとい、髪は県旗と同じ納戸色、南部鉄器の風鈴を模した髪飾りが特徴です。声は盛岡市出身の声優・佐々木未来が担当しています。
最近では、盛岡市のホテルエースで岩手さちこのラッピング自動販売機や、缶バッジ・アクリルキーホルダーなどのグッズ販売、等身大パネルと撮影できるフォトスポット「さちスポット」の設置など、リアルイベントやコラボ企画も展開されています。こうした活動を通じて、岩手のファン拡大や地域の魅力発信に貢献しています。
参考:岩手県公認VTuber「岩手さちこ」
X:岩手さちこ❄岩手県公認VTuber (@iwate_vtuber)
YouTube:岩手さちこ【公式ch】 - YouTube
春日部つくし:埼玉県
春日部つくし(かすかべ つくし)は、埼玉県出身のバーチャルYouTuber・3Dモデラー・イラストレーターで、埼玉バーチャル観光大使を務めるご当地VTuberです。愛称は「つっく」。2018年から活動を開始し、YouTubeではゲーム実況、筋トレ、歌ってみた、雑談など多彩な配信を行い、2024年6月時点でチャンネル登録者数は17.7万人に達しています。
埼玉バーチャル観光大使としては、埼玉県の観光情報やご当地グルメ、名所の紹介、地域イベントのPRなどを積極的に発信しています。バスツアーや県庁オープンデーの特別コーナー「おしゃべりつくし」など、リアルイベントやオンラインイベントにも出演し、地元の魅力を広く伝えています。また、埼玉県主催のオーディションを経て2021年12月に観光大使に就任し、その後も任期延長されて活動を継続中です。
個人クリエイターとしても実績があり、VTuberやキャラクターの3Dモデル制作、イラスト提供、LINEスタンプやフレーム切手の販売なども手がけています。さらに、テレビやラジオ、朗読劇、各種イベント出演など、メディア露出も多数。天然でマイペースな性格とされ、好きな食べ物はカレーです。
近年は、バーチャル空間を活用したイベント「水辺でカンパイ!VIRTUALミズベリング」や、地元企業とのコラボ商品開発など、VTuberの枠を超えた地域振興活動にも力を入れています。
参考:埼玉バーチャル観光大使-埼玉県
X:春日部つくし💿バーチャル埼玉県民 (@kasukaBe_nyoki)
YouTube:春日部つくし - YouTube
Webサイト:HOME | 春日部つくしofficial
奈々鹿:奈良県
奈々鹿(ななか)は、奈良県の広報担当VTuberとして2024年3月13日にデビューした奈良県公式のバーチャルYouTuberです。奈良県広報広聴課の職員という設定で、県政や観光、イベント、地元の魅力などを若年層に向けて発信しています。
プロフィールは、年齢は秘密、誕生日は2月14日(奈良公園と同じ日)、身長157.5cm。趣味は百人一首と世界遺産めぐり、特技は「奈良のあるある」を聞いたり言ったりすること。グルメ・カメラ・音楽・漫画が大好きで、感情表現は控えめですが、興奮すると早口で饒舌になるというユニークな性格です。
活動内容は、奈良県の公式YouTubeチャンネルで観光地やイベント、施設などの紹介動画を月1本程度、ショート動画を月2回程度配信し、X(旧Twitter)でも奈良の情報を発信しています。また、県の広報施策として、10代~30代の若年層への訴求力を高め、県政の認知や理解向上を目的に制作されました。
デビュー1周年となる2025年3月には、記念イラストやアクリルスタンド、PC・スマホ壁紙の配布、ファンアートキャンペーンなども実施され、ファンとの交流や二次創作活動も積極的に推進しています。
奈々鹿は、奈良県の魅力を「マイペースに」「等身大で」伝えるキャラクターとして、今後も様々な広報活動を展開していく予定です。
参考:奈良県広報担当VTuber「奈々鹿」
X:奈々鹿【奈良県広報担当VTuber】 (@Vtuber_nanaka)
YouTube:奈良県公式総合チャンネル - YouTube
えびちゃん:江府町
鳥取県江府町のご当地VTuber「えびちゃん」は、江府町を代表する夏祭り「江尾十七夜」のイメージキャラクターとして2012年に誕生し、2021年からは江府町公認のVTuberとして本格的に動画での活動を始めました。えびちゃんは江府町初代観光大使も務めており、町の観光スポットや地域の魅力、地元イベントの情報などをYouTubeやSNSで発信しています。
活動内容は、江府町の観光案内や道の駅の紹介、地元の特産品や自然の魅力を伝える動画配信、町のイベントや他のご当地VTuberとのコラボ企画など多岐にわたります。また、島根県松江市の観光大使VTuber「ちぃさん」や鳥取県全域で活動する「おたねちゃん」とのコラボ動画も制作し、山陰地方全体の魅力発信にも取り組んでいます。
えびちゃんは、町の伝統や自然、地元の人々の温かさを伝える"まったり"とした雰囲気が特徴で、観光大使として江府町のPRに積極的に取り組んでいます。
参考:えびちゃんVTuberデビュー+観光大使任命!|江府町行政サイト
X:えびちゃん(古代地江美)公式 (@ebi_okudaisen)
YouTube:鳥取県江府町 - YouTube
のんのちゃん:上関町
山口県上関町公式VTuber「のんのちゃん」は、町花「野路菊(のじぎく)」の妖精をモチーフにした、上関町公認のマスコットキャラクターです。2024年3月1日にVTuberとしてデビューし、YouTubeやX(旧Twitter)を中心に、上関町の観光・イベント情報、地元の自然や文化、グルメなどの魅力を発信しています。
のんのちゃんは、SDキャラの姿で活動するのが特徴で、ゲーム配信や歌、さまざまな企画にも挑戦し、町のPRだけでなくエンタメ要素も積極的に取り入れています。明るく天真爛漫な性格で、誰とでも友達になれる親しみやすさが魅力です。プロフィール上、性別はなく、年齢は不明、誕生日は上関町創立日の2月1日。好きなものは山口県の郷土料理「けんちょう」とびわ、嫌いなものは雨の後に運動場に生えるワカメです。
もともとは町の案内キャラクターとして2016年に誕生し、2019年からは着ぐるみとしても町のイベントに参加。2024年からはVTuberとして本格的に活動を開始し、町の魅力を全国・世界に向けて発信しています。「花咲く海の町へようこそ!」を合言葉に、上関町の明るい未来を目指して、さまざまなコンテンツを展開しています。
参考:山口県上関町公式Vtuberのんのちゃん
X:のんのちゃん-山口県上関町公式VTuber- (@nonnokaminoseki)
YouTube:のんのちゃんねる -山口県上関町公式VTuber- - YouTube
紫式部:越前市
越前市は、紫式部が生涯で唯一都を離れて暮らした地であることを背景に、2024年2月1日から「紫式部」を公認VTuberとして活動させています。紫式部VTuberは「このさき1000年愛されたい行政系VTuber!」をキャッチコピーに、YouTubeやX(旧Twitter)、TikTokなどで越前市の歴史や文化、観光情報を若い世代に向けて発信しています。
プロフィール上は25歳、身長165cm、趣味はシュールなもの探しや筆文字。行政系VTuberながら自由奔放な発言が特徴で、親しみやすいキャラクターとして展開されています。また、越前市公認VTuber「若紫まい」とともにユニット「越前クロニクル」としても活動し、地域の魅力をエンタメ性を持って伝えています。
実際の活動内容は、イベントのインフォメーション担当や、子どもたちへの出前授業、地域の魅力発信動画の制作、オリジナルグッズ(アクリルスタンド等)の展開、新ビジュアルの制作など多岐にわたります。VTuberを活用したこれらの取り組みは、若者層への情報発信力強化と、越前市の郷土愛・観光促進を目指したものです。
参考:越前市公認VTuberについて
X:紫式部@行政系VTuber (@echizen_shikibu)
YouTube:紫式部@越前市公認VTuber - YouTube
信州なかの:中野市
信州なかの(しんしゅう なかの)は、長野県中野市公認のVTuberで、「中野市魅力発信バーチャルYouTuber」として2021年5月に誕生しました。モデルは中野市の「巡り逢いの巨石」をモチーフにした神様で、ウサ耳フード姿が特徴的です。主にYouTubeやSNSで中野市の農産物や観光、イベント情報などを若い世代や全国に向けて発信しています。
活動では、地元農産物の品種紹介や観光スポットの案内、イベントレポート、地域の名物PRなどを行い、2024年には市の公用車にラッピングされて「痛車」としても登場。さらにAI化も進められ、イベントや展示会で来場者とリアルタイムに対話できるAIアバターとしても活用されています。AI版はキャラクターの性格や方言、口ぐせを忠実に再現し、マルチデバイスや多言語対応も特徴です。
また、夜の姿「よるナカノ」など新キャラクターも登場し、グッズ展開やコラボ企画、クラウドファンディングによるミニドール制作など、地域活性化やファンとの交流にも積極的に取り組んでいます。信州なかのは、中野市の魅力を多角的に発信する現代的なご当地VTuberです。
参考:「中野市魅力発信バーチャルYouTuber」の名前が決定しました!|長野県中野市
X:信州なかの魅力発信Lab🐰🌹 (@nakanoshi_ureno)
YouTube:信州なかの魅力発信Lab - YouTube
自治体のVtuber活用の注意点
Vtuberを成功させるためには、いくつかの重要な注意点があります。これらを押さえておくことで、リスクを最小限に抑え、効果を最大化することができます。
キャラクター設定と世界観を統一する
Vtuberを長期的に運用するためには、キャラクター設定と世界観の一貫性が重要です。キャラクターの性格、口調、好みなどの設定を明文化し、運用担当者が変わっても一貫性を保てるようにすることが大切です。
また、地域の歴史や文化、特産品などをキャラクター設定に組み込むことで、地域との結びつきを強化し、より説得力のあるPRが可能になります。キャラクターデザインだけでなく、背景となる世界観や物語性を持たせることも、視聴者の興味を継続させるポイントです。
炎上リスク管理を徹底する
Vtuberの運用においては、SNSでの炎上リスク管理が重要な課題となります。政治的な発言や、特定の商品・サービスへの過度な言及、誤った情報発信などが炎上の原因となる可能性があります。
そのため、発信内容のチェック体制を構築し、複数の目でリスクを確認するプロセスを設けることが推奨されます。また、万が一炎上した場合の対応プランも事前に策定しておくことで、被害を最小限に抑えることができます。
住民や関係者との共感形成がカギ
自治体Vtuberを成功させるためには、地域住民や関係者との共感形成が重要です。一方的な情報発信だけでなく、地域住民や地元企業を巻き込んだ企画を実施することで、地域全体での盛り上がりを創出することができます。
例えば、地元イベントへの参加や、地域の人々との対話企画、地元企業とのコラボレーションなどを通じて、Vtuberを地域の「共有財産」として育てていく姿勢が大切です。住民参加型のコンテンツ制作や、ファンアート募集などの双方向コミュニケーションも有効な手段となります。
自治体のVtuber活用に関するよくある質問
Q1.自治体がVtuberを活用するにはどれくらいの費用がかかりますか?
A. 初期制作費は、2Dモデルなら30万〜100万円程度、3Dモデルなら100万〜300万円以上かかることが一般的です。
さらに、配信・動画制作・運用体制を整える場合、月額で10万〜30万円程度の運用コストも見込む必要があります。
ただし、スコープや運用内容によって大きく変動します。
Q2.自治体でVtuberを導入する場合、どこに依頼すればいいですか?
A. Vtuber制作会社、動画制作会社、または地域振興に強いクリエイティブエージェンシーに依頼するのが一般的です。
制作だけでなく、運用・PRまでトータルサポートできる会社を選ぶと安心です。
Q3.住民に受け入れられるか不安です。どうすればいいですか?
A. 住民参加型のコンテンツ企画(例:キャラクター名募集、地元紹介動画)を取り入れると、親しみを持たれやすくなります。
また、行政情報だけでなく「地域愛」をテーマにした発信を重視することが、共感形成に効果的です。
Q4.Vtuberを使った場合、どのぐらい効果が出ますか?
A. SNSフォロワー数増加、動画視聴数、観光サイト流入数アップなど、デジタル領域での成果が出やすいです。
一方で、短期間で劇的な移住者増加や経済効果を狙うには継続的な取り組みが必要です。中長期的な広報施策と捉えるのが成功のポイントです。
Q5.Vtuber運用にあたって気をつけるべき法律や規制はありますか?
A. 著作権(BGM・イラスト・映像素材)や肖像権、景品表示法(キャンペーン時)などには注意が必要です。
また、炎上リスク対策として、発言内容を事前にチェックするルールを設ける自治体も増えています。
まとめ:自治体はVtuber活用してPRをしよう
Vtuberの活用は、デジタル時代における自治体PRの新たな可能性を広げています。若い世代へのアプローチや地域ブランディング強化に効果的なツールとして、今後も多くの自治体での導入が進むことが予想されます。
成功のポイントは、単なる「流行り」として取り入れるのではなく、地域の特性や魅力をキャラクター設定に反映させ、継続的な運用体制を構築すること。そして何より、住民や関係者との共感形成を大切にし、地域全体で育てていく姿勢が重要です。
この記事で紹介した9つの事例や活用方法、注意点を参考に、あなたの自治体でもVtuberを活用した効果的なPR戦略を検討してみてはいかがでしょうか。新たな地域活性化の切り札となる可能性を秘めています。