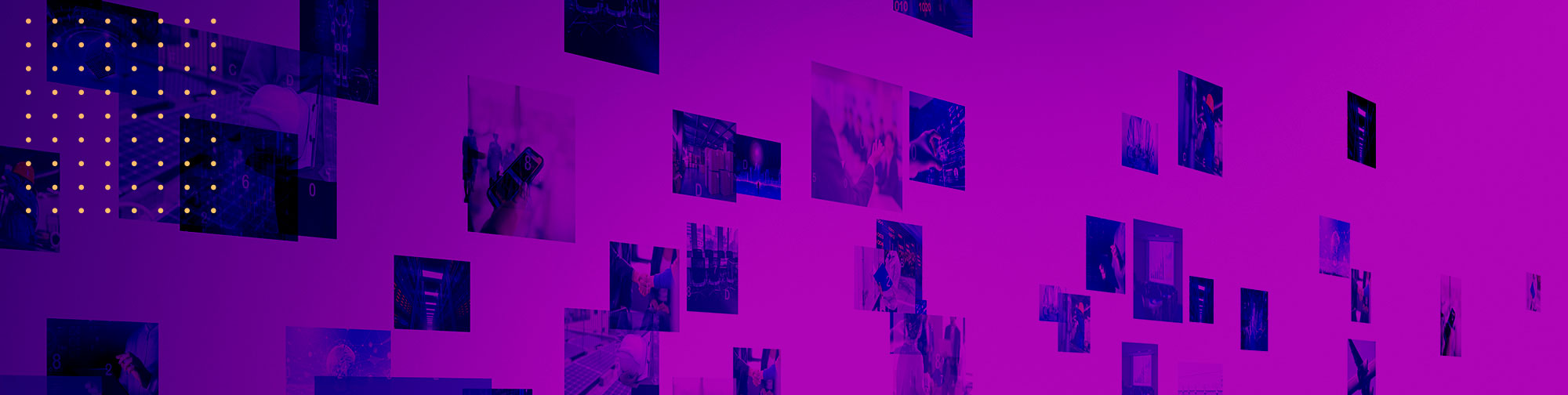記事一覧

CG動画とは?作成方法やおすすめのソフトを紹介
近年、様々な場面で目にするようになったCG動画。製品の紹介やプロモーション、教育コンテンツなど、多くの分野で活用されています。
「CG動画を作ってみたいけど、どうやって始めればいいの?」「どんなソフトを使えばいいの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、CG動画の基本的な知識から作成方法、おすすめのソフトまで、CG動画制作に関する情報を初心者にもわかりやすく解説します。
自分でCG動画を作りたい方はもちろん、制作会社に依頼したい方に向けて選び方のポイントも紹介しているので、CG動画に興味がある方はぜひ参考にしてください。
この記事でわかること
- CG動画とは何か、2DCGと3DCGの違い
- CG動画のメリットと、PR・教育・エンタメなどの活用シーン
- CG動画を自作する方法(使用ソフト)と制作会社へ依頼する場合のポイント
- CG動画制作の具体的な手順と注意点
- 効果的な動画を作るためのコツとおすすめソフトの選び方
- 信頼できるCG制作会社の選び方
目次
CG動画とは
CG動画とは、コンピューターグラフィックス(Computer Graphics)を用いて作成された映像のことです。手描きアニメーションや実写映像とは異なり、コンピュータ上で作成された映像や画像を指し、パソコンや専用ソフトを使ってキャラクターや背景、動きなどを仮想的に作り出します。
かつてはハリウッド映画や大作ゲームに限られていたCG制作技術ですが、ソフトウェアやハードウェアの進化、インターネット環境の普及により、現在では個人クリエイターから中小企業まで、様々な規模での活用が可能になっています。特に、YouTubeやTikTokといったプラットフォームの発展は、CG動画、そこから生まれたVTuberという文化を広く普及させる大きな要因となっています。
3DCGと2DCGの違い
CG動画は大きく分けて「3DCG」と「2DCG」の2種類があります。
3DCGは立体的な映像を制作する技術で、コンピュータ上に仮想空間を作り、人物や物体を縦・横・高さの三次元で表現します。照明やテクスチャ、アニメーションなどを設定することで、リアルな映像や奥行きのある表現が可能です。映画、ゲーム、CM、医療や製造業の可視化など幅広い分野で活用されています。
一方、2DCGは平面的な映像を制作する技術で、アニメやイラストなどでよく使われます。紙に描いたイラストをスキャンしてデジタル化したり、直接コンピュータ上で描いたりして制作されます。奥行きはなく、シンプルで分かりやすい表現が特徴で、イラストや素材作成にはAdobe IllustratorやPhotoshop、CLIP STUDIO PAINT、編集・アニメーション・合成などにはAdobe After Effectsなどのソフトを使って制作されることが多いです。
2DCGは比較的学習コストが低く、初心者でも始めやすいのに対し、3DCGはより専門的な知識とスキルが必要ですが、表現の幅が広いという特徴があります。
CG動画のメリット
個人から企業まで活用シーンが広がりつつあるCG動画。CG動画には、以下のようなメリットがあります。
- 複雑な情報を直感的に伝えられる
- 実写では表現できない演出が可能
- 制作コストを抑えることができる
それぞれ解説します。
複雑な情報を直感的に伝えられる
CG動画の最大のメリットの一つは、複雑な仕組みや内部構造、抽象的な概念など、実写では伝えにくい情報をシンプルかつ直感的に視覚化できる点です。例えば、新製品の機能や使い方、目に見えない仕組みなども、CG動画にすることで誰にでもわかりやすく伝えることができます。
また、オリジナルキャラクターの能力や設定、MVの世界観、未来的な空間演出など、「頭の中にあるイメージ」をそのまま形にできるのもCGならでは。言葉では伝えづらいことを、映像で一瞬にして共有できるのが、CG動画の大きな強みです。
実写では表現できない演出が可能
CG動画では、現実世界では撮影できないような表現も自由自在に作り出すことができます。例えば、製品の内部構造を見せたり、空を飛んだり、未来や過去の世界を再現したりなど、実写では不可能な演出もCG動画では全て可能です。
これにより、映画や広告、教育など幅広い分野で、従来の映像表現を超えた演出が可能に。CG動画の自由度の高さは、視聴者の興味を引きつけ、印象に残る映像を作る上で大きな強みとなります。
制作コストを抑えることができる
実写撮影では、ロケーション確保、俳優の手配、撮影機材など多くのコストがかかります。また、天候や時間帯に左右されることもあります。
一方、CG動画は一度背景やキャラクターなどの素材を作ってしまえば、何度でも使い回すことが可能。また、撮影場所の確保や出演者、天候の心配もなく、すべてを自分のPC上でコントロールできます。
修正も簡単にできるため、細かい調整や更新が必要なシーンでも柔軟に対応できます。そのため長期的に見れば、実写撮影よりもコスト効率が良くなる場合も多いです。
CG動画の活用シーン
CG動画は、あらゆる業界・分野で活用が進んでいます。特に、以下のような場面でCG動画が活用されています。
PR・プロモーション
CG動画は、企業のPRやプロモーションに活用することも効果的です。特に、製品やサービスの強みを視覚的に伝えたい場面、ブランドイメージを高めたい場面において、CG動画の表現力が強みとなります。
実写では伝えづらい仕組みやコンセプトを、CGなら誰でも理解できるように映像化することが可能です。製品の分解イメージや未来的な演出、視覚的な比較表現など、見るだけで「わかる」「記憶に残る」コンテンツを実現します。
例えば、以下のような活用例があります。
| 活用例 | 特徴 |
|---|---|
| 製品・サービス紹介動画 | 製品の構造や特徴、使い方を3DCGやモーショングラフィックスで可視化し、理解と購買意欲を高める |
| 企業ブランディング動画 | 世界観・ビジョン・信頼感をストーリー仕立ての映像で伝え、ブランド価値を浸透させる |
| 採用プロモーション | 職場の雰囲気や働き方を、ナビ動画やアニメーションでリアルかつ魅力的に演出。若年層への訴求にも強い |
| 事業紹介・展示会映像 | 複雑なビジネスモデルやソリューションを図解・CGアニメーションで表現。展示会・営業ツールとしても活用される |
教育・研修
CG動画は、単に派手な演出をするためだけのツールではありません。「情報を視覚で伝える力」が強いため、教育系・解説系コンテンツとの相性も抜群です。
例えば、機械の動作原理、複雑なデータフローなど、言葉や静止画だけでは理解しづらい抽象的な概念や目に見えない仕組みを、CGなら直感的かつ正確に再現できます。これにより、学習者の理解度と定着率を飛躍的に向上させることができます。
また、手順や操作などの解説にもCGが役立ちます。危険な作業手順や、高価な機器の操作方法などを、CGで安全かつ繰り返し学べるシミュレーション映像として提供できます。実践に近い形で学べるため、知識だけでなくスキル習得にも効果的です。
特に、オンライン学習やリモートワークが普及した現代において、場所を選ばずに高品質で均一な教育・研修を提供できるCG動画の価値はますます高まっています。視覚的な面白さも加わるため、学習者のモチベーション維持にも繋がります。
エンタメ
映画、ゲーム、音楽などのエンタメ分野では、CG動画は長年にわたり視覚的な魅力と没入感を生み出すために活用されてきました。迫力あるVFXや非現実的な世界観の演出に、CGは欠かせない存在です。
現在では、YouTubeや配信プラットフォームでもCGが活躍しています。印象的なオープニング映像や、アニメーション演出、オリジナルキャラクターの動きなど、視聴者の関心を引く表現に広く使われています。
このCG技術の進化形がVTuberです。CGはVTuberのような「バーチャルな存在」を通じて、新たな表現とコミュニケーションの形を創り出しています。CGで生まれたオリジナルキャラクターは、個人の顔として活動し、ファンと深い関係性を築く「人格のあるブランド」として機能します。
CG動画技術は映像制作だけでなく、VTuberやバーチャルイベント、メタバースのアバターなど若年層を中心とした新しいカルチャーやビジネスの基盤としても注目されています。
CG動画を作る方法
CG動画を制作するには、大きく分けて以下2つの方法があります。
- CGソフトで作る
- CG制作会社に依頼する
目的やスキル、予算に応じて、どちらが適しているかを判断しましょう。それぞれの違いや向いている人について解説します。
CGソフトで作る
個人でCG動画を作る場合は、専用のソフトを使って制作します。最近では無料でも高機能なツールが多く、初心者でも挑戦しやすい環境が整っています。
自分でCG動画を作る場合、以下のメリットがあります。
- 自由に創作できる
- スキルを身につければ継続的に制作コストを抑えられる
- ポートフォリオとして将来の仕事にも活用できる
一方で、ソフトの使い方をマスターするには時間がかかり、高品質な映像を作るには専門的な知識とセンスも必要になる点には注意が必要です。
近年は、YouTubeやUdemy、Skillshareなどでチュートリアル動画が豊富に公開されており、独学で学ぶハードルも下がっています。「まず1本作ってみたい」という人は、無料で使えるBlenderやVroid Studioから始めるのがおすすめです。
CG制作会社に依頼する
「時間がない」「高クオリティを求めたい」「ブランド用の動画を作りたい」という場合は、CG制作会社に依頼するという選択肢もあります。
制作会社に依頼するメリットは、以下のとおりです。
- プロによる完成度の高い映像が期待できる
- 自分では難しい表現(リアルな物理演算、群集、特殊効果など)も可能
- 企画から納品まで一括サポートしてもらえることが多い
一方で、制作費用がかかることや、細かい要望を伝えるためのコミュニケーションが必要になることはデメリットといえます。
依頼する際は、予算や目的、納期などを明確にした上で、相談することが大切です。Vtuberモデルの制作、MVの演出、企業案件など、目的に応じて制作会社を選ぶことで、クオリティと満足度の両方を高められるでしょう。
デジギアは「作りたいもの」「実現したいこと」を丁寧にヒアリングし、自作支援からプロによる制作代行まで、最適なソリューションを提案します。「どこまで自分でやって、どこからプロに任せるべきか」といったご相談も歓迎です。
CG動画の制作手順
CG動画制作は、多くの専門的な工程を経て完成します。制作するCGの種類や、最終的な用途によって細部は異なりますが、ここでは主に複雑な3DCG制作や、現代のトレンドであるリアルタイムCGに焦点を当てて、主要なステップを解説します。
制作会社に依頼する場合も、これらの工程を理解しておくと、コミュニケーションがスムーズになり、より効率的にプロジェクトを進めることができるでしょう。
企画をする
CG動画制作の第一歩は企画で、全ての制作の土台となる最も重要な工程です。何のために作るのか、誰に見てもらいたいのか、どんなメッセージを伝えたいのかを明確にします。この段階で予算や納期、大まかなビジュアルイメージも共有し、プロジェクトの方向性を固めます。
企画書やコンセプトシートを作成して、関係者間で共有しておくと良いでしょう。明確なビジョンがあることで、後の工程がスムーズに進みます。
構成を作成する
企画が決まったら、次は動画の構成を考えます。全体のストーリー展開、シーンの切り替え、カメラワーク、登場キャラクターの動き、セリフやナレーションなどを具体的に検討します。
視覚的なシナリオである絵コンテやプリビズと呼ばれる粗いアニメでの検証で映像イメージを具体化。関係者間の共通認識と合意形成が最大の目的です。ここでしっかり固めることで、後の高コストな制作工程での手戻りを防ぎ、効率的な動画制作に繋がります。
三面図を作成する
3DCGの場合、キャラクターや物体のモデリングに必要な三面図(正面・側面・背面など)を作成します。これは設計図のようなもので、これに基づいてモデリングを行います。2DCGやモーショングラフィックスでは省略可能です。
特にキャラクターデザインの場合は、表情・衣装差分もこの段階で設定しておくとよいでしょう。映像全体のトーンや世界観と調和するようにデザインすることが、統一感のある高品質な映像につながります。
モデリングをする
デザインや三面図をもとに、3Dソフトを使ってキャラクターやオブジェクト、背景などの立体的な形状データ(3Dモデル)を作成する工程です。これは彫刻のように、形を作り上げていく作業です。
キャラクターの顔や体のパーツ、物体の細かいディテールなどを丁寧に作り込みます。特にVTuberのアバターのようにアニメーションさせるモデルの場合、形状だけでなく、滑らかな動きのために考慮された適切なメッシュ構造(トポロジー)で作成することが非常に重要になります。アバターの場合は特に、魅力の出る顔まわりを丁寧に作り込みましょう。モデリングの精度が最終的な映像クオリティの基礎となります。
リギング
モデルに「骨組み(リグ)」を入れる作業がリギングです。これにより、モデルを自由に動かせるようになります。キャラクターの場合、表情を制御するためのリグも作られます。
人型キャラクターであれば関節構造を設定し、機械であれば可動部に対応するリグを作ります。特にキャラクターやVTuberのアバターにおいて、このリギングの質は、自然で豊かな表現力やリアルタイムでのスムーズな動きに直結します。 表情の変化を可能にするフェイシャルリグもこの段階で作られます。
スキニング
リグ(骨組み)と3Dモデルの表面(スキン)を結びつける作業がスキニングです。具体的には、モデルのどの部分がどの骨の動きにどれくらい影響を受けるかを設定(ウェイト付け)し、調整していきます。
例えば、腕を曲げたときに肩や服が自然に変形するように、顔の表情筋の動きに合わせて皮膚が適切に変形するように、細かく設定を調整します。このスキニングの精度が、キャラクターアニメーションやリアルタイムでの動きのリアリティと滑らかさを決定づけます。 自然な動きには、この段階での細かな調整が重要です。
ライティング
ライティングは、シーンに仮想的な光源を配置し、その種類、色、明るさ、影の落ち方などを調整することで、映像の雰囲気や見た目を決定づける工程です。
ライティングは、モデルの形状や質感を際立たせ、シーンの感情や時間帯、場所などを表現する上で非常に重要な役割を果たします。ドラマチックな陰影から明るくフラットな照明まで、表現したい世界観に合わせて設計していきます。
リアルタイムCGの場合は、リアルタイムでの処理負荷も考慮したライティング設定やライティング情報の事前計算(ベイク)なども行います。
レンダリング
レンダリングは、これまでの工程で設定された全ての情報(モデル、アニメーション、テクスチャ、ライティング、カメラなど)に基づいて、コンピューターが最終的な画像や映像を計算し出力する工程です。CG制作の制作プロセスによって、2種類のレンダリングがあります。
オフラインレンダリング(事前レンダリング):映画やテレビCMなど、最終的な映像を事前に計算して出力する方法です。複雑な計算(光の反射や拡散など)が可能で高品質ですが、1フレームの計算に数分〜数時間かかることも珍しくありません。
リアルタイムレンダリング:ゲームやシミュレーション、VTuberなどで使用される方法です。UnityやUnreal Engineといったゲームエンジン上で、毎秒数十フレームといった速度で画像を計算し、同時に表示します。オフラインほど複雑な計算は難しいですが、双方向性や即時性が可能です。
どちらの方式であっても、レンダリングによって生成された画像データが次の編集工程に進みます。
編集
レンダリングによって出力された画像シーケンス(またはリアルタイムエンジンの出力映像)を、動画編集ソフトで繋ぎ合わせ、一本の動画作品として完成させる工程が編集です。
Adobe Premiere ProやFinal Cut Proなどの編集ソフトを使用して、各シーンのタイミング調整、トランジション(場面転換)の挿入、テロップや図形の追加、BGM、効果音、ナレーションといった音響要素などの追加と調整を行います。
色調補正(カラーグレーディング)も含め、この最終工程で映像全体のトーン、リズムなど全体の雰囲気や伝えたいメッセージが最終的に形になります。VTuberのアーカイブ動画などの場合、ライブ配信の素材をこの編集工程で再構成・加工することもあります。
CG動画制作のコツ
CG動画制作を成功させるためには、いくつかのコツがあります。主なコツは、以下の3つです。
- 目的を明確にする
- オリジナルのキャラクター
- リアルな動き
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
目的を明確にする
CG動画制作で最初にやるべきことは、「この動画で何を達成したいのか」をはっきりさせることです。誰に向けて、どんなメッセージを届け、どんな行動(フォロー/視聴/購入など)を促したいのかを明確にすると、構成や演出の方向性がブレません。
例えば、SNSで拡散されたいならテンポ重視で15秒以内に、チャンネル登録を促したいならキャラクターの魅力を重視します。また、商品PRなら特徴や利点を分かりやすく、教育用なら理解しやすい説明を心がけるなど、目的に合わせた構成や表現を選びましょう。
目的が曖昧なまま進めると、伝えたいことがぼやけ、視聴者に印象を残しにくくなります。制作の前に、ターゲットとゴールをしっかり言語化しておくことが成功の第一歩です。
オリジナルのキャラクター
CG動画の大きな強みの一つは、現実には存在しない、オリジナルのキャラクターを創り出せる点です。オリジナルキャラクターを使うことで、ブランドや企業のイメージを視覚的に伝えることができます。
オリジナルキャラクターは、単なる登場人物ではなく、ブランドや企業の「顔」となる重要な存在です。ターゲット層の心に響くデザインと個性を持ったキャラクターは、視聴者の記憶に強く残り、親近感を生み出し、メッセージの伝達効果を高めます。
キャラクターデザインの際は、ターゲット層の好みや企業イメージに合わせることが大切です。また、キャラクターの個性や背景ストーリーを設定することで、継続的に活用できる資産となります。
リアルな動き
どんなに魅力的なデザインのCGキャラクターやオブジェクトでも、その動きが不自然だと、映像全体のクオリティや説得力は大きく損なわれます。特に人間やキャラクターのアニメーションにおいては、重力や慣性といった物理法則を考慮し、感情や意思を感じさせるような自然で豊かな動きが非常に重要です。
モーションキャプチャを活用したり、実際のダンス映像や動作を参考にしたりすることで、より自然で説得力のあるアニメーションが作れます。CG動画は動きが命。細部まで丁寧に動きを設計することで、作品の没入感と完成度が大きく向上します。
CG動画制作におすすめのソフト
CG動画を自作するなら、まずは目的に合ったソフト選びが重要です。ここでは、人気・定番の3つのCG制作ソフトを取り上げ、それぞれの特徴や適性をわかりやすく解説します。
| ソフト | Blender | Maya | Adobe After Effects |
|---|---|---|---|
| 特徴 | 無料でフル機能の3DCG制作 | 映画・ゲーム業界でも使用されるプロ向け | 2Dアニメ・MV・モーショングラフィックス向け |
| メリット | ・完全無料 ・3D制作が一通り可能 ・チュートリアルが豊富 |
・高機能なアニメーション ・業界標準ツール ・高度な制御が可能 |
・Adobe製品との連携が強力 ・テンポ感ある映像が作りやすい |
| デメリット | ・UIに慣れが必要 ・レンダリングにPCスペックが求められる |
・有料(年間契約制) ・操作習得に時間がかかる |
・サブスクリプションが必要 ・3D機能は限定的 |
| 向いている人 | ・初心者〜中級者 ・予算を抑えてCG制作を始めたい人 ・幅広い機能を使いたい人 |
・将来プロを目指す人 ・映画やゲーム制作に携わりたい人 |
・YouTube映像制作 ・MV制作 ・モーショングラフィックスを作りたい人 ・2Dアニメーションに興味がある人 |
Blender
Blenderは、無料で使える高機能な3DCGソフトウェアです。モデリング、スカルプト、リギング、アニメーション、シミュレーション、レンダリング、コンポジット、動画編集まで、3DCG制作ワークフローのほぼ全てをこの一つのソフトで行える統合型パッケージであることが大きな特徴です。
近年はアップデートを重ね、商用レベルの制作にも十分対応できる機能を備えています。予算をかけずに3DCG制作を始めたい個人やチーム、幅広い表現に挑戦したいクリエイターに強く支持されており、豊富な無料チュートリアルや活発なオンラインコミュニティも魅力。わからないことがあればすぐに質問できる環境が整っており、初心者にもおすすめです。
Maya
Mayaは、プロの現場で広く使われている3DCGソフトウェアです。映画やゲームなど、ハイエンドな制作環境で利用されています。
特にキャラクターアニメーション機能とリギング機能に非常に優れており、複雑で高品質なキャラクターの動きを作り込むことに強みがあります。高度なシミュレーション機能や豊富なプラグインも利用可能で、大規模なCG制作やリアルな動きを必要とする案件に向いています。
サブスクリプション形式で提供されているため、初期投資は比較的抑えられますが、継続的なコストがかかる点は考慮が必要です。ただし、学生や教育機関向けに無料ライセンスも提供されているので、学習目的での利用も可能。将来的に映像業界・ゲーム業界を目指す方には最適といえるでしょう。
Adobe After Effects
After Effectsは、2Dアニメーションやモーショングラフィックス、ビジュアルエフェクト(VFX)、コンポジット(合成)制作に特化したソフトウェアです。PhotoshopやIllustratorで作成した素材を読み込んで動きをつけたり、テキストアニメーション、図形アニメーション、パーティクルエフェクトなどを組み合わせたりすることができます。実写映像へのエフェクト合成やカラー補正にも広く使用されます。
特にロゴアニメーション、サービス説明動画のインフォグラフィック、Web広告用アニメーション、VTuberの配信画面デザインやオーバーレイ作成など、ビジネス動画やWebコンテンツで多用される視覚表現を効率的に制作するのに最適です。他のAdobeソフトとの連携がスムーズな点も大きなメリットといえます。
CG動画制作会社の選び方
CG動画を制作会社に依頼するなら、クオリティ・価格・納期だけでなく自分の目的に合った制作会社かどうかを見極めることが大切です。ここでは、個人クリエイターが安心して依頼できる会社を選ぶための3つのポイントを紹介します。
実績の有無
CG制作会社を選ぶ際は、まず実績を確認しましょう。過去にどのような案件を手がけてきたか、ポートフォリオやショーリールをチェックすることで、クオリティや得意分野が分かります。
特に、自分が求めるスタイルや業界に近い実績があるかどうかは重要なポイントです。例えば、医療機器のCG動画を作りたい場合は、同様の技術的な映像制作の経験がある会社を選ぶと安心です。
小規模でも優秀な制作会社は多数存在します。単に会社の規模だけでなく、実際の制作物の内容とクオリティをしっかり評価して、見極めることが大切です。
得意ジャンル
CG制作会社にはそれぞれ得意分野があります。以下のように、自分のプロジェクト内容とジャンルが一致している会社を選ぶと、スムーズに理想の仕上がりが期待できます。
| 得意分野 | 向いている制作案件例 |
|---|---|
| キャラクターアニメーション | Vtuberモデル、配信演出、OP・EDアニメ |
| モーショングラフィックス | MV、インフォグラフィック、広告用動画 |
| 建築・製品ビジュアライゼーション | 建築プレゼン、機械説明映像、リアル質感の再現 |
自分のプロジェクトに最適な会社を選ぶためには、制作したい内容と会社の得意ジャンルがマッチしているかを確認することが重要です。会社のウェブサイトやポートフォリオ、SNSで「どの分野の案件を多く手がけているか」を見れば、おおよその得意ジャンルが分かるでしょう。
制作スピード
納期が限られている場合は、制作スピードと対応の柔軟さが大きなポイントです。以下の点をチェックしましょう。
- 過去の納品事例で、どれくらいの期間がかかっているか
- 修正依頼に対して柔軟に対応してくれるか
- 初回の問い合わせ返信が早いか
これらを事前に確認しておくとよいでしょう。
コミュニケーションのスムーズさも制作スピードに影響します。質問や相談に素早く応じてくれる会社なら、制作過程での行き違いも少なく、効率的に進められる可能性が高いです。
そのため初回の問い合わせから返信までの速さも、その会社の対応力を示すひとつの指標と言えるでしょう。
CG動画制作に関するよくある質問
最後にCG動画制作によくある質問をまとめます。
Q1. CG動画の制作にはどれくらいの費用がかかりますか?
A. 制作内容や映像の長さ、3DCGの有無によって大きく変動します。
簡単な2Dアニメーションなら10万円前後から、複雑な3DCGやフルアニメーションは50万円〜100万円以上になることもあります。企画や修正の有無も影響します。
Q2. 自分でCG動画を作るのと、制作会社に依頼するのはどちらがいいですか?
A. 社内リソースや目的に応じて選びましょう。
簡単な動画であれば、Blenderなどを使って自作も可能ですが、クオリティや納期、表現力を求めるなら制作会社に依頼するのが安心です。
Q3. CG動画と実写動画はどう使い分ければいいですか?
A. 見せたい内容によって適性が異なります。
製品の内部構造や空想的な演出など、実写では撮影が難しい内容にはCG動画が向いています。一方、人物のリアルな表情や現場の雰囲気を伝えたい場合は実写が適しています。
Q4. CG動画を作るのにどれくらいの期間がかかりますか?
A. 企画から納品まで、短くて2〜4週間、複雑な3DCG動画であれば1〜3ヶ月以上かかることもあります。納期を明確にしてスケジュールを組むことが重要です。
Q5. CG動画の著作権や使用権は誰のものになりますか?
A. 制作会社との契約内容次第です。
制作会社が著作権を保有するケースもありますが、多くは「使用権譲渡」または「完全買い取り」の形になります。契約前に明確に確認しましょう。
まとめ:CG動画を作るならデジタルギア
CG動画は、複雑な情報を視覚的に伝えたり、実写では表現できない世界を創り出したりとさまざまな可能性を秘めたメディアです。映像編集・キャラクター演出・MV制作・情報発信など、個人クリエイターの活動をより魅力的に表現できる手段として、今後ますます重要性が高まっていきます。
自分で作る場合は、目的に合わせたソフトを選び、基本的な知識と技術を身につけることが大切です。Blenderのような無料ソフトから始めれば、初期投資を抑えつつスキルアップが可能です。
一方、高品質な映像が必要な場合や時間的制約がある場合は、専門の制作会社に依頼するのもおすすめです。制作会社を選ぶ際は、実績や得意ジャンル、制作スピードなどを考慮して、自分のプロジェクトに最適なパートナーを選びましょう。
CG動画は今後もテクノロジーの発展とともに進化し続け、さらに身近なメディアになっていくと予想されます。次に何から始めるべきか迷っているなら、まずは1つ、自分の世界観をCGで形にしてみることから始めましょう。