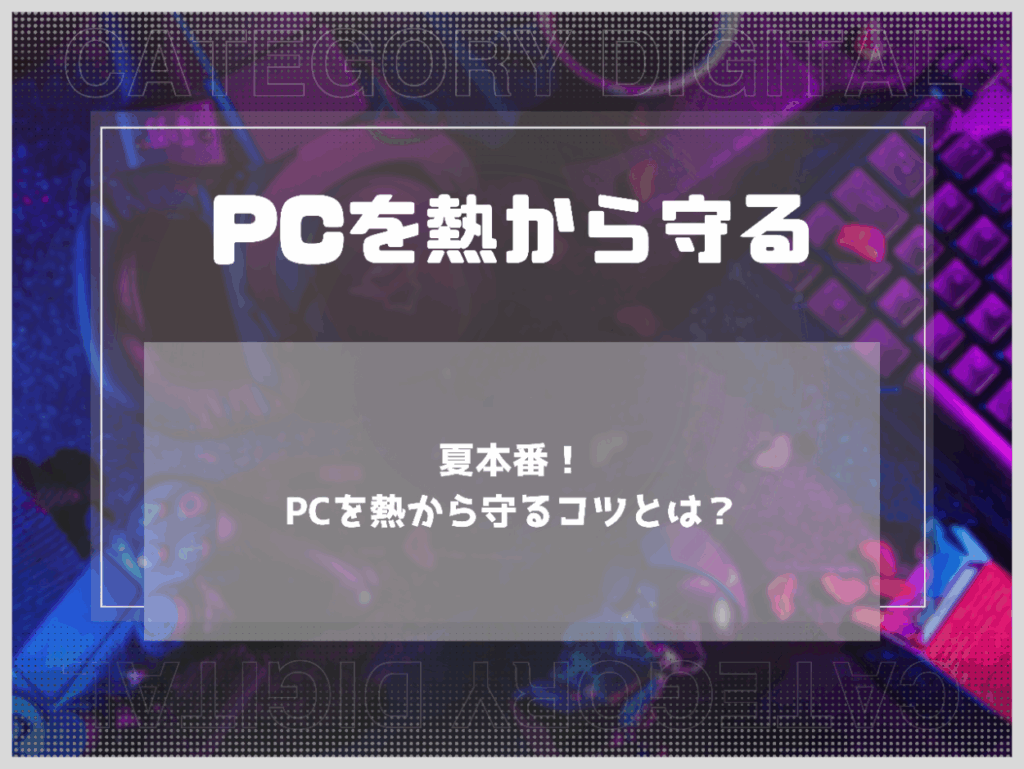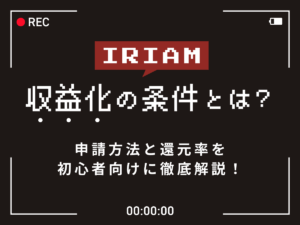はじめに
夏といえば暑い、暑いと言えば熱。
そう、パソコンの大敵である、熱の季節がやってきます。
パソコン内部が高温になると、挙動に異変が起きたり、処理が遅くなるなど、様々な不具合が発生します。
この状態を放置してしまうと、機器の破損や火災発生の危険にもつながってきます。
そこで今回はパソコンを熱から守る方法をご紹介します。
目次
1.初級編:手間をかけずにすぐできる工夫
2.中級編:少し手間がかかる工夫
3.上級編:手間と知識が必要な工夫
1.初級編:手間をかけずにすぐできる工夫
①エアコンで室温・湿度を適度に保つ
一般的にパソコンを使用する際の適正温度は、10~35℃といわれています。
しかし上限温度近くでは、すぐにPC本体の温度が上昇してしまいます。
そのため空調のある部屋では、室温を25~28℃に設定した方がいいでしょう。
またパソコンは高湿度にも弱いため、屋内での使用中はエアコンを動かし続けるのがベターです。
➁直射日光や熱源を避けて配置する
直射日光など、熱源の近くでの保管や使用は危険です。
真夏の直射日光のもとでは、電源を切っていても機器を破損させる恐れがあります。
夏はキャンプや海水浴など、屋外のイベントが盛りだくさんです。
ついうっかりしてしまいそうですが、機器の寿命を延ばすためには、日差しの元に置いたままにするのは絶対に避けましょう。
③通気口をふさがない
パソコンには吸排気のための通気口があります。
ここをふさいでしまうと、空気の流れが悪くなり排熱に問題が生じます。
デスクトップPCの場合は主に本体前部と背部に、ノートPCの場合は主に本体側部にあります。
使用時は通気口の位置を確認して、ふさがないように注意をしましょう。
④最新PCに買い替える
一般的に新しいPCの方が性能の割に発熱が少なく、排熱性能も優れています。
また使用年月が長くなると、どうしても内部のファンの性能が落ちてしまい、全体の冷却性能も低下してしまいます。
そのため排熱能力の低下を感じてきたら、思い切ってパソコンを新しいものに買い替えてもいいかもしれません。
参照や注釈
株式会社デンソー エスアイ
https://www.denso.com/group/denso-si/support/helpdesk/pc-tips
(2024-06-27)
2.中級編:少し手間がかかる工夫
①通気口やケース内のホコリを取り除く
通気口やPC内部のファンは、外部から空気を取り入れる構造であるため、ホコリもたまりやすくなります。
ノートPCの場合は通気口のホコリを、掃除機で吸い取るのがいいでしょう。
デスクトップPCの場合は、通気口だけでなく、本来ならカバーを開けて内部の基盤やファンにたまったホコリも、エアダスター(高圧の空気でホコリを吹き飛ばす、スプレー缶のこと。)で飛ばしたいところ。ですが、カバーを開けたり、中のパーツに触れることは、メーカー保証から逸脱し、自己責任になることが多いです。
静電気によってPCが故障する場合もあるため、特に空気が乾燥した季節は注意が必要です。
➁使わないソフトを終了する
同時に多くのソフトを使用していると、処理が増えて熱が発生しやすくなります。
そのため使用するソフトを絞ったり、使用していないソフトを終了させるのがいいでしょう。またバックグラウンドで立ち上がっているソフトを、終了させるという手法もあります。
③省電力設定を使用する
Windowsの省電力設定を使用する方法もあります。
画面の輝度を下げたり、数分間作業をしていないときには、スリープモードに入るようになる設定です。
Windows11で設定をする手順は以下の通りです。
(1)スタートメニューから「設定」を開く。
(2)左のメニューから「システム」を選択し、「電源とバッテリー」を選択し、「電源モード」をクリックする。
(3)「おすすめ」を選択する。
消費電力を抑えれば、同時に発熱も抑えることができます。
④冷却アイテムを使用する
パソコンを効率よく冷却したいときでも、氷や保冷剤を直接当てるのは控えましょう。急激な冷却は内部で結露を生じさせ、機器の故障を招くことがあります。
かわりに冷却パッドやノートPCクーラーなどの、冷却アイテムを使用するのがおすすめです。
冷却パッドはアルミや、熱伝導エラストマーなどの素材でできており、効率的に熱を放出するのに役立ちます。
ノートPCクーラーは金属製フレームに、ファンを1~6基程度搭載した機器で、ノートPCを乗せて風を当てることで熱を放出させます。
これらを状況によって使い分けたり、併用したりすることで効率的に冷やすことができます。
3.上級編:手間と知識が必要な工夫
①性能と負荷の関係を見直す
一般的なビジネス用ノートPCで高負荷な処理を行っていませんか?
例えば3DCGのレンダリング(描画)や、動画のエンコード(圧縮)などは、比較的高負荷の作業に当たります。
また複数のソフトを同時に使用しても、PCには強い負荷がかかります。
CPUやGPUの使用率が常に高い状態にあると、電力使用量が上昇しPC本体も常に熱を帯びるようになります。
しかしPCの性能が上がると同じ内容の処理でも、相対的に軽くなりますので、熱の発生を抑えることができます。
そのため自分のPCにはどれくらいの作業負荷が適切なのか、CPU使用率や実際の熱の発生具合を見ながら、見極めていく必要があります。
例えば、負荷のかからない作業は、持ち運びしやすいノートPCで行い、高負荷の作業はより高性能なデスクトップPCで行うなど、使い分けるのも手段です。
➁CPU温度限界を設定する
最近のPCに搭載されているCPUには、熱による破損や暴走、処理落ちを防止する機能が備わっています。
この機能は温度の上限をあらかじめ設定することで、一定以上の発熱を防止する効果があります。
通常は温度限界を設定していないか、もしくは100℃程度とされていますが、この設定を60~90℃程度に変更することで発熱を抑えることができます。
しかしその分CPU処理速度が落ちるので、注意が必要です。
CPU温度限界の設定はPCのBIOS画面(PCの基本設定をする画面)で設定します。
③【自作PCの場合】ケース内のエアフローをよく考える
エアフローとは、PCケース内部の空気の流れのことです。
エアフローを考えるとき、一般的には「空気の入り口→冷却経路→空気の出口」という順番で考えます。
特に問題が起きやすいのは冷却経路上です。
ケーブルなどが邪魔をして、空気がうまく流れないことがあります。空気がスムーズに流れて各部を冷却し、出ていくような、パーツ配置やケーブルの処理をよく考えましょう。
④【自作PCの場合】放熱性能の高いケースに買い替える
③同様、こちらも自作PCユーザー向けの対策です。
PCケースの素材や構造によっては、熱を放出しにくいものがあります。
特に静音タイプのケースは密閉性が高く、熱がこもりやすいといわれます。
ケースの強度などのバランスもありますが、アルミ製で通気口が多いケースの方が、放熱性は高くなります。
放熱対策のためにPCケースを買い替えるのも手段のひとつです。
まとめ
PCを熱から守る方法には、すぐにできる簡単なものから、知識を駆使するものまで、様々あります。
本記事を読んで、夏の熱対策を考えてくださいね!