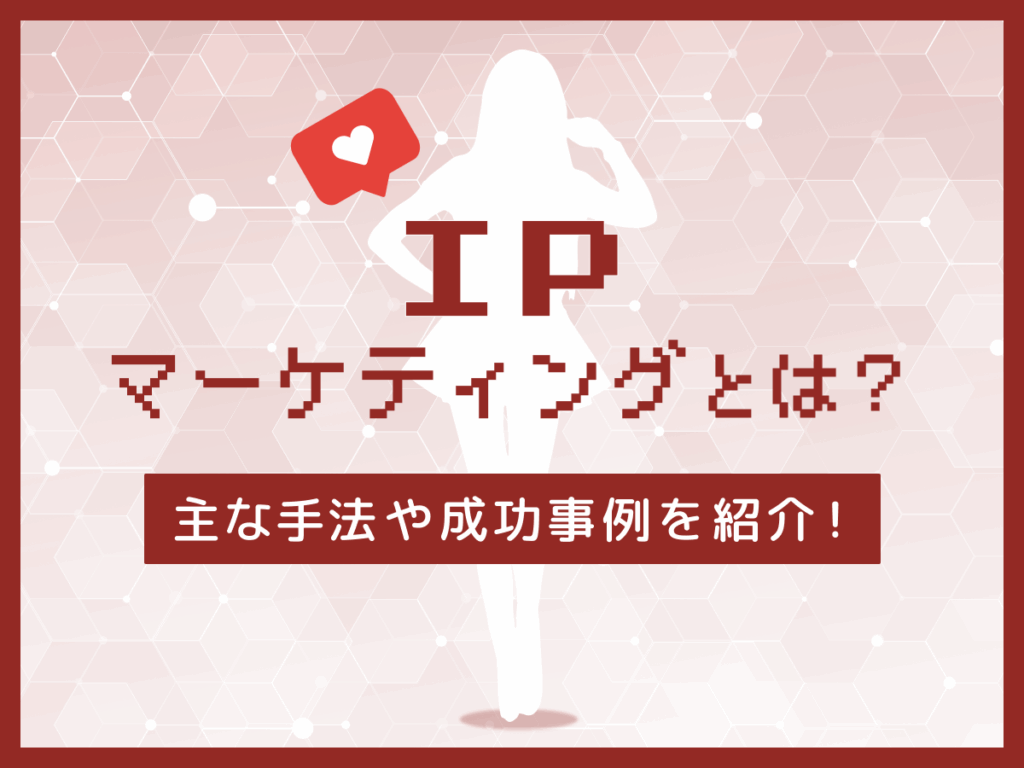「企業のマーケティング活動で注目を集めるのが難しい」「従来の広告では顧客の心に響かない」と悩んでいませんか?
近年、多くの企業が取り入れているのが、アニメや漫画、ゲームなど人気キャラクターを活用したIPマーケティングです。キャラクターのファンコミュニティを通じて訴求することで、広告色を抑えた自然で効果的なアプローチが可能になります。
特にSNSの普及により、キャラクターを中心とした情報拡散やファンコミュニティの影響力は年々強くなっています。その結果、キャラクターIPを活用した施策は幅広い業界で実績を上げ、注目を集めています。
本記事では、IPマーケティングの基礎知識から具体的な手法、成功事例、導入ステップまで、初心者にも分かりやすく徹底解説します。読み終えたときには、自社に最適な戦略の方向性が見えてくるはずです。
この記事でわかること
- IPマーケティングとは、アニメ・ゲーム・キャラクターなどの知的財産を活用する手法
- SNS時代にキャラクターの影響力が拡大し、ファンコミュニティとの結びつきで自然な訴求が可能
- コラボ商品、ライセンス、タイアップなど複数の実行手法と使い分けの考え方
- 認知拡大やファン経済圏参入のメリットと、費用やターゲット選定の注意点
- 適切なIP選定から契約、施策設計、効果測定まで段階的な導入ステップ
IPマーケティングとは
IPマーケティングとは、アニメ、漫画、ゲーム、映画などの「IP(Intellectual Property:知的財産)」を活用したマーケティング手法のことです。企業が人気キャラクターや作品の持つ魅力とファンベースを借りることで、自社の商品やサービスの認知度向上やブランドイメージの向上を図ります。
従来の広告では伝えきれなかった「親しみやすさ」や「物語性」を、すでに多くのファンに愛されているキャラクターを通じて表現できるのが大きな特徴です。例えば、食品メーカーが人気アニメとコラボした限定パッケージを発売すれば、そのキャラクターを応援するファンに自然に届き、購入動機へとつながります。
対象となるIPは非常に幅広く、国民的アニメや大ヒットゲームはもちろん、スポーツチームや映画シリーズ、さらには地域のご当地キャラクターやVTuberといったデジタル発の存在まで含まれます。近年は生成AIやモーションキャプチャ技術の進化により、企業が独自にオリジナルIPを開発・運用する動きも活発化しています。
重要なのは、IPが持つ「ファンの熱量」と「ブランド価値」を正しく理解し、自社の商品・サービスとの相性を見極めることです。人気度だけでなく、ファン層の年齢や嗜好、ブランドとの親和性を考慮することで、より効果的な施策につながります。
IPマーケティングが注目される理由
現代のマーケティング環境において、IPマーケティングが急速に注目を集めている背景には、消費者行動とメディア環境の変化があります。ここでは、IPマーケティングが重要視される4つの理由を詳しく解説します。
SNS時代のキャラクター影響力
X(旧Twitter)やInstagram、TikTokなどのSNS普及により、キャラクターの影響力は従来のマスメディア時代を超えて拡大しています。ファンが自発的にキャラクターの画像や動画をシェアし、二次創作を通じてコンテンツが拡散される現象が日常的に起きています。
企業がキャラクターとコラボすることで、そのキャラクターに関連する投稿が自然に増加し、広告費をかけずとも大きな露出効果を得られます。特に「バズる」コンテンツとなった場合、数百万人規模のリーチが期待できるため、費用対効果の高いマーケティング手法として注目されています。
ファンコミュニティとの強い結びつき
人気IPには、必ずと言っていいほど熱心なファンコミュニティが存在します。彼らは単なる消費者ではなく、IPに対して強い愛着や購買意欲を持っています。アニメファンがキャラクターグッズを積極的に買ったり、ゲームファンが関連商品を収集したりする「推し活」は、一般的な商品への購買行動とはまったく違います。
企業がこのファンコミュニティに受け入れられることができれば、非常に高いロイヤリティを持つ顧客を獲得できます。また、ファン同士の口コミや推奨によって、新規顧客の獲得も期待できるため、持続的な売上向上につながります。
広告嫌いを避ける自然な訴求
近年の消費者は従来の広告に強い拒否感を示す傾向があり、YouTubeの広告スキップや広告ブロックの利用は当たり前となりました。ところが、自分の好きなキャラクターが登場する広告やコンテンツに対しては、むしろ積極的に視聴したり共有したりするケースが多く見られます。これは、キャラクターが単なる広告媒体ではなく「楽しめるコンテンツ」として受け入れられているためです。
企業にとっては、広告色を抑えながらも商品を自然に訴求できるチャンスであり、ファンに「押し付けられている感」を与えない点が強みです。動画広告市場全体が伸びる中で、キャラクターを媒介とした広告施策は、広告嫌いを避ける有効な手段としてさらに注目を集めています。
成功事例の増加による普及
IPマーケティングが普及している背景には、実際の成功事例が増え続けていることも挙げられます。コンビニエンスストアとアニメのコラボキャンペーンや、自動車メーカーとゲームIPのタイアップなど、業界を問わず様々な成功パターンが確立されています。
こうした具体的な成果が業界を超えて共有され、企業が導入を検討しやすい環境が整いつつあります。また、IPホルダー側も企業コラボに積極的で、契約や監修のノウハウも確立されつつあります。そのため、リスクを抑えながら実行できる仕組みが整い、幅広い業種でIPマーケティングが実用的な選択肢として定着しつつあります。
IPマーケティングの主な手法
IPマーケティングにはいろいろな実施方法があり、会社の目的や予算、ターゲット層に合わせて最適な手法を選ぶことが大切です。ここでは代表的な5つの手法を詳しく解説します。
コラボレーション施策(キャラ×商品)
最も一般的なIPマーケティング手法が、人気キャラクターと自社商品のコラボレーションです。既存商品にキャラクターデザインを施したパッケージや限定仕様の商品を販売することで、ファン層の購買意欲を直接刺激できます。例えば、菓子メーカーがアニメキャラをあしらった期間限定パッケージを販売すれば、ファンは「コレクション目的」で複数購入する傾向があり、売上拡大につながります。
成功のポイントは、キャラクターの世界観と商品の特性を適切にマッチングすることです。可愛らしいキャラクターとスイーツ商品、クールなキャラクターと飲料商品など、イメージの親和性が重要になります。さらに単発施策ではなく、継続的なコラボ展開とシリーズ化を行うことで、話題性と売上の両面で持続効果を期待できます。
ライセンス利用(広告・グッズ展開)
IPライセンスを取得して、広告素材やオリジナルグッズの制作に活用する手法です。テレビCMやWebバナーにキャラクターを起用したり、ノベルティグッズとしてキャラクターアイテムを制作したりします。グッズ展開では、クリアファイルやマグカップなどの身近なアイテムにキャラクターをデザインすることで、企業ブランドを生活の中に自然に溶け込ませることができます。
ただし、ライセンス利用では、使用許可の範囲や期間、地域制限などといった契約条件を詳細に確認する必要があります。また、キャラクターのブランドイメージを損なわないよう、制作物のクオリティ管理やデザイン監修も重要です。長期的なライセンス契約により、一貫性のあるブランド戦略を築けるのも大きな魅力です。
タイアップキャンペーン
特定の期間に集中してキャラクターIPとのタイアップキャンペーンを実施する手法です。プレゼント企画、店頭イベント、SNSキャンペーンなどと組み合わせることで、短期間に大きな話題性を獲得できます。
タイアップキャンペーンの強みは、即効性のある集客効果に加え、ファンが「限定感」に惹かれて行動する点です。施策設計では、SNSでの拡散や店頭イベント、プレゼント企画などを組み合わせると効果が高まります。複数チャネルを同時展開すれば、オンラインとオフラインを横断する相乗効果も期待できます。タイアップは期間限定だからこそ熱量を集めやすく、ファンの購買行動を強く後押しする手法です。
オリジナルIPの開発
既存のIPを活用するのではなく、自社でオリジナルのキャラクターやストーリーを開発する手法です。初期費用や時間はかかりますが、長期的に独自のファンベースを形成でき、他社との差別化につながります。キャラクターデザインや世界観設定、ストーリー構築など総合的な企画力が求められますが、その分ブランドの自由度は非常に高いのが特徴です。
近年ではSNSやYouTubeを活用して少しずつファンを集め、徐々に商品やイベント展開へ広げるケースも増えています。さらに、生成AIやモーションキャプチャ技術の進化により、低コストで高品質なオリジナルIPを開発できる環境が整いつつあります。長期的なブランド戦略を見据える企業にとって、有力な選択肢のひとつです。
SNS・動画プラットフォームでの活用
YouTube、TikTok、Instagramなどのデジタルプラットフォームを活用したIPマーケティング手法は、若年層を中心とした幅広い層にアプローチできます。キャラクターが出演するショート動画や生配信、ハッシュタグを使った参加型キャンペーンなどは、自然に拡散されやすく費用対効果も高い施策です。
デジタルプラットフォーム活用の利点は、リアルタイムで反応を測定できる点にあります。再生回数やエンゲージメント数を即座に把握できるため、効果検証と改善をスピーディーに行えます。また、ユーザー生成コンテンツ(UGC)を促すことで、ファン自身がプロモーションに参加してくれる点も大きな強みです。各プラットフォームの特性を理解し、最適なコンテンツ形式を選ぶことが成功のポイントとなります。
IPマーケティングの成功事例
IPマーケティングの効果を具体的に理解するため、国内外の成功事例を分野別に紹介します。これらの事例から、効果的なIPマーケティングのヒントが見つかるでしょう。
国内事例(アニメ・ご当地キャラ)
日本国内では、多数のIPマーケティング成功事例があります。特に注目されるのは、大手コンビニチェーンと人気アニメのコラボキャンペーンです。「鬼滅の刃」とローソンのコラボでは、限定グッズの販売やオリジナル商品の展開により、通常の数倍の来店客数を記録しました。
ご当地キャラクターでは、熊本県の「くまモン」が代表的な成功例です。県の観光PR用に生まれたキャラクターが、今では全国的な人気を誇り、関連商品の経済効果は年間数千億円規模に達しています。地域活性化とマーケティングを両立した画期的な事例として評価されています。
また、食品業界では「初音ミク」とのコラボ商品が話題を集めました。ボーカロイドキャラクターとしての特性を活かし、音楽とグルメを結びつけたユニークなプロモーションにより、若年層の新規顧客獲得に成功しています。
参考:熊本県「くまモン」
参考:アサヒ飲料株式会社「ドデカミン×初音ミクキャンペーン」
海外事例(スポーツ・ゲームIP)
海外では、スポーツIPを活用したマーケティングが盛んです。アメリカのNBA(National Basketball Association)は、選手やチームをIPとして様々な企業とコラボレーションを行っています。特にスニーカーブランドとの連携は、数十億ドル規模の市場を形成しています。
ゲーム業界では、「ポケモン」の海外展開が大成功を収めています。任天堂とポケモン社は、各国の企業と戦略的なパートナーシップを結び、現地の文化や嗜好に合わせたマーケティング施策を展開しています。その結果、ゲームソフトだけでなく、関連グッズや映画、テーマパークなど幅広いビジネス展開を実現しています。
ヨーロッパでは、サッカークラブのIPマーケティングが注目されています。レアル・マドリードやバルセロナなどの名門クラブは、ユニフォームスポンサーシップだけでなく、ライフスタイルブランドとの提携により、サッカーファン以外の層にもアプローチしています。
参考:Forbes「NBAのチーム単位のスポンサー収入が2024–25シーズンに16.2億ドルに」
参考:ルイヴィトン「レアル・マドリードとのオフィシャル・パートナーシップの締結を発表」
VTuberやバーチャルIP活用の新潮流
近年急速に成長しているのが、VTuberやバーチャルキャラクターを活用したIPマーケティングです。「ホロライブ」や「にじさんじ」などのVTuberグループは、従来のアニメキャラクターとは異なり、リアルタイムでファンと交流できる特性を活かしたマーケティング展開を行っています。
企業とVTuberのコラボレーションでは、商品紹介やブランド体験型の配信が親しみやすく届きます。ホロライブ所属VTuberがロサンゼルス・ドジャースの公式イベントに登場し、現地ファンを巻き込んだリアルタイムの反響が得られたのは典型例です。
AI技術の発展により、企業が自社VTuberを活用したプロモーションも増えています。例えば、ロート製薬の公式VTuber〔ネバセイ・ココロ〕は、スキンケア商品の紹介に加えて肌ケアのコツを語るなど、広告色を抑えつつ視聴者との自然なコミュニケーションを実現しています。こうした取り組みは、単なる広告を超えて自社の顔として長期的にブランド価値を高める新しいIPマーケティングの形と言えます。
参考:「ロサンゼルス・ドジャース」と「ホロライブプロダクション」の第2回コラボレーション企画「hololive night」開催決定!
IPマーケティングのメリット
IPマーケティングを導入することで、従来の広告手法では得にくい独自の効果を生み出せます。ここでは代表的な4つのメリットを解説します。
認知度・好感度の向上
IPマーケティングの最も直接的なメリットは、ブランド認知度と好感度の大幅な向上です。人気キャラクターの知名度と好感度を借りることで、短期間での認知拡大が可能になります。特に、これまで自社ブランドに接触したことのない潜在顧客層に対して効果的にアプローチできるでしょう。
また、キャラクターが持つポジティブなイメージが自社ブランドに転移することで、商品やサービスに対する印象も向上します。堅いイメージの業界や商品であっても、親しみやすいキャラクターとの組み合わせにより、消費者の心理的なハードルを下げることができます。
ファン経済圏への参入
IPマーケティングの大きな魅力は、熱量の高いファンが形成する「ファン経済圏」へ直接参入できる点です。ファンは推しのキャラクターやコンテンツに対して高いロイヤリティを持ち、関連商品やイベントに積極的に投資します。また、ファン同士の口コミや推奨により、自然な顧客拡大効果も期待できます。
ファン経済圏の特徴は、単発の購入ではなく、継続的な購買行動が見込めることです。シリーズ商品の展開や定期的なコラボレーションにより、安定した売上基盤を構築できます。ファンのエンゲージメントが高いため、競合への顧客流出リスクの低減も期待できます。
ブランドの差別化
コモディティ化が進み、機能や価格だけでの差別化が難しい市場において、IPマーケティングは強力な差別化要因となります。同様の機能や価格の商品であっても、人気キャラクターとのコラボレーションにより、独自性と付加価値を創出できます。
これにより、消費者は「選ぶ理由」を明確に持つことができ、企業は価格競争から脱却することが可能です。IPが持つ世界観やストーリーを製品に反映させることで、ブランドは唯一無二の存在感を確立できます。
長期的な顧客ロイヤリティ形成
IPマーケティングを通じて獲得した顧客は、単なる商品購入者ではなく、ブランドファンとして長期的な関係を築きやすい特徴があります。キャラクターに対する愛着は自然にブランドへの愛着へと転化し、繰り返しの購入や関連商品の利用を後押しします。
また、IPファンは積極的に情報収集を行い、新商品や新サービスに対しても高い関心を示します。このため、新商品の導入時やブランド拡張時において、既存顧客からの支持を得やすく、マーケティングコストの削減にもつながります。
IPマーケティングの課題と注意点
IPマーケティングには多くのメリットがある一方、導入を検討する際には留意すべきいくつかの課題も存在します。これらの注意点を事前に理解し、適切な対策を講じることが重要です。ここでは、主な注意点を4つ紹介します。
ライセンス費用の高さ
人気IPを活用する際の最大のハードルは、ライセンス費用の高さです。特に国民的キャラクターや世界的に有名なIPでは、ライセンス料だけで数百万円から数千万円に上るケースも珍しくありません。加えて、売上に応じたロイヤリティの支払いも発生するため、収益性を慎重に検討する必要があります。
費用対効果を慎重に評価し、自社の予算規模と見込めるマーケティング効果を十分に比較検討することが重要です。また、複数年契約や複数商品での利用により、単価を下げる交渉も可能な場合があります。
ターゲット選定ミスマッチ
IPのファン層と自社商品のターゲット層が一致しない場合、期待した効果を得られない可能性があります。年齢層、性別、興味関心、購買力などの属性が大きく異なる場合、マーケティング施策が空振りに終わるリスクが高まります。
ミスマッチを防ぐためには、事前のマーケティングリサーチを通じて、IPファンの詳細な属性を分析し、自社のターゲットとの適合性を入念に検証することが重要です。小規模なテストマーケティングを実施し、実際の市場反応を確認してから本格展開する手法もおすすめです。
炎上リスク
IPマーケティングでは、キャラクターのファン感情を害するような施策を実施した場合、SNSなどで激しい批判にさらされる炎上リスクが存在します。IPの世界観を損なうような表現や、ファンが不快に感じる商品との組み合わせは、ブランドイメージの大幅な悪化につながる可能性があります。
IPホルダーとの綿密な事前協議と、ファンコミュニティの反応予測を行うことで、リスクを最小限に抑えることが重要です。万が一、問題が発生した場合に備え、迅速な対応体制を整備しておく必要もあります。IPマーケティングはファンの愛情に支えられる手法であるからこそ、その感情を尊重する姿勢が求められます。
効果測定の難しさ
IPマーケティングの効果は、従来のマーケティング指標だけでは測定が困難な場合があります。ブランド認知度の向上や好感度の変化、ファンコミュニティでの話題量など、定量的な測定が難しい要素が多く含まれます。
そのため、事前にKPI(重要業績評価指標)を明確に設定し、複数の指標で効果を測る仕組みが必要です。売上や来店数といった直接的な数値に加え、SNSでの拡散件数やアンケートによるブランド認知率の変化を組み合わせて評価するのが望ましいでしょう。最近ではソーシャルリスニングツールを活用し、ファンの声をリアルタイムで収集する企業も増えています。効果を正しく把握し改善につなげる仕組みを持つことで、投資の妥当性を判断でき、次回施策の精度も高められます。
IPマーケティングの導入ステップ
IPマーケティングを成功に導くためには、体系的なアプローチが必要です。ここでは、導入から運用までを5つのステップに分けて、具体的な実施方法を解説します。
ステップ1. 自社に合うIPの選定
最初のステップは、自社のブランドイメージや商品特性に最適なIPを選定することです。単純な人気度だけでなく、ターゲット層の一致度、ブランドイメージの親和性、長期的な活用可能性などを総合的に評価します。
IPの選定では、ファン層の年齢・性別・地域分布などの定量データを分析し、自社の顧客層と重なりがあるかを検証することが重要です。また、短期的なキャンペーン目的なのか、長期的にブランドを育てるのかによって選ぶIPも変わります。候補を複数比較し、ブランドとの親和性と活用の継続性を考慮した上で最適なIPを決めることがポイントとなります。
ステップ2. 権利関係の確認と契約
IPを活用するには、著作権や商標権、パブリシティ権など複数の権利をクリアする必要があります。契約では利用範囲や期間、地域、媒体、ロイヤリティ率などを明確に定めることが重要です。
特に人気IPでは、契約条件が厳格に設定されるため、細部の確認を怠ると後々トラブルにつながりかねません。契約前に法務担当や専門家にチェックを依頼し、自社に不利な条項が含まれていないかを確認するのがおすすめです。また、将来的に事業拡大を見据えるなら、追加利用の可否や長期契約の選択肢についても協議しておくと安心です。適切な契約はリスク回避だけでなく、IPホルダーとの信頼関係を築く上でも欠かせないプロセスです。
ステップ3. 施策設計(広告・商品・イベント)
契約を締結したら、具体的なマーケティング施策を設計します。IPの特性を最大限に活かすためには、広告・商品・イベントなどを組み合わせ、マーケティングファネルを意識した設計が求められます。例えば、認知拡大を狙うならSNSキャンペーンや動画広告、購買行動につなげたいなら限定コラボ商品や店頭イベントが有効です。
施策は単発で終わらせるのではなく、ファネルの各段階でファンの関心を継続的に引き出す仕組みを作ることが大切です。また、IPホルダーの承認を得ながら進める必要があるため、制作物の方向性やブランドとの親和性について事前に合意形成を図ることが重要です。顧客とIP双方にとって自然で心地よい体験を提供することが成果につながります。
ステップ4. KPI設定と成果指標
IPマーケティングの成功を測定するためには、あらかじめ明確なKPIを設定することが重要です。売上だけでなく、ブランド認知度や好感度、SNSでの言及量、顧客満足度などを組み合わせて多角的に評価することで、施策の効果を正しく把握できます。近年では、SNS分析やAIを活用した顧客データ解析ツールも普及しており、従来以上に精度の高い効果測定が可能になっています。以下は代表的なKPIと測定方法の一例です。
| 指標カテゴリ | 具体的なKPI例 | 測定方法 |
| 売上関連 | 売上高、販売数量、客単価 | 販売管理システム |
| 認知関連 | ブランド認知率、純粋想起率 | ブランド調査 |
| エンゲージメント | SNS言及量、シェア数、UGC数 | ソーシャルリスニング |
| 顧客関連 | 新規顧客数、リピート率、NPS(顧客推奨度) | 顧客データベース分析 |
KPIは短期的な売上効果を測るだけでなく、ブランド価値の向上やファン層の拡大といった長期的な成果を確認する役割も持ちます。数値データとともに、SNSや口コミから得られる定性的な反応も合わせて評価することで、IPマーケティング施策の真の効果を見極めやすくなります。
ステップ5. PDCAでの改善
施策実施後は、設定したKPIに基づいて効果を評価し、継続的な改善を行います。定期的な効果測定により、成功要因と改善点を明確にし、次回施策に反映させます。特にIPマーケティングはファンの反応が成功の鍵を握るため、SNSでの声やアンケート結果、販売データを総合的に評価することが重要です。
また、PDCAサイクルを回す中で、IPホルダーとの関係性を強化できるのも大きなメリットです。継続的に改善を重ねることで、短期的な話題づくりに終わらず、中長期的にブランド価値を高める仕組みが構築されます。
IPマーケティングに関するよくある質問(FAQ)
最後に、IPマーケティングの導入を検討する際によく寄せられる質問をまとめます。
Q1. IPマーケティングとインフルエンサーマーケティングとの違いは?
IPマーケティングは架空のキャラクターや作品を活用するのに対し、インフルエンサーマーケティングは実在の人物(インフルエンサー)を活用する点が大きな違いです。キャラクターはブランドの世界観に合わせて一貫したイメージを維持できるため、長期的な活用がしやすいメリットがあります。
一方、インフルエンサーは人間である以上、スキャンダルや発言によってブランドイメージに影響するリスクもあります。安定したブランド訴求を重視するならIP、即時性や話題性を重視するならインフルエンサーといった使い分けが効果的です。
Q2. IPマーケティングは小規模事業でも可能か?
はい、小規模事業でもIPマーケティングは可能です。大手企業向けの有名IPだけでなく、地域キャラクターやニッチなファン層を持つIPなど、予算に応じた選択肢があります。短期間の限定コラボやSNSキャンペーンなど、低コストで始められる方法もあります。
重要なのは自社の予算と目標に適したIPと手法を選択することです。無理に高額なライセンス料を支払うより、自社に適した規模での実施から始めることをおすすめします。
Q3. IPライセンス費用の目安は?
IPライセンス費用は、IPの人気度、利用範囲、利用期間によって大きく変動します。一般的には、初期費用として数十万円から数百万円、売上に応じて3〜10%程度のロイヤリティが設定されることが多いです。
地域キャラクターやニッチなIPでは数万円から利用可能な場合もあり、予算に応じた選択が可能です。正確な費用は、IPホルダーとの直接交渉で決まるため、複数のIPで見積もりを取ることをおすすめします。
Q4. IPマーケティングで失敗を防ぐためのポイントは?
失敗の多くは、IPファン層と自社ターゲットのミスマッチから生じます。そのため、事前にファン層の年齢・性別・嗜好などを分析し、自社顧客と重なっているかを確認することが重要です。
また、キャラクターの世界観を損なう表現は炎上につながりやすいため、施策設計時にはIPホルダーと丁寧に協議する必要があります。最近では、SNS上でテスト的に小規模キャンペーンを行い、反応を見てから本格展開する企業も増えています。万が一のリスクに備え、迅速な対応体制を整えておくことも重要です。
Q5.IPマーケティングはBtoB企業でも使える?
はい、BtoB企業でもIPマーケティングは効果的です。特に、展示会での集客や営業ツールとしての活用、従業員のモチベーション向上、企業ブランディングなどに活用できます。堅いイメージの業界ほど、IPの親しみやすさが差別化要素として機能します。
BtoB企業では、直接的な売上効果よりも、ブランド認知度の向上や営業機会の創出、顧客との関係強化などの効果を重視することが多いです。適切なIPを選択することで、BtoC企業同様の効果を期待できます。
まとめ:IPマーケティングでファンを増やそう
IPマーケティングは、従来のマーケティング手法とは異なり、現代の消費者行動に適応した効果的な手法です。人気キャラクターや作品の持つファンベースを活用することで、自然で親しみやすい形で商品やサービスを伝えられます。
成功のポイントは、自社に合ったIPを選び、ファンの期待を尊重しながら施策を設計することです。ライセンス費用やターゲット選定などの課題はありますが、事前準備と効果測定をしっかり行えば、大きなマーケティング効果を得ることができます。
IPマーケティングの本質は「ファンの力を借りるマーケティング」であり、大企業だけでなく中小企業でも取り組める手法です。認知獲得からブランド強化まで幅広く効果が期待できるため、ぜひ自社のマーケティング戦略に取り入れることを検討してみてください。あなたの企業も、IPマーケティングを通じて新たなファンコミュニティとのつながりを築いてみましょう。