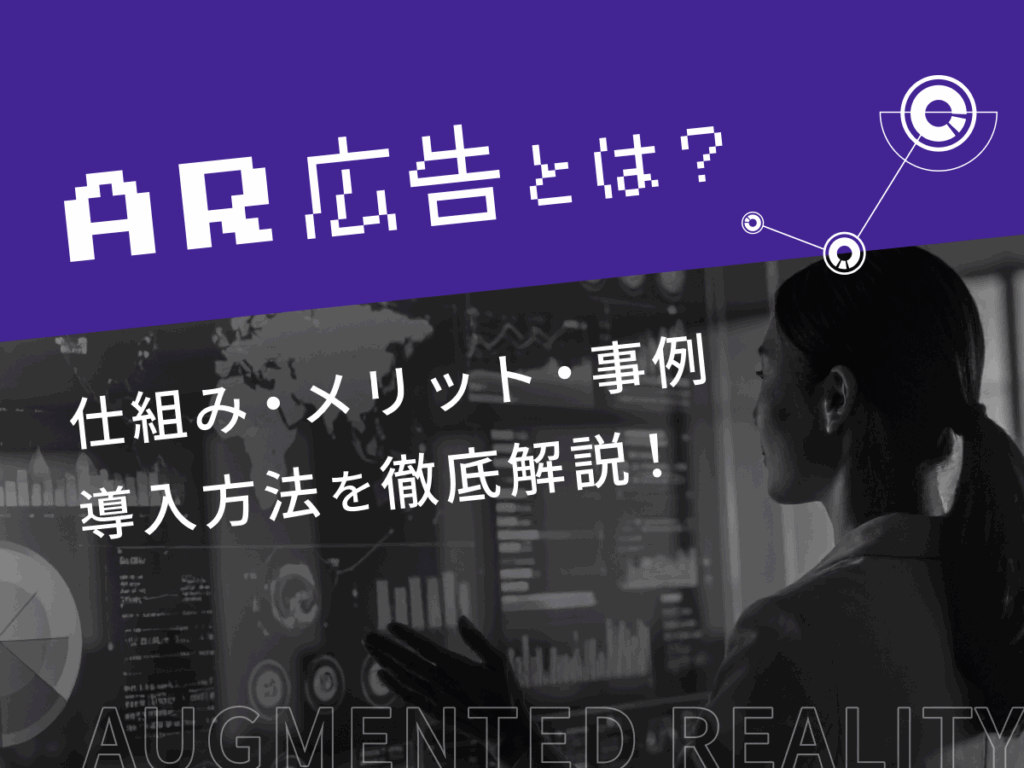「AR広告って最近よく聞くけど、実際どんな効果があるの?」「自社でも導入を検討しているが、費用や制作方法がわからない」と悩んでいませんか?
AR(拡張現実)広告は、従来の静的な広告とは異なり、ユーザーが実際に体験できるインタラクティブな広告として注目を集めています。実際に商品を試したり、キャラクターと一緒に写真を撮ったりと、体験を通じてブランドをより深く理解できるのが特徴です。
本記事では、AR広告の基本的な仕組みから具体的な活用事例、導入ステップまで、マーケティング担当者が知っておくべき情報を網羅的に解説します。最後まで読めば、AR広告の特徴を理解し、自社のマーケティング戦略に活用するためのヒントが得られるでしょう。
この記事でわかること
- AR広告は現実空間にデジタル情報を重ねる体験型広告の手法
- ロケーション型・ビジョンベース型・WebAR・SNS活用型の主な4種類がある
- 視覚的インパクト、SNS拡散性、ブランド愛着向上、CVR改善など大きなメリットがある
- 導入コストや効果測定などの課題もあり、事前の準備が必要
- 食品・アパレル・コスメ・エンタメを中心に多くの成功事例が出ている
AR広告とは?
AR広告とは、AR(Augmented Reality:拡張現実)技術を活用した次世代の広告手法のことです。現実空間にデジタル情報を重ね合わせることで、ユーザーが実際に触れて体験できるインタラクティブな広告体験を提供します。
従来の静的な広告とは異なり、AR広告では商品を実際に試したり、キャラクターと一緒に写真を撮ったり、仮想的な空間で商品情報を確認したりすることが可能です。こうした「体験を通じた理解」は強い印象を残しやすく、SNSで共有されることも多いのが特徴です。
近年は WebARやSNSフィルター など、専用アプリを使わずに利用できる形式が主流になってきました。ユーザーがQRコードを読み込むだけで体験を始められるため、導入ハードルが低く、企業にとっても活用しやすい環境が整いつつあります。AR広告は「見る広告」から「体験する広告」への転換を象徴する存在として注目度が高まっています。
AR広告の仕組みと種類
AR広告は技術的なアプローチによって、いくつかの種類に分類されます。それぞれの特徴を理解し、目的に応じて最適な手法を選ぶことが重要です。
ロケーション型AR広告
ロケーション型AR広告は、GPS情報を活用して特定の場所でAR体験を提供する手法です。ユーザーが指定された場所を訪れると、スマートフォンの画面上に仮想的なオブジェクトやキャラクターが現れ、その場所ならではの体験を楽しむことができます。
この手法は観光地での活用が特に効果的で、歴史的建造物にまつわる情報を3D表示したり、その場所にゆかりのあるキャラクターを登場させたりすることで、訪問体験を豊かにします。店舗では来店者限定のクーポンや限定キャラクターを出現させ、集客施策に活用される事例も増えています。位置情報を活用することで、確実にターゲット層にリーチできる点も大きなメリットです。
ビジョンベース型AR広告
ビジョンベース型AR広告は、カメラで特定の画像やマーカーを認識することでAR体験を起動する手法です。商品パッケージ、チラシ、ポスターなどの印刷物にマーカーを配置し、スマートフォンでスキャンすることで3Dキャラクターや動画コンテンツを表示できます。
この方式は既存の印刷広告との連携が容易で、パッケージデザインを大きく変更することなくデジタル体験を付加できる点が強みです。食品パッケージにかざすとレシピ動画が流れる、雑誌からそのままバーチャル試着ができるなど、印刷物の新しい価値を生み出します。比較的低コストで導入できるため、幅広い業界で活用が進んでいます。
WebAR広告(アプリ不要型)
近年急速に普及しているのがWebARです。専用アプリではなく、QRコードやURLリンクから直接ブラウザで体験できます。ユーザーはワンタップで参加できるため、参加ハードルが低いのが最大の特徴です。
また、アプリのダウンロードが不要なため、ユーザーのストレージ容量やプライバシーに関する懸念を軽減できます。また、iOS・Android問わず利用でき、幅広いデバイスでの利用が可能です。WebARの技術向上により、アプリ版と遜色ない高品質なAR体験を提供できるようになり、小売からエンタメ業界まで多くの企業がWebARを採用しています。
SNS・アプリを活用したAR広告
Instagram、TikTok、SnapchatなどのSNSプラットフォームが提供するAR機能を活用した広告手法です。各プラットフォームが用意した開発ツールを使用して、フィルターやエフェクトとしてAR体験を配信できます。
ユーザーが自然に遊びながら体験でき、撮影した写真や動画をそのままシェアできるため、拡散力が非常に高いのが特徴です。特に若年層との親和性が高く、Instagramのフィルターとして提供されたブランド体験を、ユーザーがストーリーズで友人に共有することで、自然な形でブランドの認知拡大が期待できます。また、各プラットフォームの既存ユーザーに直接リーチできるため、新規顧客獲得も期待できるでしょう。それぞれ独自のAR開発ツールを提供しており、比較的短期間で制作できるのも魅力です。
AR広告のメリット
AR広告は従来の広告手法にはない独特の優位性を持っています。ここでは、AR広告が企業のマーケティング活動にもたらす4つの主要なメリットについて詳しく解説します。
視覚的インパクトと体験価値
AR広告の一番の魅力は「目で見るだけでなく、実際に体験できる」点です。従来の静的な広告では伝えきれない商品の魅力や使用感を、ユーザーが実際に体験することで理解してもらえます。
例えば、家具業界では商品を実際の部屋に配置した状態を確認でき、アパレル業界では仮想試着によりサイズ感や着用イメージを把握できます。この「体験してから購入する」プロセスにより、購入後のミスマッチを減らし、顧客満足度の向上につながります。また、珍しい技術であることから、ユーザーの印象に強く残りやすく、ブランド記憶の定着にも効果的です。
SNSで拡散されやすい話題性
AR広告は体験そのものが新鮮で面白いため、ユーザーが自発的に写真や動画をSNSに投稿するケースが多くあります。ユーザーが体験したAR広告の様子を写真や動画で撮影し、友人やフォロワーに共有することで、オーガニックな口コミマーケティングが発生します。
特に、InstagramやTikTokでは「映える体験」として、積極的に共有される傾向があります。この拡散効果により、広告費以上のリーチを獲得できる可能性があり、マーケティングROIの大幅な改善が期待できます。また、ユーザー自身が発信者となることで、企業からの一方的な広告メッセージよりも信頼性の高い情報として受け取られます。
ブランド愛着やファン化の促進
AR体験は、ユーザーとブランドとの間に感情的なつながりを生み出し、長期的な愛着関係を構築する効果があります。従来の広告では一方的な情報提供に留まりがちでしたが、AR広告ではユーザーが能動的に体験に参加することで、より深いブランド理解が生まれます。
参加型の広告はユーザーにポジティブな感情を残しやすく、特に限定コンテンツやイベント連動型のARは「特別な体験」としてファン化を後押しします。長期的に顧客との関係を築きたい企業にとって、AR広告はロイヤルティ向上の有効な手段といえます。
コンバージョン率の向上
AR広告は、商品やサービスの理解度向上により、最終的なコンバージョン率の改善に寄与します。「実際に体験してから購入する」というプロセスを作れるため、購入への不安が軽減され、より確信を持って購買判断を行えるようになります。
特にオンラインショッピングでは、実物を確認できないという課題がありましたが、AR技術により仮想的に商品を試すことで、この課題を解決できます。さらに、AR体験からそのまま購入ページに誘導する導線を設計することで、体験から購入までのスムーズな流れを作り出せます。結果として、従来の広告手法と比較して高いコンバージョン率を実現できるケースが多く報告されています。
AR広告のデメリット・課題
AR広告には大きな可能性がある一方で、導入時には注意すべき課題も存在します。ここでは特に押さえておきたい3つのポイントを解説します。
導入コストと制作ハードル
AR広告の制作には、従来の広告制作よりも高度な技術と専門知識が必要となるため、初期導入コストが高くなる傾向があります。3Dモデリング、プログラミング、UX設計など、複数の専門分野のスキルが必要で、内製化が困難な場合は外部制作会社への依頼が必要となります。
AR技術自体がまだ発展途上の分野であるため、制作できる会社や人材が限られているため、費用が膨らみやすいのも現実です。品質の高いAR体験を提供するためには、相応の投資が必要であることを理解し、予算計画を慎重に立てることが重要です。ただし近年はWebARやSNSフィルターの普及により、比較的低コストで導入できる選択肢も増えています。小規模な施策からスタートし、効果を検証しながら段階的に拡大していくのが現実的なアプローチです。
効果測定の難しさ
AR広告の効果測定は、従来のデジタル広告と比較して複雑で、適切なKPIの設定が困難な場合があります。AR体験の「質」や「満足度」を定量的に測定することは難しく、単純なクリック率やインプレッション数といった従来のデジタル広告の指標だけでは真の効果を把握できません。
体験時間、AR機能の使用率、共有回数、体験後の行動変化など、AR特有の指標を設定し、継続的にデータを収集・分析する必要があります。また、AR体験がブランド認知や購買意向に与える長期的な影響を測定するためには、GoogleアナリティクスやSNSの解析機能などさまざまなマーケティング手法との組み合わせが必要になる場合もあります。効果測定の仕組みを事前に設計し、適切なツールを導入することが重要です。
ユーザー体験に依存するリスク
AR広告の成功は、ユーザーの体験品質に大きく依存するため、技術的な不具合やUX設計の不備が直接的にブランドイメージに影響を与えるリスクがあります。ARアプリが正常に動作しない、読み込みが遅い、操作が分かりにくいなどの問題が発生すると、ユーザーにネガティブな印象を与えてしまう可能性があります。
また、ユーザーのデバイス環境(機種、OS、カメラ性能など)によって体験品質が大きく左右されるため、幅広いデバイスでの動作テストが必要です。さらに、ARという新しい技術に慣れていないユーザーにとっては、操作方法が分からずに体験を諦めてしまうケースもあります。直感的で分かりやすいUI/UXの設計と、十分なテスト期間の確保が成功のポイントとなります。
AR広告の活用事例
AR広告は様々な業界で実際に活用され、成果を上げています。ここでは業界別の代表的な成功事例を通じて、AR広告の具体的な活用方法と効果について詳しく見ていきましょう。
食品業界(商品パッケージ×AR体験)
食品業界では、商品パッケージにAR機能を組み込むことで、調理方法やレシピ情報を提供する事例が増えています。ユーザーがスマートフォンで商品パッケージをスキャンすると、その商品を使った料理のレシピ動画が再生されたり、栄養成分の詳細情報が表示されたりします。
実際の事例としては、2025年春にカルピスが「『カルピス』からの挑戦状キャンペーン」を展開しました。専用サイトのARカメラを起動すると、画面に流れるボトルを数えるゲームがスタート。「#7月7日はカルピスの誕生日」のハッシュタグとともにSNS投稿することで、サイト滞在時間を延ばしつつユーザーの参加を促進しました。
参考:アサヒ飲料株式会社
アパレル業界(試着・カタログ連動)
アパレル業界では、バーチャル試着機能がAR広告の代表的な活用例となっています。ユーザーは自宅にいながら、スマートフォンのカメラで自分の姿を映しながら様々な服装を試すことができ、サイズ感や色合いを確認してから購入判断を行えます。
海外の例として、Nikeは2025年オリンピック期間中にパリの空を巨大なAR空間に変える「Victory Mode Paris」をSnapchatのARレンズで展開しました。リアル空間をゲームフィールドに変え、リアルな体験とデジタル体験を融合したユニークな施策として、2,300万回以上の広告インプレッションを記録しています。身体の動きに反応する没入感の高い演出で、ブランドの世界観と体験価値を同時に訴求しました。
参考:NIKE
エンタメ業界(ライブ・映画プロモーション)
エンターテイメント業界では、映画やアニメ、音楽ライブのプロモーションにAR技術を活用する事例が増えています。映画の公開に合わせて、キャラクターが現実空間に現れるAR体験を提供したり、音楽アーティストのライブ会場でファンがARフィルターを使って記念撮影を楽しめる企画が人気を集めています。
2022年、バーチャルバンドGorillazが「Cracker Island」リリースに合わせて、ニューヨークとロンドンの街中に巨大ARアバターを登場させるイベントを開催しました。タイムズスクエアやピカデリーサーカスに、バンドの巨大アバターが現れるというインパクト大の体験で、GoogleのAR技術を用いたこの試みはファンとの距離をぐっと縮めるプロモーションとして注目されました。
参考:ゴリラズが新曲を公開
コスメ業界(バーチャルメイク体験)
コスメティック業界では、ARを活用したバーチャルメイク体験が非常に人気となっています。ユーザーはスマートフォンのカメラで自分の顔を映しながら、様々な化粧品を試すことができ、実際に購入する前に仕上がりイメージを確認できます。
世界最大手の化粧品メーカーであるロレアルは、AR・AI技術を活用したバーチャルメイクアプリを提供しています。ユーザーはアプリで自分の顔を認識させ、ロレアルの様々な商品をバーチャルで試すことができます。この技術は、同社のECサイトや小売店の店頭でも活用され、顧客の購買前の不安を解消し、売上向上に貢献しています。
参考: ロレアルのバーチャルメイクアプリ「YouCam メイク」
AR広告の導入ステップ
AR広告を成功させるためには、計画的なアプローチが重要です。ここでは、初めてAR広告を導入する企業が押さえるべき5つのステップについて解説します。
ステップ1.目的とターゲットを明確化
AR広告を始める際は、まず「なぜAR広告を行うのか」「誰に届けたいのか」を具体的に定義することが大切です。ブランド認知を広げたいのか、購買意欲を高めたいのか、ファンとの関係を強化したいのかなど、達成したいゴールを明確にしましょう。
加えて、ターゲット層の年齢や性別、ライフスタイル、デジタルリテラシーレベルなどを詳細に分析し、AR技術に親和性の高い層かどうかも検討します。特に、スマートフォンの操作に慣れているZ世代やミレニアル世代は、AR体験に対する受容度が高い傾向があります。目的とターゲットを具体化することが、次のステップを成功させる基盤となります。
ステップ2.手法(WebAR・アプリ型)を選定
目的とターゲットが明確になったら、適切なAR実装手法を選択します。主な選択肢としては、WebAR(ブラウザベース)、専用アプリ型、SNSプラットフォーム活用型があり、それぞれ異なるメリットとデメリットを持っています。
WebARは導入のハードルが低く、幅広いユーザーにリーチできますが、表現力に一定の制限があります。専用アプリ型は最もリッチで没入感のあるAR体験を提供できますが、アプリのダウンロードが必要でユーザーの参加ハードルが高くなります。SNS活用型は既存のユーザーベースを活かせるメリットがありますが、プラットフォーム側の仕様変更の影響を受けやすいリスクがあります。予算、技術的要件、ターゲットユーザーの行動パターンを総合的に考慮して、最適な手法を選定することが重要です。
ステップ3.体験設計とクリエイティブ制作
AR広告の成功は、ユーザー体験の質に大きく依存するため、体験設計とクリエイティブ制作は特に重要なステップです。ユーザーがAR体験を通じて「何を感じ、どのような行動を取ってほしいか」を具体的に設計します。
体験設計では、ARコンテンツの起動方法、操作方法、体験内容、体験後の導線まで、ユーザージャーニー全体を詳細に設計します。直感的で分かりやすい操作性を重視し、初めてAR体験をするユーザーでも迷わず楽しめるよう配慮します。クリエイティブ制作では、ブランドの世界観を表現しながら、AR技術の特性を活かした魅力的なビジュアルを制作します。3Dモデル、アニメーション、サウンドなど、各要素を組み合わせて統一感のある体験を創造することが求められます。
ステップ4.配信チャネルの選択(SNS・OOH・Web)
制作したAR広告を効果的にユーザーに届けるため、適切な配信チャネルを選択します。選択肢としては、SNSプラットフォーム、屋外広告(OOH)、自社Webサイト、印刷媒体などがあり、それぞれ異なるリーチ特性を持っています。
SNSプラットフォームは若年層への訴求力が高く、拡散効果も期待できますが、競合コンテンツも多いため注目を集める工夫が必要です。屋外広告との連携では、QRコードを活用してAR体験への導線を作ることで、リアルとデジタルを融合した体験を提供できます。自社Webサイトでは、既存顧客やブランドに関心の高いユーザーにより深い体験を提供できます。複数のチャネルを組み合わせることで、より幅広いユーザーにリーチし、相乗効果を生み出すことも可能です。
ステップ5.効果測定と改善
AR広告の効果を正しく評価し、継続的な改善を行うためには、適切な指標設定と測定システムの構築が必要です。AR特有の指標と従来のマーケティング指標を組み合わせて、多角的に効果を評価します。
効果測定ではAR体験の開始率、完了率、体験時間、シェア率、体験後のWebサイト訪問率、最終的なコンバージョン率などを指標に設定します。さらに購買や資料請求など最終的な成果にどの程度結び付いたかを追跡することで、ROIを可視化できます。
また、ユーザーアンケートやインタビューを通じて、体験の満足度や印象、購買意向への影響なども調査します。収集したデータを分析し、ユーザー行動のパターンや離脱ポイントを特定することで、次回の改善点を明確にします。AR広告は比較的新しい手法のため、トライアル&エラーを繰り返しながら最適化していくアプローチが重要です。
AR広告に関するよくある質問(FAQ)
AR広告の導入を検討する際によくある質問について、詳しくお答えします。
AR広告とVR広告の違いは?
AR(拡張現実)とVR(仮想現実)は混同されがちですが、全く異なる技術です。AR広告は現実世界にデジタル情報を重ね合わせる技術で、ユーザーは現実空間にいながらデジタルコンテンツを体験できます。一方、VR広告は完全に仮想的な空間でのコンテンツ体験となり、専用のヘッドセットが必要になることが多いです。
AR広告の方がより手軽で日常的に利用でき、スマートフォンやタブレットがあればすぐに体験可能です。また、現実世界との融合により、商品の実際の使用感や配置イメージなどをより直感的に理解してもらえる特徴があります。マーケティング用途では、ARの方がユーザーの参加ハードルが低く、広範囲なリーチが期待できます。
AR広告は小規模企業でも導入できる?
小規模企業でもAR広告の導入は十分可能です。近年、WebARプラットフォームやSNSのAR機能が充実しており、大規模な開発投資なしでもAR体験を提供できるようになっています。
特に、InstagramやTikTokなどのSNSプラットフォームが提供するARフィルター作成ツールを活用すれば、比較的低コストでAR広告を制作できます。また、既存の商品写真や動画素材を活用したシンプルなAR体験から始めて、効果を確認しながら段階的にレベルアップしていく方法もおすすめです。重要なのは、技術的な高度さよりも、ユーザーにとって価値のある体験を提供することです。
AR広告の導入コストの目安は?
AR広告の導入コストは、実装方法や求める品質レベルによって大きく変動します。簡単なWebARやSNSフィルターであれば10万円〜50万円程度から始められ、高品質なアプリ型AR体験では250万円以上かかる場合もあります。
| 実装方法 | 概算費用 | 特徴 |
| SNSフィルター | 10万円〜30万円 | 短期間で制作可能、SNS拡散効果が高い |
| WebAR | 30万円〜100万円 | アプリ不要、幅広いデバイスに対応可能 |
| 専用アプリ | 250万円〜1,500万円 | 高品質体験が可能、長期利用や大型施策に適する |
初回導入時は比較的シンプルなものから始めて、効果を検証しながら投資を拡大していくことをおすすめします。
AR広告の効果測定はどう行う?
AR広告の効果測定は、従来のデジタル広告指標とAR特有の指標を組み合わせて行います。基本的な指標として、インプレッション数、クリック率(AR体験開始率)、体験完了率、平均体験時間などがあります。
さらにAR特有の指標として、AR機能の使用率、3Dオブジェクトとのインタラクション回数、ARカメラ機能の利用率、体験のシェア率なども重要です。最終的には、AR体験後のWebサイト訪問率、資料請求率、購入率などのコンバージョン系指標で効果を評価します。GoogleアナリティクスやSNSの解析機能を組み合わせることで、定量的な効果を把握できます。ユーザー調査を併用すれば定性的な評価も得られ、改善に役立ちます。
AR広告はどの業界と相性がいい?
AR広告は特に、商品の「体験価値」や「ビジュアル要素」が重要な業界と相性が良いとされています。アパレル・ファッション、コスメティック、家具・インテリア、食品・飲料、エンターテイメント業界での成功事例が多く報告されています。
これらの業界では、実際に商品を試したり、使用イメージを確認したりすることが購買判断において重要な要素となるため、AR技術による仮想体験が高い価値を提供します。さらに、BtoB業界でも、複雑な製品の説明や設備の設置イメージ、建設・建築分野での完成予想などでAR活用が進んでいます。体験を通じて理解が深まる商材であれば、業界を問わず有効活用できます。
まとめ:AR広告は「体験を共有させる広告」
AR広告は単なる技術的なトレンドではなく、消費者の購買行動や情報収集方法の変化に対応した次世代の広告手法です。従来の「見る」だけの広告から「体験する」広告へと変わり、より深いブランド理解と感情的なつながりを生み出すことが可能になりました。
特にSNS全盛の現代においては、AR広告の「体験を共有したくなる」特性が強力な武器となります。ユーザーが自ら体験し、その様子をSNSで共有することで、企業からの情報発信を超えた信頼性の高い口コミマーケティングが実現します。
AR広告は、BtoC業界だけでなく、BtoB業界でも活用が広がっています。複雑な製品の説明、設備の導入イメージ、研修・教育コンテンツなど、「体験による理解促進」が価値を生むあらゆる場面でAR技術の可能性が広がっています。
今後、AR技術のさらなる普及と低価格化により、より多くの企業がAR広告を活用できるようになることが予想されます。早期にAR広告に取り組むことで、競合他社との差別化と顧客との新しい関係性構築を実現し、将来のマーケティング戦略において有利なポジションを築くことができるでしょう。