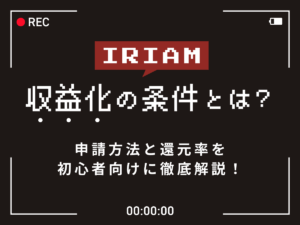スマートフォンの普及とテクノロジーの進化により、AR(拡張現実)は私たちの生活やビジネスに身近なものになってきました。「AR制作会社に依頼したいけど、どこを選べばいいのか分からない」「ARをビジネスに活用したいけど、どんな場面で効果があるの?」と悩んでいませんか?ARは適切に活用すれば、プロモーションや販促、教育、空間提案など様々な場面で強力なツールになります。この記事では、AR制作会社の選び方から実際におすすめの会社まで、AR活用を検討している方に役立つ情報をまとめました。この記事では、以下の5つのポイントで解説します。
【記事のまとめ】
- AR技術は現実空間にデジタル情報を重ねることで、ユーザーに新しい体験価値を提供できる
- 販促、イベント演出、教育、不動産、エンタメなど業界を問わず様々な活用シーンがある
- AR制作会社選びは対応ARの種類、実績、一貫対応力、3D制作スキル、提案力がポイント
- エム・ソフト、vartique、ジグノシステムなど実績豊富な制作会社が多数存在する
- 目的や予算に応じた最適なパートナー選びが、成果の出るARコンテンツ実現の鍵となる
AR制作とは
AR制作とは、現実の世界にデジタル情報を重ね合わせる「拡張現実(Augmented Reality)」技術を活用したコンテンツやアプリケーションの開発プロセスを指します。スマートフォンやタブレット、ARグラスなどのデバイスを通して、現実世界に3Dモデル、アニメーション、テキスト、音声などを表示させることで、ユーザーに新しい体験価値を提供します。
AR制作には、プランニングから3DCG制作、プログラミング、テスト、運用まで多岐にわたる工程があります。技術の進化により、以前は高額な専用機器が必要だったARも、今ではスマートフォン一つで手軽に体験できるようになり、ビジネスでの活用機会も急速に拡大しています。企業のプロモーションや教育、エンターテイメントなど、様々な分野でAR技術の可能性が広がっています。
ARの活用シーン
AR(拡張現実)は、スマートフォンやARグラスを通じて現実空間にデジタル情報を重ねる技術です。近年では様々な業界で活用が広がっており、特に以下のようなシーンで効果を発揮しています。
プロモーション・販促施策
ARを活用した商品紹介やキャンペーン体験により、ユーザーの印象に残るプロモーションが可能になります。商品パッケージにスマートフォンをかざすと、キャラクターが飛び出してくる演出や、自宅にいながら家具や家電の設置イメージを確認できるARカタログなどが代表例です。
また、化粧品や眼鏡、アパレル製品などのバーチャル試着も人気の活用法です。実際に店舗に足を運ばなくても、自分に合うかどうかを視覚的に確認できるため、購買意欲の向上につながります。このように、ARは従来の広告手法と比べて、ユーザーの能動的な参加を促し、より深い製品理解と記憶に残る体験を提供できるのです。
展示会・イベント演出
リアルイベントでのAR演出や、会場案内、ARスタンプラリーなどにより、参加者の満足度を高め、SNSでの拡散にもつながります。展示会ブースにARマーカーを設置して、来場者が自分のスマートフォンで商品の詳細情報や3Dモデルを確認できるようにすれば、限られたスペースでも多くの情報を伝えることが可能です。
また、イベント会場内でのARスタンプラリーは、来場者の回遊性を高め、より多くのブースやコンテンツに触れてもらう効果があります。特に若年層を対象としたイベントでは、撮影した映像をSNSで共有してもらうことで、イベントの認知拡大にもつながります。参加者にとって新鮮で楽しい体験を提供しながら、主催者側のマーケティング目標も達成できる一石二鳥の施策といえるでしょう。
教育・研修コンテンツ
製品の使い方、設備の操作方法、災害時対応など、複雑な工程を視覚的に伝えるためにARを活用。言語や世代を超えた理解促進に貢献します。例えば、医学教育では人体の構造をAR表示することで、従来の教科書や模型では伝わりにくかった立体的な理解が可能になります。
また、製造業では機械の操作手順や保守点検のガイドをARで表示することで、作業効率の向上とヒューマンエラーの削減が期待できます。特に多言語対応が必要な現場では、言語の壁を超えて視覚的に作業手順を伝えられるというメリットがあります。
教育現場では教科書の内容をAR化することで、子どもたちの興味関心を引き出し、学習意欲の向上につなげる取り組みも増えています。抽象的な概念も視覚化することで、理解度と記憶の定着率を高められるのがAR教育コンテンツの強みです。
不動産・建築業界での空間提案
住宅やオフィスの完成予想をARで表示し、図面では伝わらない「実感」を提供できます。家具配置や内装の確認にも活用されています。従来のパース画像や模型と違い、実際の敷地や空間上に建物を表示できるため、完成後のイメージがより具体的に伝わります。
特に注文住宅では、顧客が自分の土地に建つ家のイメージを掴みにくいという課題がありましたが、ARを活用することでその場で建物の外観や高さ、周囲の景観との調和を確認できるようになりました。また、室内設計においても、壁紙や床材の変更、家具のレイアウトをリアルタイムで変更しながら確認できるため、顧客の意思決定をサポートし、満足度の高い空間づくりに貢献しています。
不動産販売においても、物件の内見前にARで間取りや内装を確認できれば、顧客の検討プロセスが効率化され、成約率の向上にもつながるでしょう。
エンタメ・アパレル・Vtuberとの連携
ARを通じたVtuberのライブ演出や、アパレル業界での試着体験など、感情を動かす体験としてのAR導入が進んでいます。エンターテイメント業界では、コンサートやイベントでARを活用したライブ演出が人気を集め、通常では表現できない視覚効果を実現しています。
アパレル業界では、スマートフォン上で衣服のバーチャル試着ができるARアプリが普及し始めており、実店舗に足を運ばなくても自分に似合う服装を確認できるようになりました。コロナ禍以降、非接触での買い物体験のニーズが高まる中、こうしたAR技術の活用はさらに加速しています。
また、バーチャルYouTuberとファンをつなぐ新しいコミュニケーション手段としても、ARは注目されています。ファンが自分の部屋に推しのVtuberを登場させて一緒に写真を撮ったり、特別なメッセージを受け取ったりする体験は、従来のエンタメコンテンツにはない親近感と没入感を生み出しています。
AR制作会社の選び方
AR制作を依頼する際には、自社のニーズに合った最適なパートナーを選ぶことが重要です。以下のポイントを参考に、AR制作会社を選ぶ際の判断基準としてください。
対応できるARの種類を確認する
マーカー型AR、空間認識型AR、WebAR、アプリ型など、会社によって得意なARのタイプが異なります。自社の施策に最適な方式に対応しているかを確認しましょう。例えば、気軽に多くのユーザーに体験してもらいたい場合は、アプリのインストールが不要なWebARに対応している会社がおすすめです。
一方、高度な空間認識や没入感の高い体験を提供したい場合は、アプリ型ARに強みを持つ会社が適しているでしょう。また、最新のARKitやARCoreといったプラットフォーム対応状況も確認すると良いでしょう。自社のターゲットユーザーがどのようなデバイスを使っているかを考慮し、そのプラットフォームに対応しているARを制作できる会社を選ぶことが大切です。
実績・ポートフォリオの豊富さ
これまでにどのような業界・用途でARを制作しているかを確認することで、制作会社のレベルや対応力が分かります。特に自社と同じような目的・業界の実績があれば安心です。制作会社のウェブサイトやSNSで過去の実績を確認するだけでなく、可能であれば実際に制作したARコンテンツを体験してみることをおすすめします。
クオリティはもちろん、UIの使いやすさや読み込み速度なども体験することで、ユーザー目線での品質を確認できます。また、大手企業との取引実績があるかどうかも一つの判断材料になります。複数の企業から継続的に依頼を受けている会社は、技術力だけでなく、クライアント対応や進行管理においても信頼できる可能性が高いでしょう。
企画~運用まで一貫対応しているか
AR制作は、企画・設計・デザイン・開発・運用・検証とフェーズが多岐に渡ります。すべてを一括して任せられる会社なら、管理工数が削減され、スムーズにプロジェクトが進行します。特に、AR施策が初めての場合は、企画段階からアドバイスをもらえる制作会社を選ぶと安心です。
運用面でも、リリース後のバグ対応や、OSアップデート時の動作検証、アクセス解析など、継続的なサポートが必要になります。こうした運用フェーズまで対応可能かどうかも、事前に確認しておくべきポイントです。プロジェクトの途中で別の会社に依頼し直すことになると、余計なコストや時間がかかってしまうため、長期的な視点でパートナーを選ぶことが重要です。
CG・3D制作スキルの有無
ARでは3Dモデルやアニメーションが重要な要素です。自社で高品質な3DCGを制作できる会社か、または信頼できる外部パートナーと提携しているかもチェックしましょう。3Dモデルの品質はARコンテンツの見栄えを大きく左右するため、この点は特に重視すべきです。
制作実績の中で、3Dモデルの精度や表現力、動きの自然さなどを確認してみましょう。また、3Dモデルの軽量化技術も重要です。いくら見栄えの良いモデルでも、読み込みに時間がかかったり、動作が重くなったりすると、ユーザー体験が低下してしまいます。モバイル環境でも快適に動作する最適化技術を持っているかどうかも確認するとよいでしょう。
見積もりの明瞭さと柔軟な提案力
目的に応じた柔軟な提案をしてくれるか、そして見積もりが明瞭であるかは重要です。安さだけで選ぶと、完成品質やサポート面で後悔するケースもあるため、コストと価値のバランスを見極めましょう。見積もりの内訳が詳細に記載されているか、追加費用が発生する条件が明確か、といった点をチェックすることで、後々のトラブルを防げます。
また、予算に応じた複数の提案ができる会社は、クライアントの状況を理解し柔軟に対応してくれる可能性が高いです。初期段階で「これしかできない」と限定的な提案しかできない会社よりも、複数の選択肢を示しながら最適な解決策を一緒に考えてくれる会社を選ぶことで、より効果的なAR施策を実現できるでしょう。
おすすめのAR制作会社
AR制作を検討する際に参考になる、実績豊富なおすすめ会社を6社ご紹介します。それぞれ特徴や強みが異なるため、自社のニーズに合った会社を選びましょう。
株式会社エム・ソフト

株式会社エム・ソフトは、長年のソフトウェア開発実績と豊富な知見を活かし、AR(拡張現実)制作サービスを提供しています。独自の画像処理技術をはじめ、組込みソフトウェアやモバイルアプリ、クラウド・Webシステムまで幅広く対応し、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進をサポートします。産学連携による先進技術も活用し、企業の新しい価値創造を実現しています。
参考:エム・ソフト
vartique
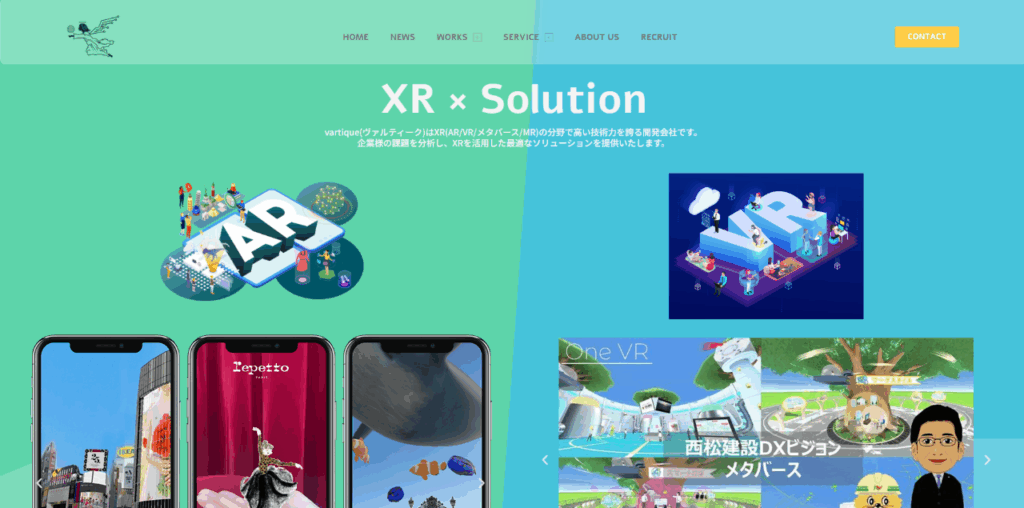
株式会社vartiqueは、XR(AR/VR/メタバース/MR)分野において高い技術力を持つ開発会社です。AR制作サービスでは、SNS向けARフィルターやWebブラウザで体験できるwebARコンテンツなど、専用デバイス不要でスマートフォンから利用できる多彩なコンテンツを提供しています。企業のマーケティングやイベント、教育・研修など幅広い用途に最適なARソリューションを提案し、課題解決をサポートしています。
参考:vartique
ジグノシステムジャパン

ジグノシステムジャパン株式会社は、AR制作サービスとして「ARフォトフレーム」などのARコンテンツ制作を提供しています。エフエム東京グループの強みと、Webサイトやアプリ開発、3D制作で培った高い技術力を活かし、企業やイベント向けにオリジナルのAR体験を企画・制作。最新の導入事例には「TOKYO FM 開局55周年記念ARフォトフレーム」や「コエ×コエ フェスティバル 2024」などがあり、プロモーションやキャンペーンの認知度向上に貢献しています。
参考:ジグノシステムジャパン
REACTOR

株式会社リアクターは、北海道札幌市を拠点に、映像制作の枠を超えた多彩なコンテンツ開発を手がけています。AR(拡張現実)制作では、WebやVRと組み合わせた新しい表現を実現し、企業や自治体のプロモーション、観光アプリなど幅広い分野で活用されています。企画から撮影、CG制作までワンストップで対応し、ユーザー体験を高めるARコンテンツを提供しています。
株式会社プラージュ
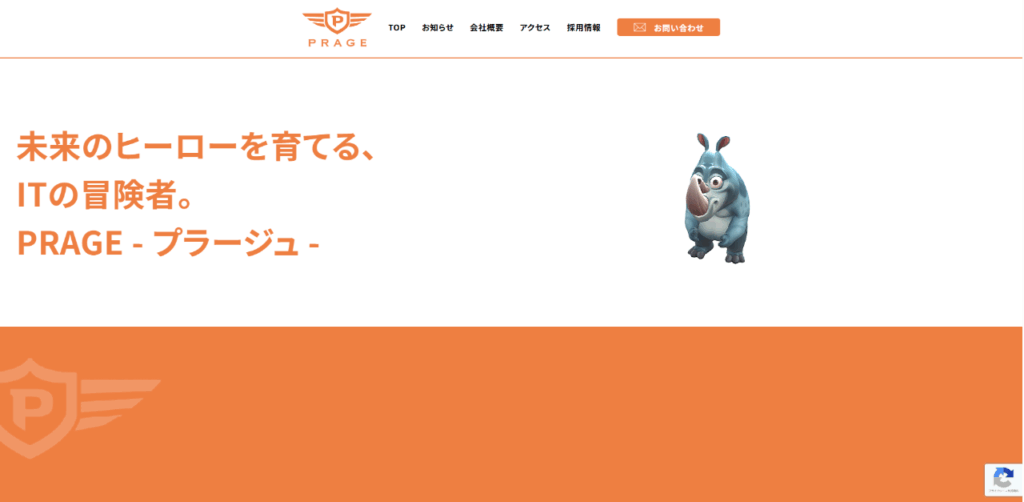
株式会社プラージュは、AR(拡張現実)技術を活用したサービスを提供し、DX推進や教育、マーケティング、商品プロモーション分野で新しい体験を創出しています。独自開発の「ARcube」は、スマートフォンやタブレットで画像認識し、デジタルコンテンツをリアルタイム表示できる革新的なツールです。企業や学校の教育、販促活動に活用でき、競争力強化に貢献するARソリューションを提案しています。
参考:株式会社プラージュ
ビーアンドピー

株式会社ビーアンドピーは、インクジェットプリント事業で培ったノウハウを活かし、販促広告物と連動したワンストップのAR(拡張現実)サービスを提供しています。広告物に印刷した二次元コードを読み込むだけで、アプリ不要で手軽にAR体験が可能です。プリントとARを一体化した統一感あるプロモーションを実現し、短期間イベントにも最適なサービスです。
参考:ビーアンドピー
AR制作会社に関するよくある質問(FAQ)
AR制作会社に関するよくある質問をまとめました。
Q1. AR制作にはどれくらいの費用がかかりますか?
A. 制作内容やARの種類によって異なりますが、簡易なWebARであれば数十万円から、本格的な3DCGやアプリ開発を伴う場合は数百万円になることもあります。見積もりの明瞭な会社に相談しましょう。
Q2. WebARとアプリ型ARの違いは何ですか?
A. WebARはアプリのインストール不要でブラウザから体験できるARです。アプリ型ARはダウンロードが必要ですが、表現力や機能性に優れています。目的に応じて選びましょう。
Q3. どんな業種でARは活用できますか?
A. 販促・イベント・教育・不動産・アパレル・エンタメなど、業界を問わず活用されています。具体的には、商品プロモーション、展示会演出、研修コンテンツ、住宅の完成予想などがあります。
Q4. 初めてでもAR制作を依頼できますか?
A. はい。企画から運用まで一貫してサポートしてくれる制作会社も多く、初めての方でも安心して依頼できます。まずは相談から始めるのがおすすめです。
Q5. 自社に合ったAR制作会社はどう選べばいい?
A. 「対応できるARの種類」「実績」「一貫対応体制」「CG制作スキル」「柔軟な提案力」などを基準に選ぶと、自社の目的に合った最適なパートナーが見つかりやすくなります。
まとめ:AR制作で魅力的な体験を実現しよう
AR技術は、プロモーションや教育、空間提案など多様なシーンで活用され、ユーザーに新しい体験価値を提供できる手段として注目されています。本記事で紹介した制作会社は、それぞれ異なる強みを持っており、目的や予算に応じて最適なパートナーを選ぶことが大切です。
AR制作を検討する際は、まず自社の課題や目標を明確にし、どのようなAR体験を提供したいのかをイメージすることから始めましょう。続いて、対応ARの種類、実績の豊富さ、一貫対応力、CG制作スキル、提案力といった観点から、複数の制作会社を比較検討することをおすすめします。
ARは単なる技術的な目新しさだけでなく、ユーザーの行動変容やブランド体験の向上につなげてこそ価値があります。制作会社との綿密なコミュニケーションを通じて、目的に合ったAR体験をデザインし、効果測定までを視野に入れた施策を実施しましょう。適切なパートナー選びが、AR活用の成功への第一歩となります。