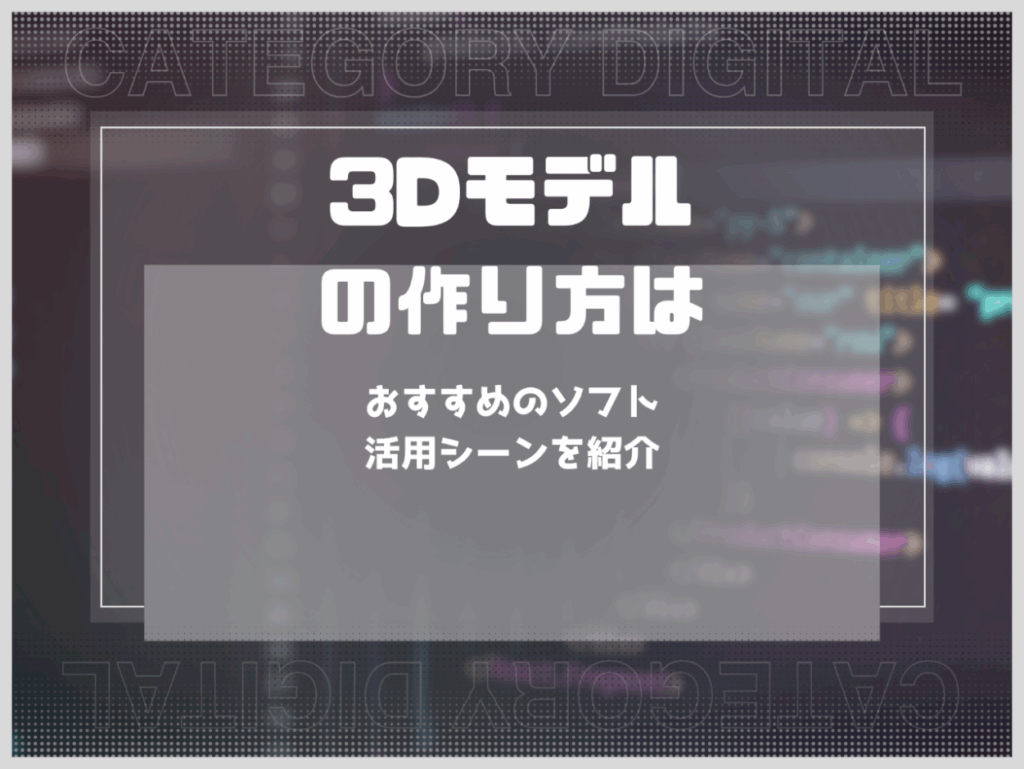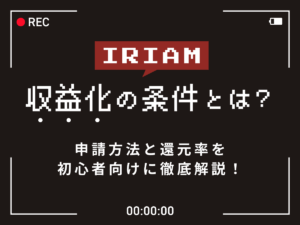近年、VTuber配信やゲーム制作、プロダクトデザインなど、3Dモデルを使う場面がどんどん増えています。「自分でも作れるの?」「どんなソフトを使えばいい?」と気になる方も多いのではないでしょうか。
3Dモデル制作は専門的な知識が必要に見えますが、今は無料ツールやインターネット上の解説も充実しており、初心者でも気軽に挑戦できるクリエイティブな活動です。
この記事では、3Dモデルの基礎知識や作り方の流れ、主な活用シーン、費用の目安、おすすめソフトまで、幅広く解説します。自分で作りたい方にはおすすめのソフトも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
この記事でわかること
- 3Dモデルとは?どこで活用されているか
- 3Dモデル制作の基本的な手順と流れ
- 制作を依頼した場合のおおまかな費用感
- 外注先を選ぶ際に注意したいポイント
- 初心者向け・プロ向けのおすすめ3Dモデリングソフト
おすすめ記事
目次
3Dモデルとは
3Dモデルとは、コンピューター上で作られた立体的な物体やキャラクターのデジタルデータのことです。平面的な2Dイラストとは異なり、X軸(横)、Y軸(縦)、Z軸(奥行き)という3つの軸で構成されるため、360度全方位から確認や操作ができます。
3Dモデルは、ただの見た目だけでなく、動きや重さ、質感なども再現できるのが特徴です。そのため、ゲームやアニメ、VR(バーチャルリアリティ)、AR(拡張現実)、製品デザインなど、さまざまな分野で活用されています。さらに3Dモデルは現実のモノをリアルに再現したり、想像の世界をデジタル空間で作り出すこともできます。
3Dモデルの活用シーン
3Dモデルは、私たちの身の回りのさまざまな場所で活用されています。ここでは、主な活用シーンを具体的に見ていきましょう。
配信用アバター・Vtuberのモデル制作
VTuberやライブ配信では、3Dモデルが自分の分身となるアバターとして使われています。特にVTuber文化の広がりとともに、リアルな動きや個性豊かなデザインのキャラクターモデルの需要が高まっています。
配信用3Dモデルは、表情やモーションのスムーズさが非常に重要。顔の喜怒哀楽の変化や、髪の毛、衣装の細かな揺れなど、細部の作り込みが人気のポイントとなります。
一般的にVRMやLive2Dといった特定のファイル形式で制作され、配信用ソフトウェアと連動してリアルタイムに動かすことが可能です。より高品質なVTuberアバターは、視聴者とのコミュニケーションを深め、配信の質を格段に向上させるでしょう。
アニメーション作品・映像制作での利用
映画やテレビアニメ、CMなどの映像制作においても、3Dモデルはもはや欠かせない存在です。ピクサーやディズニーに代表されるフルCGアニメーションはもちろんのこと、実写映画でも、爆発や炎といった特殊効果、壮大な架空の背景、現実には存在しないクリーチャーなど、数多くの要素が3Dモデルで表現されています。
高品質な3Dアニメーションを実現するには、緻密なモデリングに加え、キャラクターの骨組み(リグ)の設定、滑らかな動きを生み出すアニメーション、膨大な計算を伴うレンダリング処理が欠かせません。
近年では、セルルック(2Dアニメ風)の表現を3Dで実現する技術も進化し、日本のアニメ業界でも積極的に活用されています。
VR・ARコンテンツへの3Dモデル活用
バーチャルリアリティ(VR)や拡張現実(AR)の世界では、3Dモデルが仮想空間や現実世界に重ね合わされる情報の基本要素となります。ユーザーがまるでその場にいるかのように体験できる没入感の高い環境を作り出すために、3Dモデルは必要不可欠です。
VR・AR向けのモデルは、360度どの角度から見ても自然で破綻がないように設計されます。また、スマートフォンやVRヘッドセットといった限られたデバイスの処理能力でもスムーズに動作するよう、軽量化されたモデル設計が求められるのが特徴です。仮想空間での会議、ARを活用した家具の配置シミュレーションなど、その用途は広がり続けています。
ゲーム・アプリ内キャラクター・アイテムとして利用
ゲーム業界では、キャラクター、敵、アイテム、背景など、ほぼすべての要素が3Dモデルで構成されています。特に広大な世界を自由に探索できるオープンワールドゲームでは、膨大な量の3Dモデルが使用され、プレイヤーを魅了する世界観を作り上げています。
ゲーム用3Dモデルは、見た目の美しさだけでなく、リアルタイムでの動作負荷とのバランスが非常に重要です。モデルの複雑さを示すポリゴン数を適切に調整し、カクつきなくスムーズに動く軽量なモデル設計が求められます。また、物理演算や衝突判定が正しく機能するように、モデルの構造にも配慮が必要です。
工業製品・機械の可視化と説明資料
製造業や建築業では、実際に製品を製造したり建物を建設したりする前に、3Dモデルで設計・確認することが一般的になっています。これにより、製品の見た目や使い勝手だけでなく、機能性や組み立て方法の検証、部品の干渉チェックなどもできるため、開発プロセスにおいて重要な役割を果たします。
CADソフトを使用して精密な3Dモデルを作成し、製品企画、設計検証、マーケティング資料、取扱説明書、工場でのラインシミュレーションなど、多様な用途に活用されます。実物を作る前に潜在的な問題点を発見できるため、大幅な開発コスト削減や品質向上に貢献しています。
ライブ演出・イベント空間での3D演出
コンサートや演劇、大規模なイベントでは、プロジェクションマッピングや大型LEDスクリーンを活用した3D演出が人気を集めています。実際の空間と融合した立体的な映像体験は、観客に強いインパクトと没入感を提供します。
この種の演出では、会場の形状や構造に合わせた精密な3Dモデルが作成され、音楽やパフォーマーの動きと完全に同期した映像が投影されます。時には、空間自体が変形しているかのような錯覚を起こさせる演出も可能。3Dモデルと最新の映像技術が融合することで、観客を魅了する忘れられない体験が生み出されています。
3Dモデルの手法
3Dモデルを作成する手法は、その表現方法によって大きく以下の3種類に分けられます。
- ワイヤーフレームモデル
- サーフェスモデル
- ソリッドモデル
それぞれの特徴と主な用途を見ていきましょう。
ワイヤーフレームモデル
ワイヤーフレームモデルは、3Dモデルの最も基本的な表現方法です。物体を構成する点(頂点)と、それらをつなぐ線(エッジ)だけで、その輪郭や構造を表現します。面や色はなく、針金細工の骨組みだけの状態です。
このモデルは、主に設計の初期段階や、モデル全体の形状やプロポーションを素早く確認したい場合に使用されます。データ容量が非常に小さく、処理が軽いため、複雑なモデルの基礎として最初に作成されることが多いです。建築設計の構想段階や、機械部品の構造確認などでよく使われる手法です。
サーフェスモデル
サーフェスモデルは、ワイヤーフレームモデルに面を張り付けた状態を指します。物体の表面(サーフェス)を表現し、内部は空洞で、風船の皮のような状態です。
曲面を非常に精密に表現できるため、自動車のボディ、航空機の外装、流線型の家電製品など、見た目の美しさや空気抵抗といった形状が重要な製品の設計によく使用されます。キャラクターのモデリングにおいても、滑らかな肌や複雑な衣装の表現に広く活用されています。
ソリッドモデル
ソリッドモデルは、物体を中身の詰まった固体として表現するモデルです。単なる表面だけでなく、内部構造や体積・質量・重心など物理的なデータも含めて設計されます。
このモデルは、工業製品の設計、機械部品の製造、建築構造物の設計など、物理的な性質や強度計算が必要な場合に最も適しています。また、3Dプリンターでの出力や、CAEシステムでの応力解析や熱解析などにも使用されます。
一方で、データ量が大きく、複雑な曲面の表現はやや苦手です。ゲームや映像分野ではあまり使われません。実際の製品開発や製造工程において、設計ミスを防ぎ、品質を向上させるために不可欠なモデル形式と言えます。
3Dモデルの作り方
3Dモデルの制作過程は、一般的に以下の5つのステップで進められます。
- 三面図を作る
- モデリングを行う
- テクスチャー・マテリアル設計を行う
- リギングを行う
- レンダリングを行う
これらの工程を順に踏むことで、ゼロから立体的なモデルを作り上げることができます。
三面図を作る
3Dモデル制作の最初のステップは、正面・側面・上面の三面図を作成することです。三面図は、対象物を正面、側面、上面から見た図面で、いわば「設計図」の役割を果たします。
キャラクターモデルの場合、イラストレーターに依頼したり、自分でイメージを具体化したデザイン画を描いたりします。製品モデルであれば、実際の設計図や既存の製品写真、スケッチから三面図を起こします。
この段階で、モデルのプロポーション(比率)や全体のデザイン、細部の整合性を十分に確認しておくことで、後のモデリング工程がスムーズに進みます。計画が曖昧だと、途中で手戻りが発生し、時間とコストが無駄になる可能性があるため、丁寧な準備を心がけましょう。
モデリングを行う
次に、モデリングを行います。モデリングは、三面図やデザイン画をガイドラインとして、実際に3D空間上でモデルの形状を作り上げていく工程です。専用のソフトウェアを使い、点(頂点)や線(エッジ)、面(ポリゴン)を操作しながら、立体的な形状を構築していきます。
モデリングの手法には主に以下の3種類があります。
- ポリゴンモデリング: 最も一般的な手法で、多角形(ポリゴン)を組み合わせて形状を構築します。ゲームやアニメーションで広く使われます。
- スカルプトモデリング: 粘土をこねるように、ブラシツールを使って直感的に形を削ったり盛り上げたりする手法です。有機的なキャラクターや生物のモデリングに適しています。
- スプラインモデリング: 数学的な曲線(スプライン)を使って形状を定義します。滑らかな曲面や工業製品の精密なデザインによく用いられます。
モデリングは、形状のバランスやディテールを意識しながら進めることが重要です。表現したいものや最終的な用途に合わせて最適な手法を選択し、モデルの形状を細部まで作り込んでいきましょう。
テクスチャー・マテリアル設定を行う
モデルの形状が完成したら、次にその表面の質感や色、模様を設定します。この工程によって、モデルに、金属の光沢、布のしわ、肌の質感など、リアルなマテリアル表現が可能になります。
テクスチャー: モデルの表面に画像を貼り付けることで、模様、柄、傷、汚れ、肌の細かな質感などを表現します。画像編集ソフトで作成したテクスチャマップ(色、凹凸、光沢などを情報として持つ画像)をモデルに適用します。
マテリアル: 物体の光の反射特性、透明度、表面の粗さ、色などの物理的な性質を設定します。金属、プラスチック、木材、ガラスといった異なる素材の質感を再現するために、各マテリアルパラメーターを調整します。
テクスチャとマテリアルを組み合わせることで、モデルはよりリアルで説得力のある見た目になります。
リギングを行う
次にキャラクターに骨組みを設定するリギングを行います。キャラクターなど、動かす必要のある3Dモデルの場合、リギングの工程が不可欠です。リギングとは、モデルの内部に骨組み(ボーンまたはリグ)を設定し、それによってモデルに動きを与えるための準備をすることです。
リギングでは、人間の骨格や関節の動きを模倣するようにボーンを配置し、各ボーンがモデルのどの部分に影響を与えるかを設定します。指の動きや顔の表情、髪の揺れなど、細かな動きが必要な部分は、より複雑なリグ設定が必要になります。
適切なリギングを行うことで、後工程のアニメーション作成で自然で滑らかな動きを実現できるようになります。VTuberのようにリアルタイムで表情や動きを反映させる場合も、このリギングが重要です。
レンダリングを行う
最終工程として、作成した3Dモデルを2Dの画像や動画として出力する作業であるレンダリングを行います。この工程で、光源(ライト)、カメラの視点、影の落ち方、環境光などを設定し、モデルの最終的な見た目を決定します。
レンダリングでは、光の反射、屈折、影、拡散などの物理的な計算を行い、リアルな光の振る舞いを表現します。用途に応じて、写真のようなフォトリアルな表現や、アニメのようなトゥーンレンダリングなど、さまざまなスタイルを選択できます。
高品質なレンダリングはコンピューターに高い負荷をかけ、時間がかかることが多いため、用途や予算に応じた適切な設定が重要になります。
3Dモデル制作の費用相場
3Dモデル制作の費用は、目的・モデルの複雑さ・納品形式によって大きく異なります。以下はジャンル別の目安です(当社事例・市場相場をもとにした参考価格です)。
キャラクターモデル(配信・VTuber向け)
目安:10万円〜50万円程度
VTuberやゲームキャラクター、SNSアイコンなどのキャラクターモデルの費用です。顔の表情制御(喜怒哀楽、口の動き、リップシンクなど)、衣装の作り込み、髪の毛やアクセサリーの揺れもの、VRChatやClusterなど特定のプラットフォームへの対応、VRM形式での納品、Live2D連携などで価格が変動します。
特に、プロのVTuberや企業案件で求められるような、非常に高品質で表現豊かなモデル、リアルタイムでの動きや感情表現を追求したモデルの場合、100万円を超えることも珍しくありません。これは、緻密なモデリングに加え、高度なリギング、複雑なシェーダー設定、さらにはAIによる表情生成技術との連携を見越した設計などが含まれるためです。
初心者向けの比較的シンプルなモデルであれば、10万円前後から制作可能です。モーションキャプチャに対応させるためのボーン設計や、専用のリグ設定も費用に影響します。
プロダクトモデル(工業製品・機械・家具など)
目安:5万円〜30万円程度
製造業の製品、機械部品、家具、家電など、実用的な物品の3Dモデル制作費用です。既存の設計図やCADデータ、詳細な写真などがある場合は、作業効率が良いためコストを抑えやすい傾向にあります。
製品カタログやECサイト、プレゼンテーション資料、オンラインショールーム用の3Dモデルは、精度と見栄えのバランスが重要です。単純な形状であれば5万円程度から作成可能ですが、内部構造が複雑な機械、精密機器、あるいは分解シミュレーションやインタラクティブな表現、ARでの表示最適化などが必要な場合は、30万円以上かかることもあります。
高精細なレンダリングや、製品の材質感を忠実に再現するための高度なマテリアル設定が必要な場合も追加費用が発生します。
背景・空間モデル(イベント空間・ゲーム背景など)
目安:10万円〜100万円程度(サイズ・作り込み次第)
イベント会場、建築物の内装・外装、ゲームのステージ背景、VR空間、メタバースプラットフォーム向けワールドなど、広範囲な空間や環境の3Dモデル制作費用です。その規模や作り込みの密度、必要な最適化のレベルによって費用が大きく変動します。
シンプルな一室の内装であれば10万円程度から、大規模なオープンワールドのゲーム背景や、複雑な構造を持つイベント会場、または大人数が同時にアクセスするメタバース空間全体のモデリングでは50万円〜100万円以上になることも珍しくありません。
これは、膨大な量のアセット(建物、樹木、小物など)の制作、リアルタイムレンダリングに最適化された軽量設計、インタラクション(操作性)の有無、そしてUnityやUnreal Engineといったゲームエンジン、あるいはVRChatなどのプラットフォーム向けへの専門的な最適化作業が含まれるためです。
3Dモデル制作の外注先の選び方
自社での制作が難しい場合や、クオリティ・スピードを重視したい場合は、3Dモデルを外注するのもおすすめです。ここでは、失敗しない外注先の選び方で確認すべき重要なポイントを解説します。
制作実績・ポートフォリオの有無
まずは、その会社やクリエイターがどんな3Dモデルを作ったことがあるか(制作実績)を確認しましょう。
- 希望するジャンル(キャラクター・背景・製品など)に強いか
- サンプル(ポートフォリオ)に一貫性や高いクオリティがあるか
制作会社やフリーランスのWebサイト、SNS、アート系プラットフォーム(ArtStationなど)などで、実績作品の量と質を確認します。
特に、希望する「VTuber向けアバター」「ゲームキャラクター」「製品のリアルな可視化」など、用途や表現スタイルに近い作品があるかどうかを見極めるのがポイントです。たとえ実績が少ない場合でも、過去作品のクオリティが非常に高ければ、希望どおりの3Dモデルが作成できることもあります。
モデルの用途への対応力
依頼したモデルをどこでどう使うかによって、必要な納品形式や仕様が変わります。
- VTuber配信用(VRM形式など)
- ゲームエンジン用(FBXやUnity形式など)
- Webサイト表示用(GLTF形式など)
使いたい場面やソフトに合わせて対応してもらえるかを確認しましょう。また、商用利用や二次利用の可否も事前にチェックが必要です。
例えば、ゲーム用のモデルを依頼する場合は、適切なポリゴン数の最適化や、ゲームエンジンでの動作検証まで対応できる制作者がベスト。将来の拡張や他のプラットフォーム対応も考えて相談できると安心です。
モーションやアニメーション対応の有無
キャラクターや動きのあるモデルを作りたい場合は、モーション(動き)やアニメーションも制作可能かをチェックしましょう。
- 骨組み(リグ)やアニメーション、モーションキャプチャ対応か
- 歩く、走る、表情を変えるなど、複雑な動きも作れるか
静止モデルだけでなく、動きをつけたい場合は「どんな動きに対応できるか」「アニメーション制作の実績はあるか」も確認しておくと、後の作業がスムーズになります。
単に静止した3Dモデルだけでなく、動きのある表現を求める場合は、アニメーション制作の実績が重要です。キャラクターであれば歩行や走行などの基本モーションから、表情変化や特殊なアクションまで、必要な動きに対応できるかを確認しましょう。
他にも、予算と納期のバランス、追加料金の有無、修正対応の範囲も事前に確認しておくと安心です。
3Dモデル作成におすすめのソフト
自分で3Dモデルを作ってみたい方のために、代表的な3つの3Dモデリングソフトを紹介します。目的やレベルに合わせて選びましょう。
Blender
【特徴】
- 完全無料で高機能
- 商用利用ができる
- 豊富なチュートリアルとコミュニティ
| 期間 | 費用(税込) |
|---|---|
| 無料 |
Blenderは完全無料で使えるにも関わらず、プロレベルの機能を備えた高機能な3Dモデリングソフトウェアです。オープンソースとして開発されており、世界中のアーティストや開発者によって常に進化し続けています。
モデリング、テクスチャリング、リギング、アニメーション、シミュレーション(物理演算)、レンダリング、ビデオ編集、モーショントラッキングなど、3D制作に必要なほとんどの機能がBlender一つで完結します。
無料でありながら、制作した作品は商用利用も可能。近年では、インディーズゲーム開発だけでなく、一部の映画制作や大規模プロジェクトでも採用される例が増えています。
世界中にユーザーが多いため、公式チュートリアルだけでなく、YouTubeやブログで無料チュートリアルが公開されています。また、活発なオンラインコミュニティがあり、初心者でも学びやすい環境が整っています。
「とりあえず3Dモデル制作を始めてみたい」「コストをかけずに本格的なツールを使ってみたい」という初心者の方に、まずおすすめしたいソフトです。
Maya
【特徴】
- アニメーションに特化
- 業界標準のプロ仕様
- 映像表現の自由度が高い
- サブスク形式で初期費用を抑えられる
| 期間 | 費用(税込) |
|---|---|
| 月間プラン | 39,600円 |
| 年間プラン | 312,400円 |
Mayaは、映画、アニメーション、ゲーム制作の現場で業界標準として広く使われているプロフェッショナル向けの3DCGソフトウェアです。特に高度なモデリング機能と、キャラクターアニメーションの分野で高い評価を得ています。
キャラクターのアニメーション制作に強みがあり、複雑なリギングツールや、フェイシャルアニメーション(顔の表情)の制御機能が充実。高度なパーティクルシステムや、ダイナミクスシミュレーション機能により、リアルで複雑な物理現象を再現できます。
大規模な制作スタジオでの共同作業を想定した機能や、他のDCCツールとの連携もスムーズです。
サブスクリプション形式での提供となるため、継続的なコストはかかりますが、「プロの現場で通用するスキルを身につけたい」「最高峰のツールでハイクオリティな作品を制作したい」「業界標準のワークフローを学びたい」という方におすすめです。
3ds Max
【特徴】
- 建築・工業デザインに強み
- 豊富な編集機能
- プラグインの豊富さ
| 期間 | 費用(税込) |
|---|---|
| 月間プラン | 39,600円 |
| 年間プラン | 312,400円 |
3ds Maxは、Mayaと同じくAutodesk社が開発するプロフェッショナル向け3DCGソフトウェアです。建築ビジュアライゼーション、製品デザイン、ゲーム開発など、特に建築や工業デザイン分野での利用が多いのが特徴です。
精密な寸法指定が可能なパラメトリックモデリングや、BIMデータとの連携など、建築や製造業のワークフローに特化した機能が充実しています。
モデリングを非破壊的に編集できる編集機能が豊富で、効率的な形状作成が可能です。また、サードパーティ製のプラグインが豊富で、特定の専門分野に合わせた環境を構築しやすい拡張性があります。
Windows専用ソフトですが、その安定性と機能の豊富さから、多くのプロフェッショナルに支持されています。「リアルな建築パースを作りたい」「精密なプロダクトの3Dモデルを設計したい」といった方に特におすすめです。
3Dモデルの作り方に関するよくある質問
最後に3Dモデルの作り方に関するよくある質問をまとめます。
Q1. 3Dモデル制作にはどのくらいの期間がかかりますか?
A. 制作内容やクオリティ、修正回数にもよりますが、キャラクター1体の標準的な制作で2〜4週間程度が一般的です。大規模な背景モデルやプロダクトモデリングの場合は、1〜2ヶ月かかるケースもあります。
Q2. 自分で3Dモデルを作るのは難しいですか?
A. 最近はBlenderのような無料で高機能なソフトやチュートリアルが豊富にあるため、初心者でも挑戦しやすくなっています。ただし、精密なリギングやアニメーションなどは経験と学習が必要です。
Q3. キャラクターに動きをつけることはできますか?
A. はい、可能です。リギングやモーションアニメーションの対応ができる制作者に依頼すれば、表情やポーズ、歩行・ダンスといった動きも再現できます。モーションキャプチャデータとの連携も可能です。
Q4. 制作費用はどのくらいかかりますか?
A. シンプルなキャラモデルなら10万円前後から、複雑な表現や配信向けモデルで30〜50万円、工業製品や背景などの高精度モデルは30万円〜100万円以上かかることもあります。詳しくは見積もりをご依頼ください。
Q5. 外注と自作、どちらがいいのでしょうか?
A. 目的や予算によります。クオリティを重視する場合や短期間で成果が必要な場合は外注がおすすめです。コストを抑えて試したい場合は、Blenderなどでの自作から始めるのもよいでしょう。
まとめ:3Dモデルの制作はデジタルギアに
3Dモデルは、VTuberやゲーム、映像、製品デザインなど、さまざまなシーンで活用できるデジタル技術です。今は無料ソフトも充実しており、初心者でも気軽にチャレンジできます。
この記事で紹介した基礎知識や具体的な制作方法、おすすめのソフトを参考に、ぜひ3Dモデル制作に挑戦してみてください。
自分で制作するにしても、プロに外注するにしても、最も大切なのは「何のために3Dモデルを作るのか」という目的や用途を明確にすることです。
VTuber配信、ゲーム開発、製品デザインなど、活用シーンによって求められるモデルの仕様や品質は大きく異なります。予算や納期も考慮し、あなたにとって最適な制作方法を選びましょう。
「ハイクオリティなVTuberアバターで注目を集めたい」「企業としてプロモーションに3Dモデルを活用したいけれど、社内リソースがない」「モーションキャプチャでリアルな動きを表現したい」といったお悩みをお持ちなら、ぜひデジギアにご相談ください。
デジギアは、キャラクターモデルから工業製品のプロダクトモデル、広大なイベント空間デザインまで、幅広いジャンルで豊富な制作実績を持つ、VTuber事業支援の総合サービス会社です。
デジギアでは、具体的な目的に合わせた最適な提案と、高品質な3Dモデル制作を一貫してサポート。企画からモデリング、リギング、モーション収録、配信・運用支援まで、あなたの「なりたい」「実現したい」を形にします。
まずはお気軽にご相談ください。あなたの理想の3Dモデル制作をデジギアが全力でサポートします。