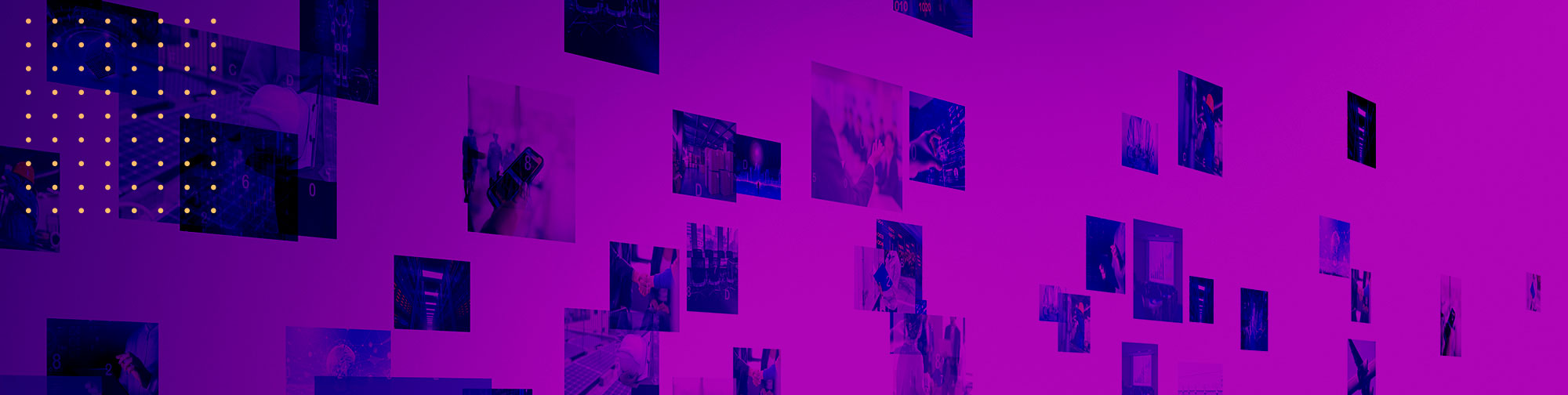記事一覧

3DCGとは?作り方からおすすめソフト・活用事例まで解説
3DCGに興味があるけれど、「3DCGとは具体的に何なのか」「どんな分野で使われているのか」「どのようなソフトで作れるのか」「2DCGとの違いは何か」といった疑問を抱えているのではないでしょうか。3DCGの基本知識や制作方法を理解することで、ゲーム・映画・建築など幅広い分野での活用可能性が見え、新たなクリエイティブなスキルを身につけることができます。
この記事では、3DCGの基本概念から活用事例、制作の流れ、おすすめソフト、学習方法まで初心者向けに詳しく解説していきます。この記事を読んで、3DCGの全体像を把握し、あなたも3DCG制作の第一歩を踏み出してみましょう。
この記事のまとめ
- 3DCGは3次元空間でデジタル画像や映像を制作する技術
- 映画・ゲーム・建築・VTuberなど幅広く活用されている
- 制作工程は設計からレンダリングまで大きく7段階に分けられる
- BlenderやMayaなど用途別にソフトを選択可能
- 制作の依頼費用は数万円から数百万円までと幅広い
おすすめ記事
目次
3DCGとは
3DCGとは「3 Dimensional Computer Graphics」の略称で、コンピューター上で3次元空間を構築してデジタル画像や映像を作成する技術です。
従来の2DCGが縦と横の2方向のみで平面的に表現されるのに対し、3DCGは縦・横・奥行きの3方向を持つ立体的な表現が可能です。3次元空間内に配置されたオブジェクトを様々な角度から見ることができ、まるでそこに実在するかのようなリアルな映像を生み出せます。
現在では映画やゲーム、建築、製品デザインなど幅広い分野で活用されており、現代のデジタルコンテンツ制作には欠かせない技術となっています。
3DCGの主な活用分野
3DCGは現代社会において様々な分野で活用されており、その応用範囲は年々拡大しています。エンターテインメント業界から産業分野まで、3DCG技術は私たちの生活に深く根ざした存在となっています。以下では、3DCGが特に重要な役割を果たしている主要な分野について詳しく見ていきましょう。
映画・映像制作
映画業界では3DCGが革命的な変化をもたらし、従来の実写撮影では不可能だった表現を実現しています。
ハリウッド映画では、SF作品やファンタジー映画において壮大な宇宙空間や幻想的な世界観を3DCGで創造しています。また、実写映像との合成技術も発達し、俳優が演技した映像に3DCGキャラクターを自然に組み込むことが可能になりました。
国内でも映画やドラマ、CM制作において3DCGの活用が進んでおり、従来のミニチュア撮影に代わって効率的で高品質な映像制作が行われています。
3DCGゲーム開発
ゲーム業界において3DCGは最も重要な技術の一つとなっており、現代のゲーム制作には欠かせない存在です。
コンシューマーゲームでは、リアルタイムで動作する高品質な3DCGによって、プレイヤーに没入感のあるゲーム体験を提供しています。キャラクターの表情や動き、背景の細部まで精密に表現され、まるで映画のような映像品質を実現しています。
モバイルゲームでも3DCG技術の普及により、スマートフォンで手軽に楽しめる高品質なゲームが数多く開発されています。
建築・設計
建築業界では3DCGが設計プロセスを大きく変革し、建物の完成イメージを事前に正確に把握できるようになりました。
建築プレゼンテーションでは、設計図だけでは伝わりにくい空間の広がりや光の入り方を3DCGで視覚化し、クライアントとの意思疎通を円滑にしています。また、VR技術と組み合わせることで、実際に建物内を歩き回るような体験も提供できます。
都市計画においても、街全体を3DCGで再現することで、開発計画の影響を事前にシミュレーションし、より良い都市環境の実現に貢献しています。
製品デザイン
製造業では3DCGが製品開発プロセスを効率化し、開発コストの削減と品質向上を実現しています。
自動車業界では、新車のデザイン検討からマーケティング用の映像制作まで、3DCGが幅広く活用されています。実際の試作車を製造する前に、3DCGで外観や内装の詳細な検討が可能になり、開発期間の短縮にも貢献しています。
家電製品や工業製品においても、3DCGによる製品紹介動画やカタログ用の画像制作が一般的となり、消費者により魅力的な製品情報を提供しています。
VR・AR分野
VR(仮想現実)・AR(拡張現実)技術の発展に伴い、3DCGの重要性はさらに高まっています。
VRコンテンツでは、ユーザーが完全に没入できる仮想空間を3DCGで構築し、教育、エンターテインメント、トレーニングなど様々な用途で活用されています。特に医療分野では、手術シミュレーションや解剖学の学習にVR技術が導入されています。
AR技術では、現実空間に3DCGオブジェクトを重ね合わせることで、新しいユーザー体験を創造しており、ショッピングアプリや観光ガイドなど身近なサービスでも利用されています。
VTuber
VTuber(バーチャルYouTuber)は3DCG技術を活用した新しいエンターテインメント分野として急速に成長しています。
3DCGで制作されたキャラクターモデルにモーションキャプチャー技術を組み合わせることで、リアルタイムでキャラクターが動き、配信者の動きや表情を反映できます。この技術により、従来のアニメキャラクターとは異なる、インタラクティブなエンターテインメント体験が実現されています。
企業のマーケティング活動や教育コンテンツにもVTuber技術が応用され、親しみやすいキャラクターを通じた情報発信が行われています。
3DCG作成の基本的な流れ
3DCG制作は複数の工程を経て完成します。企画・設計から最終的な映像出力まで、各段階で専門的な技術と知識が必要になります。以下では、プロの現場でも使われている標準的な3DCG制作の流れを、初心者にも分かりやすく解説していきます。
1. 設計・三面図作成
3DCG制作の最初の工程は、作成するオブジェクトの設計と三面図の作成です。
三面図とは、正面・側面・上面の3方向から見た設計図のことで、3Dモデルの基準となる重要な資料です。キャラクターや建物、製品など、どのようなオブジェクトを作る場合でも、まず平面での設計図を用意することで、立体化する際の形状やプロポーションを正確に再現できます。
この段階では手描きやデジタルイラストソフトを使用し、細部のディテールや寸法も含めて詳細に描き込みます。設計が不十分だと後の工程で大幅な修正が必要になるため、時間をかけて丁寧に行うことが重要です。
2. モデリング
モデリングは三面図を基に、3DCGソフト上で実際の立体形状を作成する工程です。
ポリゴンモデリングでは、点(頂点)、線(エッジ)、面(フェイス)を組み合わせて立体を構築します。基本的な立方体や球体から始めて、徐々に細かい形状を作り込んでいきます。キャラクターの場合は顔の輪郭から始まり、目や鼻、口などの細部を追加していきます。
建築物や機械類の場合は、正確な寸法と形状が重要になるため、CADソフトのような精密なモデリング手法が用いられることもあります。この工程の完成度が最終的な3DCGの品質を大きく左右します。
3. テクスチャリング
テクスチャリングは、作成した3Dモデルに色や質感を与える工程です。
UV展開という作業で、3Dモデルの表面を2次元の平面に展開し、そこに画像(テクスチャ)を貼り付けます。木材なら木目の質感、金属なら光沢や反射、布なら織物の質感など、材質に応じた適切なテクスチャを適用することで、リアルな外観を実現します。
近年では、物理ベースレンダリング(PBR)という手法が主流となり、より科学的に正確な材質表現が可能になっています。この技術により、光の当たり方や反射の仕方が現実に即した自然な表現を実現できます。
4. リギング・スキニング
アニメーション制作を行う場合に必要な工程で、3Dモデルに骨格を設定し、動きを制御できるようにします。
リギングでは、キャラクターや動かしたいオブジェクトの内部に仮想的な骨(ボーン)を配置し、関節の動きや制限を設定します。人型キャラクターの場合、背骨から手足の関節まで、実際の人間の骨格に近い構造を作成します。
スキニングは、設置したボーンと3Dモデルの表面(メッシュ)を関連付ける作業です。どの部分がどのボーンの影響を受けるかを細かく調整することで、自然な変形を実現します。肘を曲げた時に腕の筋肉がどう変形するかなど、リアルな動きを再現するための重要な工程です。
5. アニメーション
リギングが完了したモデルに実際の動きを付ける工程です。
キーフレームアニメーションでは、重要なポーズの瞬間(キーフレーム)を設定し、その間の動きをソフトウェアが自動的に補間します。歩行や走行、表情の変化など、様々な動作を時間軸に沿って設定していきます。
モーションキャプチャーを使用する場合は、実際の人間の動きをセンサーで記録し、3Dキャラクターに適用します。これにより、よりリアルで自然な動きを効率的に作成できます。タイミングや緩急の調整により、キャラクターに個性や感情を表現することも可能です。
6. ライティング
3Dシーンに光源を配置し、適切な照明効果を設定する工程です。
主要な光源として、太陽光を模した指向性ライト、室内照明を再現するポイントライト、面全体から光を放つエリアライトなどを組み合わせて使用します。光の色温度、強度、影の硬さなどを調整することで、時間帯や場所の雰囲気を表現できます。
HDRIという技術を使用することで、実際の環境の光情報を3Dシーンに取り込み、よりリアルな照明効果を実現することも可能です。ライティングの質は最終的な映像の印象を大きく左右するため、慎重に設定する必要があります。
7. レンダリング
すべての設定が完了した3Dシーンを、最終的な2D画像や動画として出力する工程です。
レンダリングエンジンが、3D空間内のオブジェクト、テクスチャ、ライティング、カメラ設定などの情報を総合的に計算し、視覚的な画像として変換します。この計算処理は非常に重い作業で、高品質な映像ほど長時間を要します。
静止画の場合は数分から数時間、映像の場合は1フレームあたり数分から数十分かかることもあります。レンダリング設定により品質と処理時間のバランスを調整し、用途に応じた最適な出力を行います。完成した画像や映像は、さらに後処理ソフトで色調補正やエフェクトの追加を行う場合もあります。
3DCG制作におすすめのソフト一覧
3DCG制作には専用のソフトウェアが必要で、用途や予算、スキルレベルに応じて適切なソフトを選択することが重要です。無料で高機能なソフトから、プロの現場で使われる高価な業界標準ソフトまで様々な選択肢があります。以下では、初心者からプロまで幅広く推奨される代表的な3DCGソフトを紹介します。
| ソフト | 価格(税込) | 主な用途 |
|---|---|---|
| Blender | 完全無料 | 総合3DCG制作(モデリング・アニメーション・レンダリング) |
| Maya | 年間286,000円 | 映画・アニメ・ゲームのキャラクターアニメーション |
| 3ds Max | 年間286,000円 | ゲーム開発・建築ビジュアライゼーション |
| Cinema 4D | 年間134,640円 | モーショングラフィックス・映像制作・CM制作 |
| ZBrush | 年間69,740円 | デジタル彫刻・高精細キャラクター制作 |
※価格は2025年5月時点の参考価格です。価格設定や為替レートによって調整される可能性があります。
Blender
Blenderは完全無料のオープンソース3DCGソフトで、世界中で最も注目されている3DCG制作ツールの一つです。
モデリングからアニメーション、レンダリングまで3DCG制作のすべての工程を一つのソフトで完結できる統合型ソフトとして設計されています。高性能なCyclesレンダーエンジンを標準搭載し、プロレベルのフォトリアルな映像制作が可能です。また、VFX、スカルプティング、2Dアニメーション機能まで備えており、幅広い創作活動に対応できます。
無料でありながら商用利用も可能で、個人クリエイターから大手制作会社まで幅広く採用されています。日本語にも対応し、豊富なチュートリアルやコミュニティサポートがあるため、初心者でも学習しやすい環境が整っています。
Maya
Mayaはオートデスク社が開発する業界標準の3DCGアニメーションソフトで、映画やゲーム制作の現場で最も信頼されているツールです。
ハリウッドの大手映画スタジオをはじめ、国内外のプロダクション現場で圧倒的な実績を誇り、『ファイナルファンタジー』シリーズや『バイオハザード』などの有名作品でも使用されています。高度なキャラクターアニメーション機能、物理シミュレーション、VFX制作機能を搭載し、複雑な映像表現を実現できます。
PythonやMELスクリプトによる拡張性の高さが特徴で、制作現場のニーズに応じたカスタマイズが可能です。サブスクリプション制で提供され、年間約30万円程度の費用がかかりますが、プロフェッショナルな3DCG制作には欠かせないソフトとして位置づけられています。
3ds Max
3ds Maxはオートデスク社のもう一つの主力3DCGソフトで、特にゲーム開発と建築ビジュアライゼーション分野で強みを発揮します。
豊富なプラグインエコシステムを持ち、様々な拡張機能により制作の幅を大きく広げることができます。モデリング機能に優れ、建築パースやプロダクトデザインの分野では特に高い評価を得ています。また、Character Studioによるキャラクターアニメーション機能も充実しており、ゲーム制作現場でも広く採用されています。
Windows専用ソフトという制限がありますが、CADソフトとの連携性が高く、建築業界では設計から完成予想図制作まで一貫したワークフローを構築できます。Mayaと同様にサブスクリプション制で、用途に応じてMayaと使い分けられることも多いソフトです。
Cinema 4D
Cinema 4DはドイツのMaxon社が開発する3DCGソフトで、直感的な操作性とモーショングラフィックス機能の充実で知られています。
最大の特徴は非破壊的なワークフローで、制作過程でのやり直しや修正が容易に行えるため、創造的な試行錯誤を効率的に進められます。MoGraph機能による複雑なモーショングラフィックス制作や、Adobe After Effectsとの緊密な連携により、映像制作の現場で重宝されています。
学習コストが比較的低く、初心者でも短期間で基本操作を習得できるという利点があります。近年はRedshiftレンダーエンジンが標準搭載され、高品質なレンダリングも可能になりました。テレビCMやプロモーション映像、アニメ制作などの分野で特に人気が高いソフトです。
ZBrush
ZBrushは元Pixologic社(現Maxon社)が開発したデジタル彫刻に特化した3DCGソフトで、高精細なキャラクターやクリーチャー制作の業界標準として確立されています。
粘土を捏ねるような直感的な操作でデジタル彫刻が行え、数百万ポリゴンの高密度メッシュを軽快に扱えることが最大の特徴です。映画やゲームのキャラクター制作、フィギュア原型制作、ジュエリーデザインなど幅広い分野で活用されており、ハリウッド映画の多くのクリーチャーがZBrushで制作されています。
200種類以上の専用ブラシと独自のツール群により、他のソフトでは困難な有機的で複雑な造形を効率的に行えます。近年はiPad版もリリースされ、タブレットでも本格的なデジタル彫刻が楽しめるようになりました。彫刻やフィギュア制作経験者には特に親しみやすいソフトです。
3DCG学習のロードマップ
3DCG学習は段階的なアプローチが成功の鍵となります。適切な環境構築から始まり、基礎技術の習得、実践的な作品制作を経て、最終的に専門分野への特化を目指す流れが効果的です。各段階で必要な期間や学習内容を理解し、自分のペースで着実にスキルアップを図りましょう。
学習準備・環境構築
3DCG学習を始める前に、適切な学習環境を整えることが重要です。まず、PCスペックの確認と必要に応じた強化を行います。最低でもメモリ16GB、グラフィックカードは専用GPU(NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER / RTX 3050、またはAMD Radeon RX 6500 XT 以上などを推奨)を搭載したPCが必要です。
次に、学習目的に応じたソフトウェアの選択を行います。初心者は無料のBlenderから始めることをおすすめします。学習リソースとして、公式チュートリアル、YouTube動画、オンライン講座などを事前に調査し、学習計画を立てましょう。
基礎技術の習得
基礎技術の習得段階では、3DCG制作の核となる基本操作と概念を学びます。最初に3DCGソフトの基本操作(ナビゲーション、オブジェクト操作、基本ツール)を習得し、次にモデリングの基礎(基本図形の変形、ポリゴンモデリング、UV展開)を学習します。
同時に、3DCG制作の基本概念(座標系、ライティング、マテリアル、レンダリング)についても理解を深めます。この段階では簡単なオブジェクト制作を通じて、実際に手を動かしながら学ぶことが重要です。期間の目安は3-6ヶ月程度です。
実践・作品制作
基礎を習得したら、実際に作品制作を通じてスキルを向上させる段階に入ります。まず、小さなプロジェクトから始めて徐々に複雑な作品に挑戦します。静物のモデリングから始まり、キャラクター制作、簡単なアニメーション制作へと段階的に難易度を上げていきます。
作品制作では、企画から完成まで一連の制作工程を経験することで、実践的なスキルを身につけられます。完成した作品はポートフォリオとして蓄積し、定期的に他者からフィードバックを得ることで、客観的な視点からスキル向上を図ります。
専門分野への特化
基本スキルが身についたら、自分の興味や目標に応じて専門分野を選択し、深く学習を進めます。主な専門分野には、キャラクターモデリング、背景・環境制作、アニメーション、VFX、ゲーム開発などがあります。各分野では特有の技術やワークフローがあるため、専門的な教材や業界標準のツールを使った学習が必要です。
また、業界のトレンドや新技術についても継続的に情報収集を行い、実際のプロジェクトや就職活動に向けた準備を進めます。この段階では、オンラインコミュニティへの参加やプロとのネットワーキングも重要な要素となります。
3DCG制作にかかる費用
3DCG制作の費用は、制作内容や品質、制作者のスキルレベルによって大きく変動します。個人クリエイターへの依頼から制作会社への発注、既存モデルの購入、自作まで様々な選択肢があり、それぞれ異なる費用構造を持っています。予算と求める品質のバランスを考慮して最適な選択肢を検討しましょう。
個人クリエイターへの依頼相場
個人クリエイターへの3DCG制作依頼は、比較的リーズナブルな価格で高品質な作品を得られる選択肢です。詳細度や複雑さによって価格は変動し、シンプルなキャラクターモデル制作の場合は数万円〜十数万円と比較的安価ですが、リアルな人間キャラクターや複雑な機械モデルの場合は数十万円からが目安です。
アニメーション制作を含む場合は、1秒あたり3万円~10万円程度の追加費用が発生します。個人クリエイターは制作会社と比べて中間コストが少ないため、同等の品質でもより安価で依頼できることが多く、密なコミュニケーションも取りやすいメリットがあります。
【価格帯別】個人クリエイターへの依頼相場
- シンプルなキャラクターモデル:5万円~15万円程度
- リアルな人間キャラクター:20万円~50万円程度
- 複雑な機械モデル:20万円~50万円程度
- アニメーション制作:1秒あたり3万円~10万円程度
制作会社への依頼相場
制作会社への依頼は品質とサポート体制の充実が期待できる反面、費用は個人クリエイターより高額になります。何を制作するかによって費用は大きく変動し、数十万円から数百万円が目安となります。
制作会社の場合、プロジェクト管理、品質保証、修正対応、納期管理などが含まれるため、大規模プロジェクトや企業案件では安心感があります。また、複数のスペシャリストが連携するため、個人では対応困難な高度な技術要求にも応えられます。
【価格帯別】制作会社への依頼相場
- キャラクターモデル制作: 20万円~100万円程度
- 背景・シーン制作: 50万円~300万円程度
- フル3DCGアニメーション制作: 1分あたり100万円~500万円程度
既存モデル購入の費用相場
既存3DCGモデルの購入は、最も手軽で即座に利用できる選択肢として人気があります。
汎用的な3Dモデルは数千円~数万円程度で購入でき、TurboSquidやCGTraderなどの大手マーケットプレイスで豊富な選択肢があります。高品質なキャラクターモデルや詳細な建築モデルの場合は数万円~十数万円程度になることもあります。
ライセンス形態により価格が異なり、個人利用限定、商用利用可能、再配布可能などの条件によって価格設定が変わります。既存モデルは制作時間を大幅に短縮できるため、プロトタイプ制作や予算を抑えたい場合に効果的です。
自作する場合の費用相場
3DCGを自作する場合の費用は、主にソフトウェアライセンス料と学習コスト、制作時間のコストで構成されます。
ソフトウェア費用として、Blenderなら無料です。有料のプロフェッショナル向け3DCGソフトウェアの場合、年間サブスクリプション費用はソフトによって異なり、一般的に年間約7万円から30万円程度の範囲で考慮する必要があります(例:Cinema 4D 年間約13.5万円、Maya 年間約28.6万円など ※2025年5月時点の税込価格)。
ハードウェア費用として、3DCG制作に適したPCは20万円~50万円程度の投資が必要です。長期的には最も経済的な選択肢となる可能性がありますが、初期投資と学習期間を確保できる場合に限定されます。
3DCGに関するよくある質問
Q1. 3DCG制作にはどのようなスペックのパソコンが必要ですか?
A. 最低限快適に学習を始めるためのスペックとして、CPUは近年のIntel Core i5以上またはAMD Ryzen 5以上、メモリは16GB以上、グラフィックカードは専用GPU(NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER / RTX 3050、またはAMD Radeon RX 6500 XT 以上など)を推奨します。本格的な制作やより複雑なシーンを扱う場合は、メモリ32GB以上、NVIDIA GeForce RTX 3070以上のGPUが理想的です。ストレージは高速なSSDが必須で、プロジェクトの規模に応じて十分な容量を確保しましょう。
Q2. 3DCGの習得にはどのくらいの期間がかかりますか?
A. 基礎知識の習得には約3-6ヶ月、実用的なスキルの獲得には1-2年程度が目安です。毎日2-3時間の学習を継続した場合、半年でシンプルなモデル制作、1年で基本的なアニメーション制作が可能になります。プロレベルに達するには3-5年の継続的な学習と実践が必要で、個人の努力や学習環境によって大きく期間は変わります。
Q3. 3DCGソフトの中で最も学習しやすいのはどれですか?
A. 初心者には「Blender」が最もおすすめです。完全無料でありながら高機能で、日本語対応も充実しており、YouTube等で豊富な学習コンテンツが提供されています。操作が直感的で、モデリングからアニメーションまで一つのソフトで完結できます。商用利用も可能で、プロの現場でも使われているため、学習投資に対するリターンが高いソフトです。
Q4. 3DCGと2DCGの違いは何ですか?
A. 3DCGは立体的な空間で奥行きを持つ表現が可能で、視点を自由に変更できるのが特徴です。一方、2DCGは平面的な表現で、手描きのような温かみのある表現が得意です。3DCGはゲームや映画のVFXに、2DCGはイラストやアニメに多用されます。制作工程や必要なスキルも大きく異なり、3DCGはより技術的、2DCGはより芸術的な側面が強い傾向があります。
Q5. 3DCGと2DCGはどちらから学ぶべきですか?
A. 目標によって選択が変わります。ゲーム制作や映像制作を目指すなら3DCGから、イラストやキャラクターデザインが目標なら2DCGから始めるのが効率的です。ただし、デザインの基礎となる構図や色彩理論は共通するため、2DCGで基礎を学んでから3DCGに進む方法も有効です。最も重要なのは自分の興味と将来のビジョンに合わせて選択することです。
まとめ:3DCGは幅広い分野で活用できる制作技術
3DCGとは、3次元空間でデジタル映像を作成する技術で、映画・ゲーム・建築・製品デザインなど様々な業界で実用的に活用されています。
BlenderやMayaなどの制作ソフトが充実し、モデリングからアニメーションまで段階的に学習することで、個人でも本格的な3DCG制作が可能です。特にVTuberやメタバースの普及により、アバター制作の需要が高まっており、3DCGスキルを身につけたい方にとって魅力的な分野といえるでしょう。
もし3DCGのアバター制作でお困りの際は、VTuberモデル制作を通じて、デジタルギアが豊富な実績とノウハウを持っています。本格的な3DCG制作の取り組みを検討されている方は、ぜひ一度デジタルギアにご相談ください。