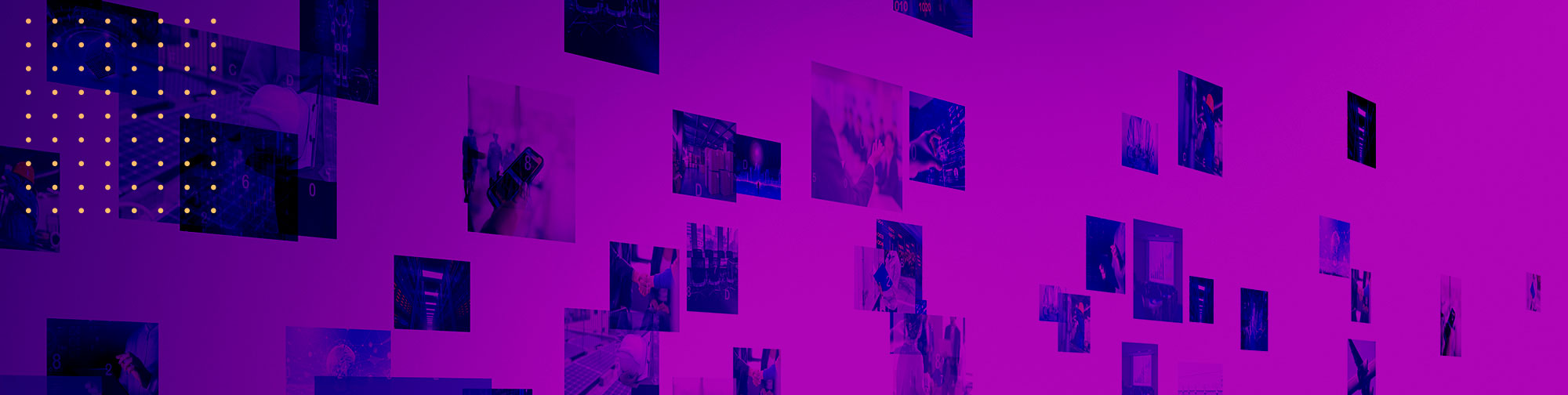記事一覧

オリジナルキャラクターとは?作り方や活用シーンを解説
オリジナルキャラクターとは?作り方や活用シーンを解説
「オリジナルキャラクターを作って活動してみたい」と思っても、何から手をつけてよいか分からず、立ち止まっていませんか?
近年では、個人でもSNSやYouTube、VTuber活動を通じて、自分だけのキャラクターで発信やブランディングを行うケースが増えています。企業でもマスコットキャラクターを使った広報が当たり前になるなか、オリジナルキャラクターの持つ影響力はますます高まっています。
とはいえ、いざ作ろうとすると「どう設定を考える?」「デザインは自分でやる?依頼する?」「どこで活用する?」など、疑問や悩みも尽きません。
この記事では、オリジナルキャラクターを初めて作る方に向けて、基本的な考え方から具体的な制作ステップ、活用のヒントまで、わかりやすく解説します。自分だけのキャラで発信したい方や、創作活動の武器にしたい方はぜひ参考にしてください。
この記事でわかること
- オリジナルキャラクターは個人ブランディングやVTuber活動など幅広いシーンで活用できる
- 効果的なキャラ作りには目的設定→性格設定→ビジュアル決定→デザイン作成の体系的なステップが重要
- 魅力的なキャラ設定にはギャップや一貫性を意識し、他との差別化を図ることがポイント
- デザインでは配色やシルエット、性格と外見の連動性を重視する
- 完成したキャラクターはVTuber活動、SNS発信、グッズ展開など多様な方法で収益化も可能
おすすめ記事
目次
オリジナルキャラクターとは
オリジナルキャラクターとは、自分自身のアイデアから生み出された架空のキャラクターのことです。既存の作品に登場するキャラクターを真似るのではなく、世界観や設定、見た目まで完全にゼロから生み出すオリジナルの存在です。
最近では、VTuberとして活動したり、SNSで発信したりと、個人がキャラクターを使って表現する場面が急増しています。キャラクターを通じて自分の考えや価値観を発信し、ファンとつながる手段として注目されています。
特に「推し活」や「キャラ推し」といった文化の広がりにより、魅力あるオリジナルキャラクターに共感し、応援する人も増えています。こうした背景もあり、自分だけのキャラクターをつくることは、今やクリエイティブな自己表現としても、ブランディング手法としても非常に価値のある取り組みになっています。
オリジナルキャラクターの活用シーン
オリジナルキャラクターは、SNSや配信、ビジネスの現場など、さまざまな場面で活用できます。ここでは、実際に多く使われている代表的な活用例を紹介します。
マスコットキャラクターとしてのブランディング活用
企業や個人事業主が、自社のブランドイメージをよりわかりやすく伝えるためのマスコットキャラクターとして、オリジナルキャラクターを起用する例が増えています。特に、堅苦しくなりがちなビジネスの場面でもキャラクターがやわらかい窓口となってくれるため、初対面の相手とも距離を縮めやすくなります。
例えば、会社のウェブサイトや名刺、パンフレット、プレゼンテーション資料など、あらゆる媒体でキャラクターを登場させることで、一貫したブランドイメージを構築できます。特に、一度見たら忘れにくい、愛着の湧くキャラクターは、顧客との心理的な距離を縮め、良い関係を築く上で大いに役立ちます。
自治体の観光・PRキャラとして地域活性化
「くまモン」や「バリィさん」のように、ご当地キャラクターが地域の活性化に大きく貢献した成功事例は数多く存在します。その地域の特産品や観光名所をモチーフにしたオリジナルキャラクターは、地域の知名度を飛躍的に向上させる力を持っています。
こうしたキャラクターは、イベントへの登場やポスター、道の駅でのグッズ販売など、多岐にわたる場面で活用できます。さらに、SNSや動画コンテンツで地域の情報を発信する「アンバサダー役」としても高い人気を集めています。地域外の人々にも親しまれやすいため、観光客の誘致や特産品の販売促進において、強力な武器となるでしょう。
採用・人材育成コンテンツへの導入
企業の採用活動や社員研修に、キャラクターを取り入れる動きも広がっています。採用サイトや説明会資料にキャラクターを登場させることで、企業に対して親近感を抱いてもらいやすくなります。特に、若い世代の求職者に対しては、堅い企業イメージを和らげ、よりフレンドリーな会社であることをアピールする効果が期待できます。
また、社内研修や業務マニュアルにキャラクターを登場させることで、学習内容の理解度を高めたり、従業員の学習意欲を向上させたりする効果も見込めます。Z世代と呼ばれるデジタルネイティブ世代とのコミュニケーション手段として、その有効性がますます注目されています。
オリジナルキャラクターの作り方【基本ステップ】
魅力的なオリジナルキャラクターを生み出すためには、段階を踏んで制作を進めることが大切です。以下の5つのステップに沿って、計画的にキャラクター制作を進めていきましょう。
- キャラの目的を明確にする(誰にどう使うか)
- キャラクター設定を考える(性格・口調・年齢・背景)
- ビジュアルの方向性を決める(現代系/ファンタジー/ゆるキャラなど)
- デザインラフを描く(自分で/依頼/AIで)
- 名前とプロフィールを仕上げる
順番にわかりやすく解説します。
このセクションの目次
① キャラの目的を明確にする(誰にどう使うか)
キャラクター制作を始めるにあたって、まず最初に行うべきことは、「なぜこのキャラクターを作るのか」「誰に向けて、どのように活用するのか」という目的をはっきりとさせることです。この目的が曖昧なままだと、その後のキャラクター設定やデザインに一貫性がなくなり、結果として人々に響く魅力的なキャラクターにはなりません。
例えば、以下のような目的が考えられます。
- VTuber活動で配信するためのキャラクターとして活用する
- SNSでの個人ブランディング用アイコンにする
- 企業のマスコットキャラクターとして起用する
- 漫画や小説、ゲームなどの創作活動における主人公にする
- 商品やサービスのイメージキャラクターとして使う
加えて、そのキャラクターがどのような層(年齢、性別、趣味嗜好など)に届いてほしいのか、具体的なターゲット層を設定することも成功への重要な鍵となります。ターゲットに深く響く要素を盛り込むことで、キャラクターの魅力は格段に高まります。
② キャラクター設定を考える(性格・口調・年齢・背景)
次に、キャラクターの内面的な部分を詳細に設定していきます。この段階で決めた設定が、後に行うビジュアルデザインや、キャラクターをどのように活用していくかの方向性を大きく左右するため、じっくりと時間をかけて検討しましょう。
性格設定では、単に「明るい」「内気」「クール」「天然」といった基本的な性格だけでなく、趣味や特技、好きなもの・嫌いなもの、どんな価値観を持っているかなども深掘りします。また、口調については、キャラクターの年齢や性格、さらには出身地などを反映させ、常に一貫性を持たせることが大切です。
年齢や背景を設定する際には、生い立ちや家族構成、現在の状況なども考慮することで、より深みのあるキャラクターとして立ち上がります。ただし、あまりに設定を複雑にしすぎると、いざ活用する際に混乱を招く可能性もあるため、適切なバランスを見つけることが重要です。
③ ビジュアルの方向性を決める(現代系/ファンタジー/ゆるキャラなど)
キャラクターの内面設定が固まったら、次にその世界観とビジュアルの方向性を決めていきます。設定した性格やキャラクターの活用目的に合わせて、最適なテイストを選択することが重要です。
例えば、現代を舞台にするなら学生や会社員、カジュアルなファッションなど、身近な要素を取り入れると良いでしょう。一方で、ファンタジーの世界であれば、魔法使いや騎士の装束、あるいは異世界を思わせるような衣装を採用します。親しみやすさを重視した「ゆるキャラ」であれば、可愛らしくデフォルメされたデザインを心がけます。
この段階で、イメージに近い既存のキャラクターやアート作品などを参考に集め、イメージボードを作成しておくと、デザインの方向性がより明確になり、スムーズに次のステップへ進めます。
④ デザインラフを描く(自分で/依頼/AIで)
いよいよ、具体的なビジュアルデザインを作成します。自分で描く場合は、まず大まかなラフスケッチで全体のシルエットやキャラクターの印象を確認し、そこから少しずつ詳細なデザインを加えていきます。
イラストレーターに依頼する際は、作成した設定資料や集めた参考画像を提示し、イメージを正確に伝えることが、満足のいく仕上がりを得るために重要です。
AI画像生成ツールを利用する際には、様々なプロンプト(指示文)を試して複数のデザインパターンを生成し、その中から最もイメージに合うものを選び、必要に応じて微調整を加えていきましょう。
どの方法を選択するにしても、設定したキャラクター像との整合性を常に確認しながら進めることが、ブレのないキャラクター制作につながります。
⑤ 名前とプロフィールを仕上げる
キャラクターの見た目が形になったら、最後に名前と詳細なプロフィールを完成させます。名前は、一度聞いたら忘れにくく、キャラクターの個性や印象にぴったりのものを選びます。必要に応じて、漢字表記やローマ字表記も決めておくと良いでしょう。
プロフィールには、身長・体重・誕生日・血液型といった基本情報に加え、詳細な性格設定、趣味や特技、好きなもの・苦手なもの、口癖、決めゼリフなどを盛り込みます。キャラクターの活用シーンに合わせて、必要な項目をさらに追加することも検討しましょう。
VTuberやマンガ、SNSで活用する場合は、プロフィールを設定資料としてまとめておくと、表現に一貫性を持たせやすくなります。
魅力的なキャラ設定を作るコツ
キャラクター設定は、ただ情報を並べるだけでは印象に残りません。人に愛され、共感されるキャラクターに仕上げるには、いくつかの工夫が必要です。ここでは、キャラづくりをより魅力的にするための実践的なコツを紹介します。
ギャップ・矛盾を意識して人間味を出す
完璧すぎるキャラクターは、かえって魅力に欠けることがあります。性格や行動にちょっとしたギャップや矛盾を持たせることで、ぐっと人間らしさが出て、魅力的になります。
例えば、「見た目はクールなのに甘い物が大好き」「強そうに見えるけど実は高所恐怖症」「頭が良いのに方向音痴」など、意外なギャップがあると、キャラクターに奥行きが生まれます。
ただし、あまりにもギャップが大きすぎると、一貫性のないキャラになってしまうため注意が必要です。キャラの軸はしっかり保ちつつ、適度な意外性を盛り込むのがポイントです。
「世界観」「役割」「口調」まで一貫性を持たせる
キャラクターが所属する世界観やストーリー、役割と口調がバラバラだと、読者や視聴者に違和感を与えてしまいます。例えば、ファンタジーの魔法使いキャラが現代のJKのような話し方をしていたら、世界観が崩れてしまいます。
反対に現代の高校生キャラなら、若者言葉や今どきの言い回しを意識するとリアリティが増します。時代設定が異なるなら、その時代に合った口調や語彙を使うことが大切です。
設定をまとめる際は、性格・背景・ビジュアル・話し方などが矛盾していないかを定期的に見直すようにしましょう。統一感のあるキャラクターは、見る人に安心感と説得力を与えます。
性格診断ツールやテンプレを活用する
性格の設定に悩んだときは、MBTI(16タイプ性格診断)やエニアグラムといった診断ツールを参考にしてみるのもひとつの手です。これらのツールを使うことで、キャラクターの具体的な行動パターンや思考の癖、さらには他者との関わり方などが自然と決まり、より一貫性のある性格を作りやすくなります。
また、同じ性格タイプの実在の人物や、他の作品に登場するキャラクターを参考にすることで、より深みのあるキャラクター設定を構築することも可能です。
ただし、ツールの結果をそのまま当てはめるのではなく、あくまでヒントとして活用し、自分のキャラに合うようにアレンジを加えることが大切です。ツールを活用する際には、独自性が失われないように注意しましょう。
他キャラとの差別化ポイントを意識する
オリジナルキャラクターを目立たせるためには、ほかのキャラクターとしっかり差別化することが重要です。既に似たようなキャラクターがいないかをチェックし、自分のキャラならではの特徴を強調しましょう。
差別化のポイントとしては、以下のようなものがあります。
- 外見:髪型・服装・小物など
- 性格:言葉づかいや価値観、癖のある行動
- 背景:出身地・家族構成・経験した出来事
さらに、「和風×サイバーパンク」や「魔法使い×現代ファッション」といった、ジャンルを掛け合わせたユニークな設定にすると、強いインパクトを与えることも可能です。既存の型にとらわれず、自由な発想であなただけのキャラクターを形にしてみましょう。
キャラクターデザインの考え方
キャラクターの魅力を引き出すうえで、ビジュアルデザインは欠かせない要素です。色の使い方やシルエット、性格とのバランスなど、デザインにはいくつかの基本ルールがあります。ここでは、印象に残るキャラクターをつくるための考え方と実践的なテクニックを紹介します。
配色(テーマカラー・補色)の重要性
キャラクターが与える印象を大きく左右するのが「配色」です。メインカラーとサブカラーを適切に設定することで、キャラクターの個性や彼らが存在する世界観を効果的に表現することが可能になります。
キャラクターのテーマカラーは、その性格や役割に合わせて慎重に選びましょう。使用するメインカラーによって、以下の表のように与える印象が異なります。
| カラー | 与える印象 | 主な適用例 |
|---|---|---|
| 赤 | 情熱的・活発・リーダーシップ | 主人公・戦闘系キャラなど |
| 青 | 冷静・知的・誠実 | 魔法使い・学者タイプなど |
| 緑 | 自然・癒し・平和 | ヒーラー・自然系など |
| 紫 | 神秘的・高貴・芸術肌 | 王族・芸術家・魔術師系など |
選んだメインカラーの「補色」を効果的にアクセントとして使うことで、デザイン全体の視覚的な魅力を一層高めることができます。
さらに、使用する色数を3~4色程度に抑えることで、デザイン全体に統一感が生まれ、より洗練された印象を与えることができます。
シルエットのわかりやすさ
優れたキャラクターデザインは、そのシルエットを見るだけで「このキャラクターだ」と認識できるほど特徴的です。遠くから見たり、影絵になったりしても、誰であるかがはっきりと識別できるようなデザインを心がけることが重要です。
髪型や服装、持っているアイテム、あるいは身体的な特徴によってシルエットに独自の個性を加えることで、キャラクターは見る人の記憶に残りやすくなります。特に、頭部のシルエット(髪型、帽子、アクセサリーなど)は、キャラクターの識別に最も重要な要素と言えるでしょう。
複数のキャラクターをデザインする場合には、それぞれのシルエットが明確に区別できるよう、意図的に差別化を図ることが大切です。
性格と外見をリンクさせる方法
キャラクターの内面(性格)と外見が一致していると、そのキャラクターはより説得力を持ち、魅力的に映ります。見た目からある程度の性格が想像できるようなデザインにするか、あるいはあえて意外性を演出できるよう設計するのも効果的です。
例えば、活発な性格のキャラなら明るい色合いや動きやすい服装、内気なキャラなら落ち着いた色味や露出を抑えた服装など、性格の特性を外見で表現することができます。また、表情や姿勢もキャラクターの性格を反映させることで、より生き生きとした魅力的な存在となるでしょう。
一方で、意図的に外見と性格の間にギャップを作り出すことで、キャラクターに深みと奥行きを与えることも可能です。この場合、なぜそのギャップが生まれたのかという背景や理由付けをしっかりと設定することが重要になります。
立ち絵・表情差分・全身図の使い分け
キャラクターを様々な場面で活用するためには、目的に応じて適切な種類のイラストを使い分けることも重要です。それぞれのイラストが持つ役割を理解し、効果的に活用していきましょう。
「立ち絵」は、VTuberとしての配信活動やゲーム、SNSのアイコンなどで最も頻繁に使用される、キャラクターの基本イラストです。「表情差分」は、感情の動きや状況変化を表現するためのパーツ。喜怒哀楽はもちろん、照れ・困り・無表情など複数用意しておくと、演出の幅が広がります。
「全身図」は、キャラクターの全体像を見せたいときに使用するイラストです。グッズ制作やポスター、キャラクターの設定資料などで活用されます。それぞれの用途をあらかじめ明確にしておくことで、必要なイラスト制作を効率的に進めることができます。
オリジナルキャラクターの活用アイデア
オリジナルキャラクターは、様々な場面で効果的に活用できます。ここでは、実際に人気を集めている活用方法を紹介します。
Vtuber活動・SNSアイコン・マンガ連載など
VTuberとしての活動は、オリジナルキャラクターを活用する上で現在最も人気の高い方法の一つです。
Live2DモデルやVRMモデルとしてキャラクターを動かせるようにすれば、YouTubeやTwitch、ニコニコ生放送といったプラットフォームで、あたかもキャラクター自身が話しているかのように配信やコンテンツ制作ができます。
SNSでの活用も非常に有効です。プロフィール画像やヘッダー、投稿イラストにキャラを使えば、アカウントに一貫性が生まれ、ブランディング効果が高まります。X(旧Twitter)やInstagram、TikTokなどでキャラの個性を発信することで、フォロワーとの関係性も深めやすくなります。
また、オリジナルキャラクターを主人公にした4コマ漫画やストーリー漫画を連載するのも人気の活用法です。SNSやブログに投稿すれば、作品の世界観を伝えながらファンを増やすことができます。日常系からファンタジーまで、ジャンルは自由。アイデア次第で展開の幅が広がります。
LINEスタンプやグッズ展開
LINEスタンプは、キャラクターを商用利用する入り口としておすすめです。スタンプ画像を40個を作ってLINEクリエーターズマーケットに登録するだけで、全世界に販売できます。キャラクターの表情やセリフをうまく活かせば、スタンプをきっかけに知名度も広がります。
さらに、キャラクターをモチーフにしたグッズ展開もおすすめです。グッズ展開では、以下のような商品が定番です。
- アクリルスタンド・キーホルダー
- 缶バッジ・ステッカー
- Tシャツ・パーカーなどのアパレル
- マグカップ・タンブラー
- スマホケース・モバイルアクセサリー
- ポストカード・クリアファイル
これらのグッズは、イベントでの販売やオンラインストアを通じて、ファンとの接点を増やし、キャラクターの知名度を高めることができるでしょう。
自社サービスのマスコットキャラとして使う
企業や個人事業主が、自社のオリジナルキャラクターをマスコットキャラクターとして活用することで、ブランドの親しみやすさを向上させることができます。Webサイトやパンフレット、名刺、プレゼンテーション資料など、あらゆる媒体でキャラクターを一貫して使用することで、企業イメージをより浸透させることができます。
また、カスタマーサポートでキャラクターを活用するのも良いアイデアです。よくある質問(FAQ)の回答や操作説明にキャラクターが登場することで、堅苦しくなりがちな内容を、より親しみやすく、分かりやすく伝えることができます。特に、ITサービスや金融サービスなど、専門的で難しく感じられやすい分野で効果を発揮するでしょう。
SNSマーケティングにおいても、キャラクターがサービスの最新情報や特徴を発信することで、フォロワーとの心理的な距離を縮め、エンゲージメントの向上につなげることが可能です。
オリジナルキャラクターに関するよくある質問
オリジナルキャラクター制作でよく寄せられる疑問にお答えします。これらの情報を参考に、より効果的なキャラクター制作を進めてください。
Q. オリキャラを作る時、性格設定に悩みます…どうすれば?
A. 「キャラ診断ツール」や「性格テンプレート(MBTI・エニアグラム)」を使うとイメージが明確になります。また、日常で見かける人物をモデルにするのもおすすめです。まずは「こういうセリフを言いそう」と想像してみるのが良いでしょう。
実際の人物の性格を参考にする場合は、著名人や身近な人の特徴的な部分を組み合わせることで、オリジナリティのある性格を作ることができます。また、好きな作品のキャラクターの性格を参考に、独自のアレンジを加える方法もおすすめです。
Q. キャラに名前は必要?どんなふうに決めたらいい?
A. 名前は「覚えやすさ」と「世界観との相性」が大切です。音の響きや意味、語感で選ぶほか、「名前生成ツール」や「日本語と英語のミックス」なども最近ではよく使われています。
また、キャラクターの出身地や時代背景に合わせた名前選びも重要です。現代日本なら一般的な日本名、ファンタジー世界なら造語や英語系の名前が適しています。また、名前の文字数や呼びやすさも考慮し、愛称やニックネームも合わせて考えるとより愛着を持ってもらいやすくなります。
Q. オリキャラを勝手に使われたらどうすればいい?
A. オリキャラに著作権がある場合、無断利用された場合は削除申請や法的対応が可能です。まずはSNSなどでの「利用ルールの明記」や「権利表記(©マーク)」で対策しましょう。必要に応じて商標登録も視野に入れてください。
予防策として、キャラクターを公開する際は必ず著作権表示を行い、利用規約を明確に示すことが重要です。万が一、無断使用を発見した場合は、まずは相手に直接連絡を取り、利用停止を求めるのが一般的です。それでも応じない場合は、プラットフォームへの報告や、必要であれば弁護士に相談し、法的措置を検討することになります。
Q. 商用利用を考えたときの注意点は?
A. 自作であれば基本的にOKですが、AI生成やイラスト依頼の場合は「商用利用可否」を必ず確認してください。素材サイトやイラストレーターによって利用範囲が異なります。トラブルを避けるために利用規約・契約書の確認が必須です。
特に、他者に制作を依頼する場合は、著作権の譲渡や商用利用権について事前に明確な合意を取ることが重要です。また、キャラクターに使用している素材(背景、アクセサリーなど)についても、それぞれの利用規約を確認する必要があります。
Q. オリキャラをVtuber化するには何が必要?
A. Live2Dまたは3Dモデル化が必要です。キャラクターデザイン→モデリング→トラッキングソフト(VTube Studioなど)を使って動かします。依頼、自作、どちらも可能で、予算は5万〜30万円程度が一般的です。
Live2D制作の場合は、キャラクターイラスト、パーツ分け、リギング、物理演算設定の工程があります。3Dモデルの場合は、3Dモデリング、テクスチャ作成、ボーン設定、表情設定が必要です。自作する場合は相応のスキル習得が必要ですが、専門の制作者に依頼することで高品質なモデルを入手できます。
まとめ:オリジナルキャラクターで"推される"発信を
オリジナルキャラクターは、個人の創作活動から企業のマーケティングまで、幅広い場面で活用できる強力なツールです。適切な設定とデザインにより、あなただけの魅力的なキャラクターを生み出すことができます。
オリキャラづくりは、創作活動やマーケティング戦略の核にもなる重要な要素です。この記事で紹介したステップやコツを活用しながら、自分の世界観を伝えるための強い味方として育てていきましょう。
完成したキャラクターは、VTuberデビュー、SNSでの発信、グッズ展開など様々な場面で活用できます。そこから共感やファンとのつながりが生まれ、活動の幅を広げることができるでしょう。
あなたの想いがこもったキャラクターを通じて、見る人・応援する人の心を動かす推される発信を、ぜひ今日から始めてみてください。