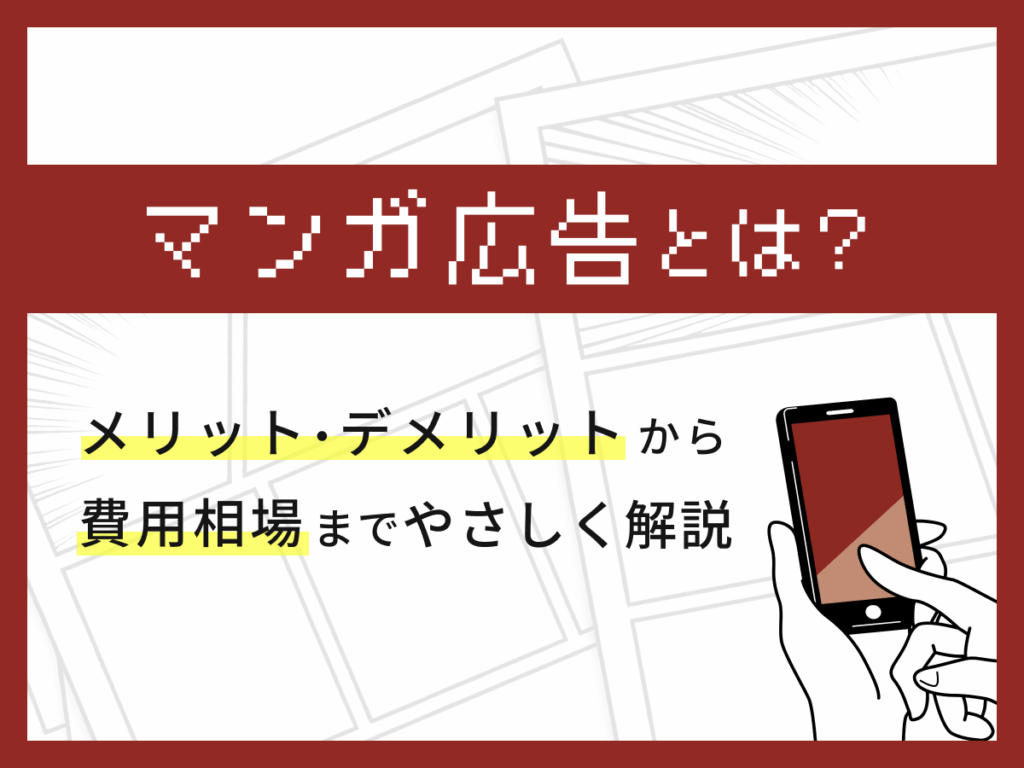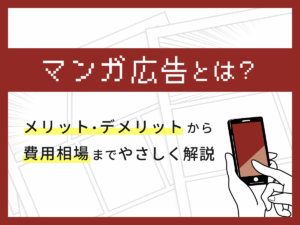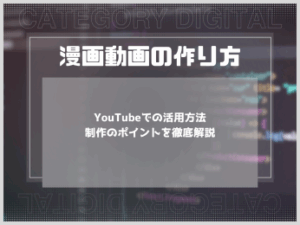マンガ広告は、視線を広告ではなく物語に向けることで、画像や動画とは異なる訴求力を発揮する新しい広告手法です。
背景には、Web上にあふれる広告による視認性の低下や、従来の広告への飽きといった課題があります。その打開策として、物語性とビジュアルを兼ね備えたマンガ広告が注目されています。
「視覚に訴えて記憶に残したい」「広告が見られず効果が出ないと悩んでいる」「VTuberなどのキャラクター施策と掛け合わせたい」といった課題を持つ企業やクリエイターにとってマンガ広告は有効です。
この記事では、マンガ広告の仕組みや注目される理由、導入のメリット・デメリット、費用相場、制作の流れまでをわかりやすく解説します。最後まで読むことで、戦略的な活用方法や成功のためのポイントが理解でき、実際の施策に自信を持って取り組めるようになるでしょう。
この記事でわかること
- マンガ広告の基本構造と注目されている理由がわかる
- メリット・デメリットと自社活用の可否を判断できる
- 費用相場や制作の流れが把握できる
- 制作会社選びや活用シーンの実例が理解できる
- 効果を最大化するポイントや応用策がわかる
マンガ広告とは?
「マンガ広告」という言葉を耳にしたことはあっても、従来のバナー広告や動画広告と何が違うのか、疑問に思う方もいるでしょう。まずは、マンガ広告の定義と特徴、近年注目されている背景について解説します。
マンガ広告の定義と特徴
マンガ広告とは、コマ割りやストーリー展開を用いて情報を伝える広告手法です。一般的なバナーや動画広告とは異なり、登場人物の体験やエピソードを描くことで、読み手の感情を自然に動かします。物語とビジュアルを組み合わせることで、静止画でも動きや時間の流れを感じさせ、視線を引きつける効果があります。
ストーリーによって商品やサービスの背景や使用シーンが自然に描き出されるため、訴求が押しつけがましくなく、理解と共感を得やすい点も魅力です。加えて、SNSやWebメディア上ではタイムラインに溶け込みやすく、拡散力の高いコンテンツとしても注目されています。
マンガ広告が注目される背景
近年、動画広告やバナー広告が急増し、ユーザーの広告耐性は高まりました。その結果、広告が視界に入っても無意識にスルーされる「バナーブラインド」が一般化しています。こうした環境の中で、マンガ形式は視線を引く手段として効果的です。物語型の訴求は理解を促しやすく、企業メッセージへの共感を生みやすいという特長があります。
ストーリー型の訴求は、読者の理解を促しやすく、企業メッセージに対する共感の構築にもつながります。またSNSの普及によって、「面白い」「共感できる」と感じたコンテンツはシェアされやすく、自然な拡散を生む力を持っています。これらの理由から、マンガ広告は従来の広告を補完する新たな手法として、多くの企業から注目を集めています。
マンガ広告のメリット
マンガ広告は、視認性・共感性・拡散性のいずれにおいても、他の広告手法よりも優れています。特にWeb広告においては、ユーザーが「読む」「理解する」「共有する」という一連のアクションに自然につなげられるため、広告効果の最大化が期待できます。以下は、マンガ広告が持つ代表的な6つのメリットです。
- インパクトで注目を集めやすい
- ストーリーで自然に情報を届けられる
- 感情移入しやすく、疑似体験を促進できる
- 多くの情報を短時間で伝えられる
- SNSで拡散されやすいコンテンツになりやすい
- ターゲット層に刺さりやすい設計ができる
それぞれのメリットを詳しく見ていきましょう。
インパクトで注目を集めやすい
マンガ広告は、目を引くビジュアルと構成力によって、Web上でのスクロール中にユーザーの視線を止めやすいという特長があります。通常のバナーと異なり、コマ割りやキャラクターによる表現が「何か物語が始まる」と印象づけ、強い第一印象を与えることができます。
視覚的に動きを感じさせる演出は、広告が静止画であっても動きのあるストーリーとして認識されるため、記憶に残りやすい利点があります。マンガに慣れ親しんでいる日本のユーザーにとって、親しみやすさと新鮮さを同時に提供できる点が大きな強みといえるでしょう。
ストーリーで自然に情報を届けられる
マンガ広告の最大のメリットは、広告感を抑えながら伝えたい情報をストーリーに組み込めることです。主人公のセリフや展開に情報を盛り込むことで、「読んでいたら自然に理解できた」という形で読者の理解を促します。
課題や解決策といった広告の基本要素も、物語構成に組み込むことで押しつけ感を抑えつつ、論理的かつ感情的な納得感を得られます。特にBtoBや複雑なサービスの場合に、難しいことをわかりやすくする手法として効果的です。
感情移入しやすく疑似体験を促進できる
マンガには感情表現をビジュアル化できる特性があり、登場人物が感じている「悩み」「気づき」「成功体験」を読者が自分ごととして捉えやすい特長があります。これは、他の広告手法にはない疑似体験の提供につながります。
結果として、読者は商品やサービスを導入した後の未来をリアルに想像しやすくなり、購買行動や問い合わせへとつながる可能性が高まります。人間は感情に訴えかけられることで記憶や行動に影響を受けやすいため、この点はマーケティングにおいて大きな武器となるでしょう。
多くの情報を短時間で伝えられる
マンガ広告は、視覚情報とテキスト情報を同時に伝える構造を持っており、読者が短時間で多くの情報を理解できるという特性があります。1コマごとにキャラクターのセリフや動き、背景などが描写され、複雑なサービスや商品の特徴でも、直感的に把握しやすくなるのがメリットです。
例えば、機能説明や利用シーンの紹介も、図解やキャラの行動を通して自然に表現できるため、読者が一目で内容を把握できます。これは特に、情報量の多い商材や理解に時間がかかるサービスにおいて効果を発揮します。
さらに、複数の要素を1ページに凝縮しても、ストーリーの流れに乗って読者がスムーズに読み進められるため、情報伝達の効率と読了率を両立できる点も魅力です。読み手の時間を奪わず、最大限の訴求を実現できる広告手法といえます。
SNSで拡散されやすいコンテンツになりやすい
マンガ広告は、SNSとの相性が非常に高いコンテンツ形式として知られています。特に「面白い」「共感できる」「学びがある」といった要素を持たせることで、ユーザーが自発的にシェアしたくなる仕掛けを作りやすくなります。
タイムライン上では、通常の広告はスルーされがちですが、マンガ広告は「物語性」や「視覚的変化」があるため、ユーザーの目に留まりやすく、クリックやタップを誘導しやすい特徴を持ちます。さらに、保存・再投稿されることで、一時的な広告効果に留まらず、長期的に拡散される可能性もあります。
SNS上ではユーザーが感情を共有したいという傾向が強く、その心理にマンガ広告が訴求しやすいこともポイントです。ストーリーによって生まれた感情が「誰かに伝えたい」という動機につながり、自然な拡散と高いエンゲージメントを実現できます。
ターゲット層に刺さりやすい設計ができる
マンガ広告は、ペルソナ設計に沿った表現がしやすく、狙ったターゲット層の心に直接届く広告づくりが可能です。キャラクターの性格や話し方、状況設定を読者の属性に合わせて設計することで、「これは自分のことだ」と思わせる共感の導線を作れます。
広告の構成としても、「共感 → 解決 → 提案」の流れを組み込みやすく、広告にありがちな一方的な押し売り感を回避しつつ、自然なアクション促進につなげることが可能です。
特にSNSを日常的に利用する若年層やデジタルネイティブ世代に対しては、マンガ形式の方が文字広告や動画広告よりも受容されやすい傾向があります。媒体やフォーマットを含めたターゲットとの接点を最適化しやすいという点も、他の広告手法にはない大きな強みです。
マンガ広告のデメリット
どんなに優れた広告手法にも、メリットがあればデメリットも存在します。導入を検討する際は、これらの注意点を把握し、適切な対策や判断材料とすることが重要です。主な注意点は以下の3つです。
- 表現次第で「うざい」と感じられる可能性がある
- 制作に時間とコストがかかる可能性がある
- コンテンツがターゲットに響かないリスクがある
ここから、それぞれのデメリットをわかりやすく解説します。
表現次第で「うざい」と感じられる可能性がある
マンガ広告は訴求力が高い一方で、表現を誤ると逆効果になる恐れもあります。キャラクターのテンションが過剰であったり、ストーリー展開に無理があったりすると、読み手に違和感や不快感を与える可能性があります。
また、広告色が強すぎると「これは読ませるための広告だ」と読者に見抜かれ、読了率や信頼感が低下するリスクもあります。特にSNSでは、押しつけがましい構成や無理なオチはユーザーからの反発を招くため、自然なトーンや誠実なメッセージ設計が求められます。表現の自由度が高い分、読み手の感情を大きく左右する可能性があるため、細心の注意と工夫が必要です。
制作に時間とコストがかかる可能性がある
マンガ広告は「読む広告」である以上、ビジュアル・構成・シナリオすべての品質が重要です。そのため、1枚のバナーや数秒の動画とは異なり、制作工程が多く、工数やコストがかさむ傾向があります。
構成案の作成、キャラクター設定、ネーム、作画、修正といったステップがあり、短納期で高品質に仕上げるには難しいケースもあります。外注する場合は10万円〜数十万円の費用が発生することも珍しくありません。
コストと時間のバランスを考慮せずに導入を進めてしまうと、費用対効果(ROI)が見合わない事態にもなりかねません。導入前に予算とスケジュールを明確にし、リソース計画を立てておくことが重要です。
コンテンツがターゲットに響かないリスクがある
どれだけ丁寧に制作しても、ペルソナ設計や構成がズレていれば効果は出にくくなります。「面白さ」や「感動」を重視するあまり、本来伝えるべきメッセージが薄まってしまうケースも少なくありません。
キャラクターのデザインや世界観がターゲット層の感性と合っていなければ、「何となく違和感がある」と思われ、途中離脱や読まれずに終わるリスクもあります。
こうした失敗を防ぐためには、制作前のターゲット分析とコンセプト設計が欠かせません。狙う読者像を明確にしたうえで、その感性や価値観に合う表現を選ぶことが、成果につながるマンガ広告を制作するポイントです。
マンガ広告が効果を発揮しやすい商材とは?
マンガ広告はあらゆる業種で活用可能ですが、特に「感情を動かしやすい商材」や「ストーリー化しやすい商材」との相性が抜群です。導入効果を最大化するには、商材の特性とマンガ広告の強みが噛み合っているかどうかを見極めることが重要です。
以下のような条件を満たす商材は、マンガ広告との親和性が高く、成果につながりやすくなります。
| 商材タイプ | 特徴 | 具体例 |
| 課題解決のストーリーを描きやすい | 問題提起から解決までを物語化しやすい | コンプレックス解消、美容、健康、転職支援、資格取得、学習教材 |
| 感情移入を誘いやすいジャンル | 読者の感情を動かすテーマが多い | 恋愛相談、カウンセリング、育児・子育て、ペット関連 |
| メリットを文章だけで伝えにくい | 複雑な仕組みや体験ベースの価値を説明しやすい | BtoBサービス、SaaSツール、人材紹介、コンサルティング、保険商品 |
| SNSユーザーとの親和性が高い | 若年層や拡散狙いの案件に強い | 若年層向けサブスクリプション、アパレル、アプリ、エンタメ、VTuber関連 |
マンガ広告は感情と論理を同時に動かす力を持っているため、「読むだけで納得できる」「自分に置き換えてイメージできる」といった腹落ちの体験を届けたい商品・サービスに適しています。
ターゲットがSNSやWebに慣れている場合、広告に対する拒否感も少なく、マンガという親しみある形式で自然に受け入れられるため、読了率やエンゲージメントが高まる傾向があります。
マンガ広告の費用相場と制作の流れ
マンガ広告を導入する際には、費用の相場と制作工程の全体像をあらかじめ把握しておくことが重要です。制作方法には大きく分けて「自作」と「外注」がありますが、それぞれにかかるコストや進行手順は大きく異なります。ここでは、費用の目安と制作の流れを詳しく解説します。
制作費の相場
マンガ広告の制作費用は、内容のボリューム・カラーの有無・制作形態などによって幅広く変動します。一般的な費用の相場は、以下の通りです。
| 形式・内容 | 制作費の目安 | 特徴・用途例 |
| 4コマ~1ページ静止画(モノクロ) | 5万〜15万円程度/本 | SNS、LP、パンフレットによく使われる・シンプルな商品紹介など |
| 4コマ~1ページ静止画(フルカラー) | 7万〜20万円程度/本 | SNS拡散・印象訴求/広告色を抑えたストーリー向き |
| 複数ページ/ストーリーマンガ | 20万〜50万円(8〜16P等) | 詳細説明やサクセスストーリー・事例解説、BtoBホワイトペーパー等 |
| アニメーション化/動画マンガ | 30万〜100万円超 | SNS動画やYouTube、TVCM向けの場合あり(尺や演出で大きく変動) |
料金は、コマ数やカラーの有無、使用目的、作家の実績などにより変動します。また、シナリオ構成やマーケティング視点のコンサルティングが含まれる場合、追加費用が発生することもあります。
事前に見積もり項目を明確にし、目的に対して適切なボリューム・形式を選ぶことが予算管理のポイントです。
自作する場合の制作の流れ
マンガ広告を自作する場合は、「広告」と「漫画」の両方の知識と技術が求められます。制作の一般的な流れは以下の通りです。
- 企画構成(目的・ターゲットの設定)
- ネーム作成(コマ割り・セリフ構成)
- 作画(キャラクターデザイン・背景・仕上げ)
- 配信設計(媒体ごとのサイズ・形式調整)
IllustratorやCLIP STUDIO PAINTなどの作画ソフト、AI生成ツールを使えば一定レベルの制作は可能です。しかし、マーケティング視点の欠如や品質不足がリスクとなる可能性があります。広告効果を出すためには、ただ描くだけでなく「伝える力」が問われます。
外注する場合の制作の流れ
外注の場合は、プロの制作会社に委託することで品質・効果の両立が期待できます。一般的な制作の流れは、以下の通りです。
- 初回ヒアリング(商材・目的の共有)
- シナリオ作成(構成・セリフの設計)
- ラフ・ネーム作成(構成確認)
- 作画〜仕上げ(イラスト制作・修正対応)
- 納品・配信(媒体に最適化したデータ提供)
制作会社によっては、SNS広告やLPとの連携提案、配信・運用まで一括で対応可能なプランもあります。ラフ段階での確認や中間チェックの有無によって、完成物の精度や修正工数が大きく変わるため、契約前に進行フローを細かく確認することが重要です。
マンガ広告の制作会社選び
マンガ広告を外注する際、制作会社の選定は成果を大きく左右します。ただ絵が上手なだけでは効果的な広告にはならず、戦略設計・提案力・実績など、多面的な観点から判断することが重要です。このセクションでは、信頼できる制作会社を選ぶための具体的なチェックポイントを解説します。
信頼できる会社の見極め方
制作会社選びでは、業界理解と広告経験のバランスが取れているかが重要な判断材料になります。特に注目すべき点は以下の通りです。
- 実績数と対応領域の広さ:過去に制作した業種や媒体の種類が多いか
- 初回ヒアリングの深さ:商材への理解を深めようとする姿勢があるか
- スピード感と柔軟性:レスポンスやスケジュール調整に対応力があるか
また、担当者が戦略的な視点を持って説明しているかどうかも確認ポイントです。制作工程の説明だけで終わる会社は、単なる制作代行になりがちです。
実績・事例の確認ポイント
制作会社のWebサイトに掲載されている過去事例や成果報告の質と内容を確認しましょう。以下の観点でチェックすると判断がしやすくなります。
- 自社と同業・同規模のクライアント事例があるか
- 商材別・目的別に整理された事例があるか(例:CV向上/SNS拡散)
- 効果が数値で示されているか
事例がサイトに載っていない場合でも、問い合わせ時に「近い業種の事例を見せてほしい」と依頼すれば、対応力や提案力が見えてきます。実績は品質の証明ですが、それを再現できるかどうかがより重要です。
ヒアリング力や提案力がある制作会社がおすすめ
最終的な成果は、「制作会社の提案力」に大きく依存します。以下のような点に注目してください。
- 商材の強みや弱みを的確に把握しているか
- ペルソナに基づいたストーリー設計を提案してくれるか
- 広告としての導線設計まで含めてアドバイスがあるか
単に「絵を描いて納品する」という対応ではなく、「どうすれば効果的な広告になるか」を共に考えてくれる姿勢があるかどうかが、制作パートナーとして信頼できるかの分かれ目です。
マンガ広告の成功事例と活用シーン
マンガ広告は、SNSマーケティングからBtoB営業資料まで、幅広いシーンで成果を上げています。ここでは、実際に話題となった事例や、目的別に効果を発揮した具体的な活用パターンを紹介します。自社での導入を検討する際の、参考にしてください。
バズを生んだ話題性のある事例
SNS上で拡散されたマンガ広告の多くは、「あるあるネタ」や「共感ストーリー」を軸に構成されています。たとえば、日常の悩みをユーモアと感動を交えて描き、商品やサービスが“救世主”のように登場するパターンは、自然な導入と拡散性を両立させます。
こうした事例に共通するのは、広告らしさを抑えた「読み物」としての完成度の高さです。読者に「つい最後まで読んでしまった」と思わせる構成力が鍵となります。
花王「バブ for SKIN」×「耐え子の日常」コラボ
花王の入浴剤「バブ for SKIN」とフォロワー60万人超の人気マンガ「耐え子の日常」がコラボ。商品訴求を“あるあるネタ”とストーリーに乗せて自然に拡散され、ユーザーから「最後まで読んでしまった」と共感を呼びました。
参考:花王バブ公式X「#耐え子の日常 × #バブforSKIN」
キリンレモンの連作マンガプロモーション
複数の人気漫画家が実体験を元に描く連作プロモーションマンガを、それぞれのSNSアカウントから発信。体験談を活かしたストーリーで広告色が薄く、ターゲット層への訴求力と拡散力が大きく向上しました。
BtoBでの活用事例
BtoB領域では、複雑なサービス内容を視覚的にわかりやすく伝えるツールとしてマンガ広告が活用されています。特に、ITサービスやSaaS、コンサルティング業などはその効果が顕著です。
専門的な内容をストーリーに落とし込むことで、初回接点の心理的ハードルを下げる効果があります。営業支援ツールや資料としても汎用性が高く、多角的な活用が可能です。
WealthPark Business「不動産DX導入マンガ」
不動産DXプラットフォームを展開するWealthParkは、管理会社の日常業務課題やDX導入ストーリーをマンガ化し、ホワイトペーパーやWebで公開しました。専門用語が多い分野でもマンガによってわかりやすくなり、資料ダウンロード数増加へ効果が見られました。
参考:WealthPark Business「マンガでわかる!オーナーアプリで不動産管理DXへの道」
AWS(アマゾンウェブサービス)「学習コンテンツ紹介マンガ」
クラウドサービスやIT製品の導入企業向けに、複雑なクラウド学習内容をストーリー漫画で解説しています。技術知識が乏しい層にも受け入れられやすく、人気を集めました。研修、資料サイト、SNSでマンガを活用しています。
参考:AWS マンガシリーズ
企業と個人クリエイターのタイアップ事例
マンガ広告は、企業だけでなく個人クリエイターやVTuberにも有効なPR手法として活用されています。自身のキャラクターを使って、活動やグッズ、イベントなどをストーリー形式で紹介することで、ファンとのエンゲージメントを高めることができます。
こうしたマンガは、「内輪ネタ」を効果的に活かすことでファン心理を刺激し、広告色を薄めながらもしっかりとメッセージを届けています。
カエルDX×QUICPayコラボマンガ
人気漫画家カエルDXがQUICPayの利用体験を題材にPRマンガを制作。
ユーモアと実体験を活かした構成でSNS上で大きな共感を集め、自然な拡散に成功しました。
Paidy(ペイディ)×漫画家タイアップ
後払い決済サービスPaidyが複数の漫画家と協業し、サービスの利便性をストーリーマンガで紹介。ユーザー目線での描写が好評を呼び、SNS上で高いエンゲージメントを獲得しました。
マンガ広告で成果を出すための運用ポイント
マンガ広告は、制作しただけでは最大の効果を発揮できません。配信設計・導線構築・改善サイクルを組み合わせることで、初めて本来のポテンシャルを引き出せます。ここでは、成果につながる4つの運用ポイントを解説します。
コンセプト設計を明確にする
マンガ広告の成功は、初期段階でのコンセプト設計にかかっています。「誰に」「何を」「どう伝えるか」を明確にしなければ、読み手の心に届かない可能性があります。
キャラクター設定やストーリー展開に一貫性を持たせることで、読者の信頼感と没入感が高まり、広告効果も向上します。面白さや演出にばかり注力すると、本来のメッセージが薄れてしまうため、伝えたい情報とのバランス設計が求められます。
効果的な広告配信先を選定する
優れたコンテンツでも、配信先が適切でなければ効果は限定的になってしまいます。マンガ広告はSNSとの相性が良いため、商材に応じて最適なチャネルを選ぶことが重要です。
- XやInstagram:拡散力重視・若年層ターゲット
- YouTube Shorts・TikTok:動画化して視聴誘導
- 自社サイト・LP:読み込みコンテンツとしてCV誘導
配信時間帯や曜日なども検証し、エンゲージメントが高まる条件を見つけて継続運用することで、広告効果を安定して向上させられます。
制作段階で引き込み力を高める工夫をする
制作段階での工夫も、広告のパフォーマンスを大きく左右します。以下のようなポイントを意識することで、読者の引き込み力を強化できます。
- 1コマ目で「共感」または「驚き」を入れることで、続きを読みたくさせる
- 視線誘導を意識したコマ構成(右下への自然な流れ)を設計する
- 吹き出しの文字数を減らし、テンポの良い読了体験を作る
- フォント・余白・色使いで可読性を高める
こうした細かな工夫が、読者のストレスを軽減し、広告としての完読率や拡散性を向上させます。
PDCAで継続的に改善する
マンガ広告も他の広告施策と同様、一度作って終わりではなく、運用・分析・改善が不可欠です。特にSNS配信では反応データを取得しやすいため、各種数値をもとにした改善がしやすいメリットがあります。
- ABテストによるタイトル・1コマ目の差し替え
- キャラクターの表情やセリフの微調整
- 最終CTA(行動喚起)の配置と表現見直し
これらを定期的に見直すことで、広告コンテンツとしての精度と持続的な成果を両立できます。
このように「戦略設計 → 適切な配信 → 制作工夫 → 改善サイクル」を組み合わせることで、マンガ広告は単なる話題作りではなく、長期的な成果を生むマーケティング資産へと成長するでしょう。
マンガ広告によくある質問
最後にマンガ広告によくある質問をまとめます。
マンガ広告はどれくらいの期間で制作できる?
制作期間は、企画内容と制作体制によって異なります。既にシナリオや構成が固まっている場合、短納期でも対応可能です。
- シナリオありの場合:最短で1〜2週間程度
- ゼロから制作する場合:通常は3〜5週間が目安
制作の進行状況や修正回数によって前後するため、事前にスケジュール感を制作側と共有しておくことが大切です。また、余裕を持った進行により、品質と成果を両立しやすくなります。
「うざくない」マンガ広告にするにはどうすればいい?
「うざい」と感じさせないためには、ストーリー性と誠実さを重視することが最も有効です。制作の際には、以下の点に注意してください。
- 宣伝要素を前面に出さず、物語の中で自然に商品を紹介する
- キャラクターのセリフや展開を読者の共感を得られる内容する
- 無理なオチや誇張表現を避け、読後感を良くする構成に仕上げる
「読んで良かった」と思わせる体験を提供できれば、広告感は緩和され、シェアされやすい魅力的なコンテンツになります。
マンガ広告と通常広告はどちらが効果的?
どちらが効果的かは目的と商材によって異なります。それぞれに適した活用シーンを理解して選択しましょう。
- マンガ広告:ストーリーによる理解促進・共感形成・SNS拡散が得意
- 通常広告(バナー・テキスト):短期的なクリック誘導・認知拡大に適している
マンガ広告と通常の広告を組み合わせて活用することで、瞬発力と持続力のバランスが取れた広告設計が可能になります。例えばバナー広告で注目を集め、クリック先にマンガ広告LPを用意する導線設計などが効果的です。
まとめ:マンガ広告を理解してプロモーション戦略に活かそう
マンガ広告は、感情と論理の両面から訴求できる希少な広告手法です。従来の広告に飽きたユーザーの関心を引き、物語として自然に情報を届けることで、商品やサービスへの理解と共感を深めることができます。
特にWeb広告やSNSマーケティングとの親和性が高く、「目に留まりにくい」「クリックされない」といった課題を抱える企業やクリエイターにとって、新たな突破口となる可能性があります。
ただし、成果を出すには適切な設計とパートナー選び、継続的な改善が欠かせません。表現の自由度が高いからこそ、狙いとストーリーの軸を明確にすることが重要です。
自社のターゲットや目的に合わせて最適な形で活用し、広告の新しい可能性として、ぜひマンガ広告を戦略の一つに組み込んでみてください。