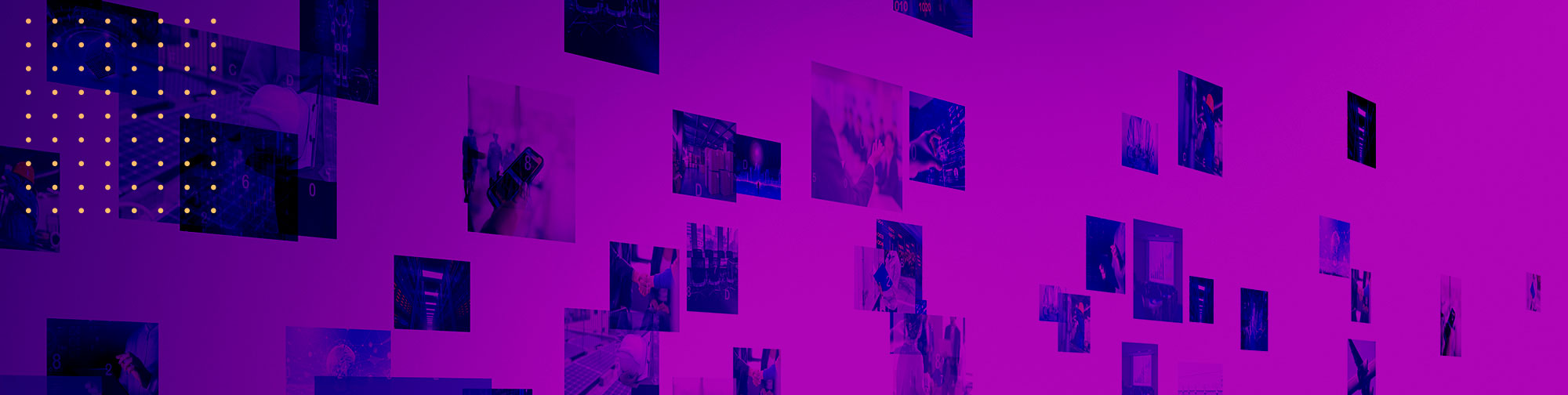記事一覧

IPコラボとは?成功事例や費用・メリットについて徹底解説!
IPコラボを検討したいけれど、「IPコラボレーションとは何か」「具体的な実施方法」「費用や法的注意点」などがわからず、なかなか踏み出せずにいませんか? IPコラボを適切に実施することで、新規顧客層の獲得やブランドイメージの向上、話題性の創出といった大きな効果を得ることができます。
この記事では、IPコラボの基本概念から成功事例、実施方法、費用の内訳、成功の秘訣まで詳しく解説します。この記事を読んで、IPコラボの全体像を把握し、自社に最適なコラボレーション戦略を見つけてください。
この記事のまとめ
- IPコラボは異なるIPを組み合わせて新商品を開発する手法
- 新規顧客獲得、ブランド向上、話題性創出の効果が期待できる
- アニメ・ゲーム・キャラ・VTuberなど多様な種類が存在する
- 費用は数百万~数千万円、ライセンス料の占める割合が大きい
- 成功には適切なIP選定と魅力的な企画設計が必要

🎥 VTuberの制作・運用ならデジタルギア
Vtuberのキャラデザから3Dアバターの制作まで一気通貫で対応
自治体やVtuber事務所など実績多数
まずはプロに相談してみませんか?
おすすめ記事
目次
IPコラボとは?
IPコラボとは、異なる企業や組織が保有する知的財産(Intellectual Property)を組み合わせて、新たな商品やサービス、コンテンツ、イベントなどを共同で企画・開発・展開することです。
アニメ、ゲーム、キャラクター、ブランドなどの知的財産を活用し、相互のファンベースを拡大させる効果的なマーケティング手法として、近年多くの業界で注目を集めています。
IPコラボの意味
IPコラボとは、IP(Intellectual Property=知的財産)を活用したコラボレーションを指し、2つ以上の異なる知的財産権を持つ企業や団体が協力し、共同で商品開発、販促活動、イベント開催、コンテンツ制作など様々な事業を行うビジネス手法です。
例えば、人気アニメキャラクターと食品メーカーがコラボレーションし、限定パッケージの商品を販売したり、ゲームタイトルと他業界のブランドが提携してオリジナルグッズを制作したりすることが挙げられます。このような取り組みにより、両者の持つIPの価値を最大限に活用し、新しい市場の開拓や既存ファンの満足度向上を図ることができます。
IPコラボが注目される理由
IPコラボは、異なる企業や組織が持つ知的財産(IP)を組み合わせることで、単独では生み出せない価値を創出する手法として注目を集めています。消費者のニーズが多様化し、情報が溢れる現代において、IPコラボは効果的なマーケティング戦略として多くの業界で採用されるようになりました。特に若年層をターゲットとしたマーケティングでは、欠かせない手法のひとつとなっています。
では、なぜこれほど多くの企業がIPコラボに注目しているのでしょうか。その主な理由は以下の3点に集約されます。
ファンベースの相互拡大
異なるIPのファン層が交わることで、双方が新規顧客を自然に獲得できます。例えばゲームとファッションのコラボでは、普段ファッションに興味のないゲームファンが新たな顧客となり、ファッション愛好者もゲームに興味を持ちます。このクロスオーバー効果は、従来の広告では届きにくかった層へのアプローチを可能にし、既存ファンのロイヤルティ強化も期待できます。
高いコストパフォーマンス
両者のブランド力を掛け合わせることで、単独展開よりも効率的なプロモーションが実現します。相手方ブランドへの信頼や愛着が転移しやすく、認知から購買までの障壁が低くなる傾向があります。
特にSNS時代には、意外性のあるコラボが「バズる」現象により、広告費をかけずとも自然拡散の力で大きなリーチを獲得できます。メディア露出の増加やPR効果も含め、投資対効果の高いマーケティングが可能です。
限定性によるセールス効果
期間・数量限定という特性が生み出す希少価値は、「今しか手に入らない」という心理を刺激し、即座の購買決定を促進します。この「入手困難感」が更なる欲求を生み、特にコレクター気質の強いファンは通常より高い価格でも購入する傾向があります。
限定商品の人気が話題となり、注目度が高まることでブランド価値が再認識されることもありますが、二次流通市場での意図しない価格高騰はブランドイメージへの影響も考慮し、慎重な販売戦略が求められます。
IPコラボのメリット
IPコラボレーションは、参加する企業や組織にとって様々なメリットをもたらします。特に新規顧客の獲得、ブランドイメージの向上、話題性の創出という3つの主要なメリットが挙げられ、投資対効果の高いマーケティング戦略として多くの企業が活用しています。
新規顧客層へのアプローチ
IPコラボの主要なメリットの一つは、従来のターゲット層とは異なる新規顧客にアプローチできることです。例えば、アニメキャラクターと化粧品ブランドのコラボレーションでは、アニメファンが化粧品に興味を持つきっかけとなり、逆に化粧品愛用者がそのアニメ作品を知るきっかけにもなります。
このように、双方のファンベースが交わることで、自然な形で顧客層の拡大が図れます。また、既存顧客にとっても新鮮な驚きを提供でき、ブランドロイヤルティの向上にも寄与します。
ブランドイメージの向上
IPコラボにより、自社ブランドに新たな魅力や価値観を付加することができます。市場から高い評価を受けているIPとのコラボレーションは、相手方のブランド力を借りることで自社のブランド価値や信頼性の向上につながります。
特に若年層をターゲットとしたい場合、人気のアニメやゲームとのコラボレーションは効果的です。硬いイメージの企業でも、親しみやすいキャラクターとのコラボにより、より身近で愛されるブランドとして認知されるようになります。
話題性の創出と拡散
IPコラボは高い話題性を生み出し、SNSを中心とした口コミ効果が期待できます。ファンの間での「推し」への愛情は非常に強く、コラボ商品の発表は大きな話題となります。TwitterやInstagramでの拡散により、広告費を大きく投下せずとも大きなリーチを獲得することが可能です。
また、メディアにも取り上げられやすく、PR効果も期待できます。意外性のあるコラボレーションほど注目度が高く、ニュース価値としても魅力的です。このような自然発生的な拡散により、コストパフォーマンスの高いプロモーションが実現できます。
IPコラボの主な種類
IPコラボには様々な種類があり、それぞれ異なる特徴やターゲット層を持っています。主要なものとしてアニメ・漫画、ゲーム、キャラクター、VTuberとのコラボレーションが挙げられます。これらの種類を理解することで、自社に最適なコラボパートナーの選択が可能になります。
アニメ・漫画コラボ
アニメや漫画とのコラボレーションは、日本のポップカルチャーの代表的なIPコラボの形態です。
人気アニメ作品のキャラクターやストーリー要素を活用し、商品パッケージのデザインや限定グッズの制作などを行います。例えば、コンビニエンスストアの一番くじや飲料メーカーとのタイアップなどが挙げられます。
アニメファンの熱狂的な購買行動により、短期間での売上向上が期待でき、SNSでの話題性も非常に高いのが特徴です。また、海外展開を視野に入れた場合、日本のアニメコンテンツは世界的に認知度が高く、グローバル展開の足がかりとしても有効です。
ゲームコラボ
ゲームとのコラボレーションは、デジタルとリアルの両方で展開される多様な形態があります。
モバイルゲームとのコラボでは、ゲーム内でのコラボイベントや限定キャラクターの提供、リアル商品の購入特典としてゲーム内アイテムを配布するなどの手法があります。また、eスポーツタイトルとのコラボにより、若い世代への訴求力を高めることができます。
近年はゲーム実況やストリーミング文化の発展により、ゲームコラボの拡散力はより一層高まっています。ゲーマーコミュニティの結束力は強く、口コミ効果による購買促進も期待できます。
キャラクターコラボ
既存のマスコットキャラクターや企業キャラクターとのコラボは、親しみやすさを重視した戦略です。
ハローキティやシナモロールといったサンリオのキャラクター、リラックマ、ディズニーキャラクター、ポケモンなどとのコラボは、幅広い年齢層に愛されています。これらのキャラクターは長年にわたってファンに愛され続けており、安定した集客力を持っています。
また、地域のゆるキャラや企業オリジナルキャラクターとのコラボにより、地域密着型のマーケティングも可能です。キャラクターが持つ世界観やストーリーを活用することで、商品に物語性を付加し、消費者の感情に訴えかけることができます。
VTuberコラボ
VTuber(バーチャルYouTuber)とのコラボは、新しい形のIPコラボとして急速に注目を集めています。
VTuberファンの熱量は非常に高く、グッズ購入やイベント参加に積極的です。また、配信での商品紹介やレビューにより、リアルタイムでの拡散効果も期待できます。配信プラットフォームでの視聴者との双方向コミュニケーションにより、ファンとの距離が近いのも特徴です。
企業系VTuberとのコラボでは、ブランドイメージに合った適切なキャラクター設定により、より自然な形での商品訴求が可能です。また、海外のVTuberファンも多く、グローバル展開の可能性も秘めています。
IPコラボの成功事例
IPコラボには数多くの成功事例がありますが、特に話題性と売上効果を両立させた代表的な事例をご紹介します。これらの事例から学ぶことで、自社のIPコラボ戦略の参考にできます。各事例の成功要因を詳しく分析し、IPコラボの可能性を探っていきましょう。
【アニメ】ユニクロ × アニメキャラクター
ユニクロのTシャツブランド「UT」は、アニメキャラクターとのコラボで数々の成功を収めています。ワンピース、ドラゴンボール、鬼滅の刃、エヴァンゲリオンなど、幅広い人気アニメとコラボしており、多くが1,500円〜1.990円(税込)を中心とした手頃な価格帯で展開しています。
成功の要因は、グローバル展開を視野に入れた戦略的なIP選定にあります。「ワンピース25周年記念コラボ」では、ルフィの冒険の軌跡を描いた全8種類のTシャツを展開し、世界最大のファンイベントとのグローバルパートナーシップも締結しました。
また、過去の人気デザインを「UT ARCHIVE」として再販する戦略により、新規ファンと既存ファンの両方に訴求することに成功しています。デザインの質の高さと、アニメの象徴的なシーンを的確に表現することで、ファンの心を掴んでいます。
【ゲーム】信州渋温泉 × モンスターハンター
2010年から2011年にかけて実施された「モンスターハンターポータブル 3rd × 信州渋温泉 ユクモノ気分で狩り放題!」は、ゲームIPとリアルな地域をコラボさせた先駆的な事例です。
渋温泉は、ゲームの舞台「ユクモ村」との共通点(和風の温泉地、古い建物、北国の立地)を活かし、温泉街全体をゲームの世界観で装飾しました。9つの温泉を巡る「九頭巡りスタンプラリークエスト」や、電源完備のリアル集会所の設置、限定グッズとして半年がかりで育てたアイルーデザインのリンゴなど、徹底した世界観の再現が話題となりました。
長野電鉄では「モンハン特急ゆけむり号」を運行し、ホームではゲームのBGMを流すなど、交通機関も巻き込んだ大規模なコラボレーションとなり、地域活性化の模範事例として注目されています。
【キャラクター】サンリオ × ちいかわ
2022年11月頃から展開されたサンリオキャラクターズと「ちいかわ」のコラボレーションは、異なるキャラクターIP同士の成功例として大きな注目を集めました。「ちいかわたちがサンリオキャラクターズの世界観を楽しむ」というコンセプトのもと、特別な描き下ろしデザインで多数のアイテムが展開されました。
ちいかわたちがサンリオキャラクターズのアイテムを身につけたり、一緒にお菓子を囲んだりする可愛らしいデザインは、両方のファンが楽しめる世界観を構築しました。サンリオピューロランドではスペシャルコラボイベントも開催され、限定グッズの販売やグリーティングなどを通じてリアルイベントとの連動による相乗効果を創出しました。
翌2023年にも新たな商品シリーズが展開されるなど、継続的なコラボレーションとして発展し、両IPのファンベース拡大に貢献しています。
【VTuber】ローソン × にじさんじ
ローソンとにじさんじのコラボは、VTuberとコンビニエンスストアという新しい組み合わせで注目を集めています。過去のキャンペーンでは、対象商品を購入することでオリジナルグッズ(クリアファイル、ミニポスターなど)をプレゼントする企画が人気を博しました。
人気VTuber(例えば、弦月藤士郎、長尾景、甲斐田晴からなるユニット「VΔLZ」など)が特別に描き下ろされたイラストでデザインされたグッズは、複数のテーマ(例:季節の装い、特別な衣装など)で展開されることもあり、ファンの間で「争奪戦」と呼ばれるほどの人気となることも少なくありません。
にじさんじファンは男女を問わず若年層を中心に幅広く、ソーシャルメディアを積極的に活用するため、キャンペーンの露出増加と自然な拡散効果を生み出しています。過去には2020年からコラボを開始し、Ponta会員限定グッズやオリジナルチョコの販売など、継続的な関係を築いています。
IPコラボの費用と内訳
IPコラボの費用は、協力するIPの知名度、コラボの規模、展開方法によって大きく異なります。一般的には数百万円から数千万円規模となることが多く、大型案件では億単位になる場合もあります。費用の主要な内訳を理解することで、適切な予算計画を立てることができます。
| 費用項目 | 割合目安 | 具体的な内容 |
|---|---|---|
| ライセンス料 | 30〜50% | IP使用料、保証金、売上ロイヤリティ |
| 制作・開発費用 | 25〜35% | デザイン制作、商品開発、品質管理 |
| プロモーション・広告費 | 15〜25% | Web広告、SNS運用、イベント開催 |
| その他の付随費用 | 5〜15% | 契約関連費用、コンサルティング料 |
※上記の割合目安は一般的なケースであり、コラボレーションの具体的な内容や契約条件によって大きく変動します。
ライセンス料
ライセンス料は、IPコラボにおける最大の費用項目の一つです。基本的なライセンス料として初期費用(保証金)が必要で、これはIPの知名度や期間によって数百万円から数千万円の幅があります。また、売上に応じたロイヤリティ(通常売上の3〜10%)も発生します。
人気の高いIPほど高額になる傾向があり、アニメやゲームの場合は放送・配信時期や話題性によって価格が変動することもあります。契約期間や使用範囲(商品種類、販売地域など)によっても金額が決まるため、事前の詳細な交渉が重要です。
制作・開発費用
コラボ商品の制作・開発には、デザイン制作から製造まで様々な費用が含まれます。キャラクターデザインの監修やオリジナルイラストの制作、パッケージデザインなどのグラフィック制作費が必要です。また、新商品や限定商品の開発・製造には、通常商品よりも高い費用がかかることが多くあります。
品質管理やキャラクター使用に関する厳格なチェック工程も必要で、これらの監修費用も計上する必要があります。特にフィギュアやアパレルなどの立体物では、原型制作や金型作成など、初期投資が大きくなる傾向があります。
プロモーション・広告費
IPコラボの成功には効果的なプロモーション戦略が不可欠です。デジタル広告では、TwitterやInstagramなどのSNS広告、YouTubeでの動画広告、ファン向けの専門サイトでのバナー広告などが含まれます。また、インフルエンサーやVTuberを起用したPR企画も一般的です。
オフラインでは、イベント開催費用、ポップアップストアの運営費、サンプリングキャンペーンなどが必要です。特にコラボ発表時の話題作りは重要で、記者発表会やファンイベントの開催により、メディア露出とファンの関心を高めることができます。
その他の付随費用
IPコラボには、直接的な制作費以外にも様々な付随費用が発生します。法務関連では、契約書作成・レビュー費用、知的財産権の調査費用、必要に応じて弁護士への相談料などがかかります。また、コラボ企画の戦略立案やIP選定のためのコンサルティング料も重要な費用項目です。
プロジェクト管理費用、撮影・取材費用、翻訳費用(海外展開の場合)、保険料なども含まれます。これらの費用は、主要な費用項目と比較すると全体の予算に対して小さな割合となることもありますが、プロジェクトの円滑な進行には欠かせない要素です。
IPコラボ実施までの具体的ステップ
IPコラボを成功させるためには、計画的なステップを踏むことが重要です。目的の明確化から効果測定まで、7つの段階を経て進めることで、リスクを最小化し、成果を最大化できます。各段階での注意点やポイントを押さえて、戦略的にコラボレーションを実施しましょう。
1. コラボ目的とターゲットの明確化
IPコラボの成功には、明確な目的設定とターゲット顧客の特定が欠かせません。まず、売上向上、ブランド認知度アップ、新規顧客獲得など、コラボレーションの主要目的を決定します。次に、現在の顧客層を分析し、IPコラボによって獲得したい新しいターゲット層を特定します。
例えば、30代女性向けの化粧品ブランドが20代のアニメファンにもアプローチしたい場合、その橋渡しとなるIPを選ぶ必要があります。KPI(重要業績評価指標)も事前に設定し、成果の測定基準を明確にしておくことが重要です。
2. リサーチ・適切なIP選定
目的とターゲットに合致するIPを選定するため、徹底的なリサーチを行います。対象となるIPの人気度、ファン層の属性、過去のコラボ実績、ブランドイメージなどを調査します。また、同業他社のIPコラボ事例を分析し、成功要因や失敗要因を把握することも大切です。
IP選定では、自社ブランドとの親和性、ターゲット層の重複度、話題性、権利関係の複雑さなどを総合的に判断します。複数の候補IPをリストアップし、優先順位をつけて交渉に臨むことをお勧めします。
3. ライセンサーとの交渉・契約
選定したIPの権利者(ライセンサー)との交渉・契約プロセスに入ります。初期接触では、コラボの概要、想定する商品・サービス、販売規模、期間などを提示し、相手方の反応を確認します。ライセンス料の交渉では、保証金、ロイヤリティ率、最低保証金額などの条件を詰めます。
契約書には、使用範囲、期間、販売地域、品質基準、デザイン承認プロセス、売上報告義務などを明記します。知的財産権に関する専門知識が必要なため、経験豊富な弁護士への相談を強く推奨します。
4. 商品・コンテンツの制作
契約締結後、実際の商品やコンテンツの制作フェーズに移ります。デザイン制作では、IPの世界観を尊重しつつ、自社ブランドとの調和を図ります。ライセンサーの承認プロセスが厳格な場合が多いため、スケジュールには余裕を持って取り組みます。
製造段階では、品質管理を徹底し、IPの価値を損なわないよう注意します。パッケージデザイン、製品仕様、取扱説明書なども含めて、総合的に監修を受ける必要があります。プロトタイプでの事前確認により、後戻りを防ぐことができます。
5. 販売・プロモーションの計画
効果的な販売・プロモーション戦略を立案し、実行に移します。販売チャネルの選定では、ECサイト、実店舗、イベント会場など、ターゲット顧客にリーチしやすい場所を選びます。プロモーション計画では、SNS戦略、インフルエンサー活用、イベント開催、メディア露出などを組み合わせます。
発売前のティザー展開により期待感を高め、発売時の話題最大化を図ります。ファンコミュニティとの連携や、限定感を演出する施策も重要です。予算配分と実施タイミングを詳細に計画し、効率的なプロモーションを実現します。
6. コラボ実施・運用
計画に基づいてコラボレーションを実施し、適切な運用管理を行います。発売開始後は、販売状況、在庫管理、顧客反応をリアルタイムで監視します。SNSでの反響や口コミの分析により、必要に応じてプロモーション戦略を調整します。
想定以上の人気が出た場合の増産対応や、逆に売れ行きが芳しくない場合の追加施策も準備しておきます。ライセンサーとの定期的な情報共有により、関係性を維持し、トラブルの早期解決を図ります。
7. 効果測定・分析
コラボレーション終了後、包括的な効果測定と分析を実施します。売上実績、新規顧客獲得数、ブランド認知度の変化、SNSでのエンゲージメントなど、事前に設定したKPIに基づいて成果を評価します。コスト対効果の分析により、投資回収率(ROI)を算出します。
成功要因と改善点を詳細に分析し、次回のIPコラボに活かすためのナレッジとして蓄積します。ライセンサーとも成果を共有し、今後の関係性構築につなげることで、継続的なパートナーシップの基盤を築くことができます。
IPコラボ成功の秘訣
IPコラボの成功は偶然ではなく、戦略的な計画と実行によって実現されます。明確な目的設定、適切なIP選定、魅力的な企画設計という3つの要素が成功の鍵を握っています。これらの秘訣を理解し実践することで、投資対効果の高いコラボレーションを実現できます。
明確な目的と戦略
IPコラボの成功には、曖昧さを排除した明確な目的設定が不可欠です。「話題性を高めたい」といった漠然とした目標ではなく、「20代女性の新規顧客を月間1000人獲得する」のような具体的な数値目標を設定します。また、短期的な売上向上だけでなく、中長期的なブランド価値向上やファンベース拡大も視野に入れた戦略が重要です。
目的達成のための具体的なアクションプランを策定し、各段階でのマイルストーンを設定することで、プロジェクトの進捗を適切に管理できます。また、想定される課題やリスクを事前に洗い出し、対応策を準備しておくことで、トラブル発生時の迅速な対応が可能になります。
相乗効果を生むIP選定
成功するIPコラボでは、単なる知名度だけでなく、相乗効果を生み出せるIPを選ぶことが重要です。自社のターゲット層とIPのファン層を分析し、重複する部分と新規開拓可能な部分を明確にします。また、ブランドイメージの親和性も重要で、高級ブランドとカジュアルなキャラクターの組み合わせは慎重に検討する必要があります。
過去のコラボ実績や活動頻度も選定基準の一つです。コラボを頻繁に行っているIPは慣れている反面、希少性が薄れる可能性もあります。タイミングも重要で、アニメの放送時期やゲームの大型アップデート時期などを狙うことで、より大きな注目を集めることができます。
IPの魅力を引き出す企画設計
IPコラボの真価は、企画の独創性と実行力にかかっています。単純にキャラクターをパッケージに印刷するだけでなく、そのIPの世界観やストーリーを商品体験に組み込みます。例えば、アニメの名シーンを再現できるギミックを商品に搭載したり、キャラクターの設定と関連する機能を持たせたりすることで、ファンの心に深く響く商品が生まれます。
限定性や収集要素を取り入れることも効果的です。シリーズ化やランダム要素、購入特典などにより、継続的な購買意欲を喚起できます。また、SNSでの拡散を狙った「映える」要素や、ファン同士の交流を促すコミュニティ機能なども現代のコラボには欠かせません。
IPコラボに関するよくある質問
Q1. どのような企業がIPコラボを活用していますか?
A. 大手メーカーやアパレル、飲料、日用品、小売業など幅広い業種で活用されています。また、最近では地方自治体や伝統工芸品など、ユニークな分野でも活用が広がっており、中小企業でも成功事例が増えています。
Q2. 中小企業でもIPコラボは可能ですか?
A. 中小企業でもIPコラボは十分に可能です。大手IPとのコラボレーションは費用面で難しい場合もありますが、地域に根ざしたIPや、ニッチなファン層を持つIPとの連携であれば、比較的取り組みやすいことがあります。また、近年注目されているVTuberやインフルエンサーとのコラボレーションも、中小企業にとっては有効な手段となり得ます。
Q3. IPコラボで注意すべき点はありますか?
A. IPコラボでは、契約内容や権利関係を明確にすることが非常に重要です。特に、知的財産権の取り扱いや責任範囲、収益分配などについては、事前にしっかりと協議し、書面で合意しておく必要があります。また、コラボレーションするIPのイメージを損なわないよう、品質管理や表現方法にも注意が必要です。
Q4. VTuberとのIPコラボは通常のキャラクターと何が違いますか?
A. VTuberとのコラボは、従来のキャラクターとは大きく異なる特徴があります。最大の違いは、リアルタイムでのコミュニケーションが可能な点です。VTuberは配信中に商品を実際に使用したり、ファンと直接やり取りをしながらPRできるため、より親密で自然なマーケティングが可能です。また、VTuberは通常のキャラクターと違い、人格や個性が強く表現されるため、コラボ内容もその特性に合わせたカスタマイズが必要になります。配信スケジュールや活動方針がIP所有者の方針により変動する可能性もあるため、柔軟性を持った企画設計が重要です。
Q5. 今後、IPコラボのトレンドはどうなると考えられますか?
A. 今後は、メタバースやNFTといった新しいテクノロジーを活用したIPコラボレーションが増加すると考えられます。これにより、物理的な制約を超えた、より没入感のある体験を提供できるようになるでしょう。また、SDGsや社会課題解決に貢献するような、社会的な意義を持つIPとのコラボレーションも注目を集める可能性があります。
まとめ:IPコラボは新規顧客獲得に有効なマーケティング手法
IPコラボは異なるファン層を持つIP同士が協力することで、新規顧客獲得に極めて有効なマーケティング手法です。相互のファンベースが交わることで自然な形で顧客層の拡大が図れ、短期間での売上向上と中長期的なブランド価値向上の両方を実現できます。
特にVTuberとのコラボは新しい形のIPコラボとして注目されており、ファンの熱量とSNSでの拡散力を活かした効果的な新規顧客開拓が可能です。ローソンとにじさんじの事例のように、限定グッズを通じて若い世代への訴求に成功している企業も多く見られます。
IPコラボを検討している企業様は、「デジタルギア」がサポートいたします。豊富な実績と専門知識を活かし、お客様のニーズに最適なコラボ戦略をご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。
関連記事

🎥 VTuberの制作・運用ならデジタルギア
Vtuberのキャラデザから3Dアバターの制作まで一気通貫で対応
自治体やVtuber事務所など実績多数
まずはプロに相談してみませんか?