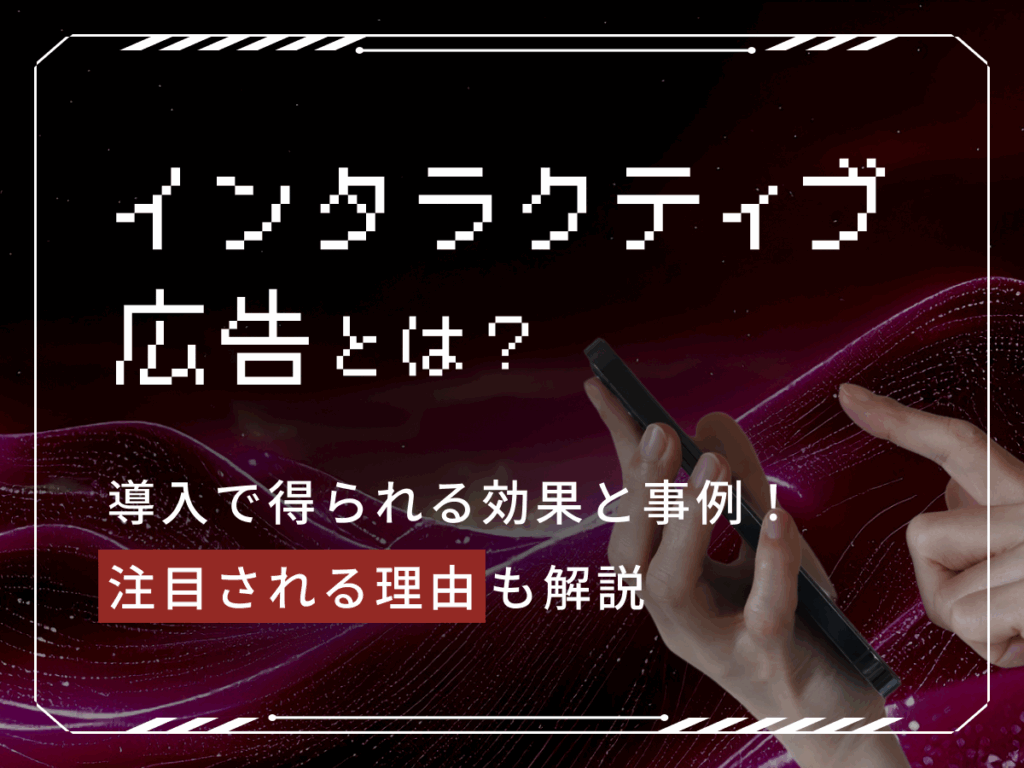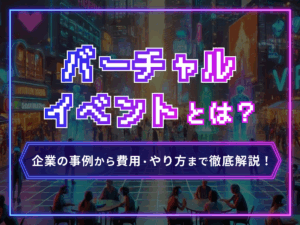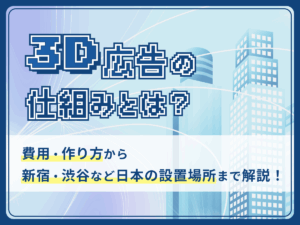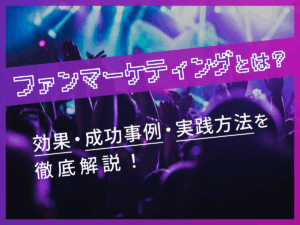近年、広告業界で急速に注目を集めているのが「インタラクティブ広告」です。従来のWeb広告は一方通行で、ユーザーは受け身の姿勢にとどまることが多く、記憶に残りにくいという課題がありました。
インタラクティブ広告は、ユーザーが広告に参加し、双方向の体験を得られる新しい手法です。ゲームや動画、AR/VR、チャットボットに加え、VTuberやキャラクターを組み合わせることで、没入感のあるマーケティング施策が可能になります。
この記事では、インタラクティブ広告の意味や仕組み、従来型広告との違い、メリットや効果、代表的な事例や導入のポイントなどを徹底的に解説します。自社広告の成果を上げたい方は、ぜひ参考にしてください。
この記事でわかること
- インタラクティブ広告の定義と基本的な仕組み
- 従来型広告との違いと注目される理由
- 広告としてのメリットと得られる効果
- 代表的なインタラクティブ広告の種類
- 活用事例と導入のポイント
インタラクティブ広告とは
インタラクティブ広告とは、ユーザーが操作することで広告が反応し、双方向体験が成立する手法です。ゲーム、動画、AR/VR、チャットボットなどが活用され、広告への深い関与と記憶定着を促します。従来型広告では得られにくい、ユーザーの能動性を引き出せる点が最大の特長です。
さらに、ユーザーの行動データを詳細に取得できるため、改善やターゲティング精度の向上につながります。広告を「見せる」だけで終わらせず、ユーザーの行動を起点に価値を高める手法として注目されています。
インタラクティブ広告の意味
インタラクティブ広告の「インタラクティブ」とは、「相互作用」を意味します。従来のバナー広告や動画広告は、基本的に一方向であり、ユーザーは受動的に情報を受け取るだけでした。しかし、インタラクティブ広告では、ユーザーが広告をクリックし、画面を操作すると選択肢に応じて内容が変化するなど、能動的な行動を促します。
例として、商品を使ったゲームへの参加や、動画内で質問に答えながら進行する体験が挙げられます。これにより、ユーザーの注意を惹きつけやすく、自然なかたちで商品やサービスへの理解が深まります。
このような仕組みを通じて、ブランドとのつながりをより強固にし、印象にも残りやすくなる点が、インタラクティブ広告の本質的な意味です。今後はさらに技術が進化し、より多彩な体験が提供されるようになると予想されます。
従来型広告との違いと注目される理由
インタラクティブ広告と従来型広告の最大の違いは、「ユーザーの関与度」にあります。バナーや静止画の広告、テレビCMのような一方向の発信とは異なり、インタラクティブ広告はユーザーが自ら参加し、体験する構造を持っています。この双方向性が、従来の広告では得られなかった高いエンゲージメントと記憶定着率を実現します。
インタラクティブ広告は、SNSやYouTubeなどとの相性も良く、話題性の高い広告は自然に拡散される傾向があります。特に若年層やデジタルネイティブ層をターゲットとする場合、導入することで競合との差別化につながります。視認性と記憶性、さらに拡散性を兼ね備えた広告手法として、今後も導入が進むと考えられます。
インタラクティブ広告のメリットや効果
インタラクティブ広告の主なメリットは、以下の4つが挙げられます。
- ユーザーエンゲージメントを高められる
- ブランド認知を広げイメージを強化できる
- コンバージョンの拡大が期待できる
- データを活用して広告改善につなげられる
これらのポイントを理解することで、従来の広告とは異なる新しいアプローチの可能性を見出せるでしょう。以下で、詳しく解説します。
ユーザーエンゲージメントを高められる
インタラクティブ広告の最大のメリットは、ユーザーのエンゲージメントを高められる点です。エンゲージメントとは、ユーザーがブランドやコンテンツとどれだけ深く関わっているかを示す指標です。従来の広告では、閲覧やクリックなどの一時的な接触が中心でしたが、インタラクティブ広告では、体験を通じて継続的な関与が生まれやすくなります。
例えば、ミニゲームやアンケート形式の広告では、ユーザーが自ら操作することで内容への理解が深まり、ブランドへの好感度も向上しやすくなります。また、操作中に得られる達成感や満足感が、次の行動(シェアや購入など)につながる可能性もあります。広告を「一度見て終わり」にさせない設計にすることで、インタラクティブ広告の効果を最大化できます。
ブランド認知を広げイメージを強化できる
インタラクティブ広告は、ブランドの認知度向上とポジティブなイメージ形成において、効果的な手法です。ユーザーが能動的に関わることにより、広告内容が記憶に残りやすく、自然とブランド名や製品情報が浸透します。さらに、ユニークな体験や印象的な演出を通じて、他社との差別化にもつながります。
キャラクターやVTuberと組み合わせれば、感情に訴える表現が可能となり、ユーザーの印象に強く残る広告体験を提供できます。商品をキャラクターと一緒に紹介するミニゲームや、ライブ配信でリアルタイムに質問に答える形式は、親しみやすさと記憶定着を同時に実現する事例です。体験を通じた広告は、単なる訴求を超えてブランドの「物語」を伝える手段としても機能します。
コンバージョンの拡大が期待できる
インタラクティブ広告は、ユーザーの興味や関心を引き出すことで、購買や資料請求、問い合わせといったコンバージョンへと自然に誘導できる点でも優れています。ユーザーが受け身ではなく、広告内で能動的に行動を起こす構造により、心理的な距離が縮まりやすくなるためです。
従来広告でよくある「クリック数はあるが成果につながらない」「途中離脱が多い」といった課題に対し、インタラクティブ広告は診断コンテンツやシミュレーションを通じて関心を持続させながら商品ページへ導けます。
また、行動を促すタイミングをユーザーの体験の流れに組み込むことで、抵抗感を与えずにCV(コンバージョン)を獲得しやすくなります。特にBtoC商材や、直感的な理解が求められるサービスとの相性が良く、高い成果が期待できます。
データを活用して広告改善につなげられる
インタラクティブ広告の大きなメリットの一つが、ユーザーの行動データを詳細に取得できる点です。広告内でどの部分が最もクリックされたか、どの選択肢が選ばれやすいか、どの時点で離脱が多いかなど、具体的な数値を把握できます。これらのデータは、次回以降の広告改善や、より的確なターゲティングに役立ちます。
従来広告の課題である「成果が見えにくい」「改善の方向性が不明」といった問題に対しても、このような詳細データの取得は大きな価値を持ちます。単なる表示回数やクリック数では見えない、ユーザーの思考や行動の傾向が可視化されることで、広告戦略全体の見直しにもつなげやすくなります。
また、A/Bテストを広告体験の中で実施することも可能なため、訴求内容やデザインの最適化もスムーズです。このようなデータ活用の仕組みは、単なる効果測定を超え、継続的な成果向上と効率的な運用の基盤となります。
インタラクティブ広告の主な手法
インタラクティブ広告には多様な形式が存在し、媒体や目的に応じて最適な手法を選ぶことが重要です。表現方法の幅広さは、インタラクティブ広告ならではの柔軟性と強みといえます。
ここでは、代表的な7つの手法を解説します。どの形式を選ぶかによって、ユーザー体験や訴求効果が大きく変わるため、自社の商品やターゲットに合った手法を見極めましょう。
ゲーム型広告・プレイアブル広告
ゲーム型広告は、ユーザーが実際にプレイすることで広告体験が完結する広告手法です。楽しみながら商品やサービスに触れることができ、広告に対する抵抗感を持たれにくく強い印象を残せます。短時間で完結するミニゲームやスコアを競うタイプなど、形式も多彩です。広告をスキップされる、滞在時間が短いといった問題を解消し、自然なエンゲージメントを生み出せる点が特徴です。
特定のブランドロゴを使ったパズルゲームや、商品に関連するキャラクターと競争するランニングゲームなどが具体例で、ゲームの結果に応じてクーポンを配布するなどでCV率向上にもつながります。
動画インタラクション広告
動画インタラクション広告とは、ユーザーが動画の進行中に操作を加えられる形式の広告です。選択肢によってストーリーが変化したり、商品に関する詳細情報を動画内で確認できたりと、映像に没入しながら双方向の体験が可能になります。従来の一方通行の動画広告と異なり、ユーザーの能動的な関与が生まれやすいのが特長です。視聴者の関心や好みに合わせて展開を変えることで、広告のパーソナライズが実現し、訴求力が高まります。
例えば、ファッション動画でユーザーが好みのスタイルを選ぶと、それに応じたコーディネート提案が表示される仕組みなどがあります。ユーザーの関与が高まることで、商品理解が進み、CVにもつながりやすくなります。技術的なハードルはやや高いものの、費用対効果の面でも期待される手法です。
SNS連動型広告
SNS連動型広告は、ユーザーのSNSアカウントや投稿機能と連携することで、広告体験をソーシャルな場に広げる手法です。ユーザーが広告内で生成したコンテンツや結果をSNSにシェアする仕組みを組み込むことで、広告が自然と拡散され、他ユーザーへの波及効果が期待できます。SNS連動型広告は、ユーザーの拡散行動を前提とした設計により、広告自体がプロモーションツールとなり、認知拡大につながる点もメリットです。
AR/VR活用広告
AR(拡張現実)やVR(仮想現実)を活用した広告は、ユーザーに没入感のある体験を提供できる先進的な手法です。実際の環境に仮想情報を重ねるARや、360度視界の仮想空間に入り込めるVRにより、現実では難しい表現も可能となり、強烈な印象を残すことができます。
ユーザーが操作しながら商品を試すような感覚を得られるため、購買意欲の喚起にもつながりやすいのが特長です。家具を自宅に配置するARアプリや、自動車の試乗体験を再現するVR広告などが典型的な事例です。体験価値が重視される高単価商材や観光業界との相性が良く、差別化を図りやすい手法です。
ライブ配信イベント型広告
ライブ配信イベント型広告は、リアルタイムでユーザーとつながることで、双方向の体験を可能にする広告手法です。コメント機能やリアクション機能を活用しながら、その場でユーザーとコミュニケーションを取りつつ情報を伝えることができます。臨場感と即時性に優れ、特にイベント性のある商材や期間限定のキャンペーンとの相性が抜群です。配信内容によってはアーカイブ視聴も見込めるため、中長期的な効果も期待できます。
VTuberを起用した新製品発表イベントや、インフルエンサーによるライブショッピングが代表例です。イベント性や期間限定キャンペーンとの相性が良く、「見る広告」から「参加する広告」への進化を象徴する手法といえるでしょう。
ショッピング連携型インタラクティブ広告
ショッピング連携型インタラクティブ広告は、広告の中で商品情報の確認から購入手続きまで完結できる設計が特徴です。クリックで詳細を表示し、そのまま決済まで進める設計により、離脱を減らしスムーズな購買行動を促します。
購入までのステップが多く離脱が多いといった課題を解決でき、特にスマートフォンユーザーとの親和性が高いのが特徴です。Instagram投稿やライブ配信中にそのまま購入できる仕組みなどが代表例で、今後ますます注目される分野です。
AI連動型インタラクティブ広告
AI連動型インタラクティブ広告は、ユーザーの行動や入力内容に応じて、広告の内容や訴求方法をリアルタイムで最適化する手法です。チャットボットによる対話形式の広告や、ユーザーの属性に合わせて表示内容が最適化されるパーソナライズ型広告が代表例です。ユーザーごとに異なる体験を提供することで、高い精度でニーズに応えることが可能になります。
旅行予約サイトで希望条件を入力すると最適なプランが提示される仕組みや、会話型広告で自動的に商品提案を行う形式が実際に活用されています。個別対応が求められる現代のマーケティングにおいて、非常に有力な手法です。
インタラクティブ広告の事例
理論だけでなく、実際の活用事例から学ぶことで、インタラクティブ広告の効果や応用範囲がより明確になります。実際の業界での活用事例を知ることで、自社の導入検討にも役立つでしょう。
ここでは、以下の4つの事例を紹介していきます。
- ゲームを活用した事例:NIKE
- ライブ配信やライブコマースを活用した事例:ZARA
- 動画インタラクション広告の事例:エアークローゼット
- AR・VRを活用した体験型広告事例:トヨタ
- デジタルサイネージを活用した事例:コカ・コーラ
それぞれの事例から、企画のヒントや業種別の活用ポイントを見つけていきましょう。
ゲームを活用した事例:NIKE「PLAY NEW」インストアARゲーム
スニーカーブランド「NIKE」はNYやLA、シカゴの旗艦店で、WebAR技術を使った「PLAY NEW」体験を提供しました。来場者がモバイルゲーム内でランニングゲームを展開し、ゲーム内に登場するアイテムとして自社製品を紹介する形式を採用。ユーザーは遊びながらブランドの価値を自然に理解でき、結果的に商品の関心度や購買意欲の向上につながりました。
ライブ配信やライブコマースを活用した事例:ZARA
アパレルブランド「ZARA」は、中国(Douyin/中国版TikTok)でライブ配信を通じて最新コレクションの紹介を行い、視聴中にそのまま商品を購入できる仕組みを提供しました。視聴者はコメントで質問し、その場で回答を得ながら納得して購入へ進める体験を実現。さらに、ヨーロッパや米国でもライブショッピング導入を拡大しました。中国展開では1配信で120万視聴、コマースとブランド体験を両立しました。
動画インタラクション広告の事例:エアークローゼット
ファッションレンタルサービス「エアークローゼット」では、SNS広告から誘導された先に「診断コンテンツ型のインタラクティブ動画」を設置しました。ユーザーが質問に答えながら動画を進める仕組みで、回答内容に応じて最適なコーディネートを提案。視聴者が自分ごと化しやすい体験を提供することで、結果としてCVRが160%改善する効果を上げました。
AR・VRを活用した体験型広告事例:トヨタ
自動車メーカー「トヨタ」は、新型車の試乗体験をVRで再現するキャンペーンを実施。ユーザーはショールームに設置されたVR機器を通じて運転席からの視点や走行感覚をリアルに体感でき、購入検討への動機付けとなりました。
デジタルサイネージを活用した事例:コカ・コーラ
飲料メーカー「コカ・コーラ」は、イギリス全土の駅や街頭デジタルサイネージで、ユーザーがQRコードからAR体験・デジタルボトルを獲得するとリアル店舗(Tesco)で実物と交換できる仕組みを展開。参加型の仕組みにより多くの人の関心を引き、SNSでの話題拡散にも成功しました。
インタラクティブ広告の作り方
インタラクティブ広告を効果的に運用するには技術を導入するだけでなく、目的やターゲットに応じた設計と、運用後の改善までを一貫して計画する必要があります。ここでは制作・運用の流れを3つのステップに分けて解説します。
- 企画コンセプト設計
- 制作ツール技術の選定
- 効果検証と改善のポイント
それぞれ具体的に解説していきます。
企画コンセプト設計
インタラクティブ広告の成果は、初期段階での企画コンセプト設計に大きく左右されます。まず明確にすべきなのは「誰に、何を、どう伝えたいか」です。ターゲットのペルソナ設定、広告の目的(認知・理解・CVなど)、期待するユーザーの行動を整理した上で、インタラクションの形式やストーリー構成を検討していきます。
若年層向けでエンタメ性を重視するのであれば、ゲームやクイズ形式が適しており、ビジネス層にはチャットボット型や診断形式が効果的です。目的やターゲットに応じて、体験内容や表現方法を柔軟に設計することが重要です。
設計段階では、ペルソナごとのシナリオ設計やカスタマージャーニーの可視化なども行いましょう。綿密に設計しておくことで、ユーザー体験の質を上げ、広告成果の拡大も期待できます。
制作ツール技術の選定
インタラクティブ広告の成果を最大化するには、目的に合った制作ツールや技術の選定が欠かせません。採用するフォーマットや体験形式によって必要なスキルやプラットフォームは大きく変わります。自社のリソース・予算・導入期間を踏まえ、目的から逆算して選ぶことが重要です。
動画にインタラクションを加える場合は、YouTubeの「エンド画面」「カード」「TrueViewアクション」などの機能を活用すれば、商品紹介や体験分岐が可能です。
国内では、ドラッグ&ドロップで動画に分岐ボタンや商品リンクを追加できる「TOUCHSPOT MAKER」や、動画内で選択肢を設けられる「MIL(ミル)」といった国産ツールも実績があります。さらに、パロニムの「Tig」シリーズは、映像内のモノや人物、場所など気になる箇所をタップするだけで情報やEC連携にアクセスできる独自技術を搭載。分析ダッシュボードで視聴やクリックを可視化でき、2025年大阪万博のサイネージ導入や大手ECとの公式事例も多数あります。
チャットボットを実装する場合は、AI搭載でLINEやSalesforceと連携可能な「Chat Plus」が代表的です。ユーザー対応を効率化しながら、広告からCVR改善まで一気通貫で支援できます。
AR体験を取り入れる場合は、アプリ不要でWebブラウザから利用できる「8thWall」が有力です。小売店舗やブランド施策と連動させやすく、没入感のある体験を提供できます。
効果検証と改善のポイント
インタラクティブ広告は、公開して終わりではなく、運用後の効果検証と改善を繰り返すことが重要です。ユーザーがどこで離脱したのか、どの要素に反応したのかといった行動データを把握し、次の施策に反映させることで、継続的な成果向上につながります。
改善を進めるためには、事前にKPI(主要指標)を明確に設定することが大切です。エンゲージメント率、クリック率、滞在時間、シェア数など、目的に合わせた指標を選びましょう。
形式ごとの評価軸も意識する必要があります。チャットボットであれば回答率や完了率、動画型広告なら再生完了率や選択率といった具体的なデータが改善の手がかりになります。さらに、アンケートやフィードバック機能を組み合わせれば、数値だけでは見えないユーザーの感覚や不満も把握できます。このように、データ分析と改善を継続することで、ユーザー体験の質を高め、広告の訴求力を最大化できます。
インタラクティブ広告の導入ポイント
実際にインタラクティブ広告を導入する際は、企画や制作だけでなく、導入に適した条件やタイミング、事前準備などにも注意が必要です。ここでは、導入するにあたって重要な3つのポイントを解説します。
導入に適した業界商材
インタラクティブ広告は、すべての業界に適しているわけではなく、特定の業種や商材において高い効果を発揮します。特にユーザー体験や視覚的な魅力、感情的な共感が重視される分野では、導入することで他の広告手法と明確な差別化が可能になります。
代表的な例としては、アパレル・美容・自動車・不動産・観光業界などが挙げられます。これらの業界では、商品を「体験」してもらうことで理解と好感が深まりやすく、ユーザーとの接点を強化することができます。また、サービス型商材であっても、チャットボットや診断コンテンツなどを通じて関心を引き出す構成にすることで、高いエンゲージメントが得られます。
一方で、インタラクティブ広告が適していない業界・商材も存在します。例えば、電気・ガス・水道などのインフラ、金融や保険など規制が厳しい業界、価格や機能が単純で比較が容易な商材は、複雑な体験型広告にしてもユーザーの理解や購買意欲を大きく高める効果は期待できません。こうした分野で無理に導入すると、コストばかりかかり、期待した成果が得られないケースもあります。
そのため、自社の商品やサービスが「体験を通じて価値を伝えやすいか」を見極めることが、導入判断の第一歩となります。
導入時の費用感と期間
インタラクティブ広告の導入には、通常の静的広告と比べてやや高めのコストが発生する傾向があります。コンテンツの種類や技術レベル、外注か内製かによって大きく異なりますが、一般的な相場としては数十万円〜数百万円、場合によっては1,000万円を超えるプロジェクトも存在します。
制作期間は、簡易的な診断コンテンツやチャットボット型広告であれば2〜4週間程度、ARやVRを活用した複雑な体験型広告になると3ヵ月以上を要するケースもあります。ツールの選定やシナリオ設計、検証工程を含めると、想定以上に準備期間が必要になる点にも注意が必要です。
「予算に見合う成果が出るのか」「社内工数はどれくらいかかるのか」と不安に感じる場合は、制作実績のあるパートナー企業に相談し、相場感を把握しておくと安心です。補助金や広告配信サービスとのパッケージ提案を活用すれば、初期費用を抑えることも可能です。
導入前に押さえておく注意点
インタラクティブ広告を成功させるためには、技術的な側面だけでなく、ユーザー視点に立った全体的な計画を立てることが大切です。
まず、技術先行にならないよう注意しましょう。目新しさだけで複雑な仕組みを導入しても、操作が分かりにくければユーザーは離脱してしまいます。Webサイトやアプリとの連携が不十分だと、ユーザー体験が途切れてしまう可能性もあります。
さらに、個人情報の取り扱いと運用体制を事前に整えておくことも重要です。AIやチャットボットを利用する場合、情報の取り扱い方やユーザーへの説明責任が求められるため、社内の法務確認やプライバシーポリシーの整備を並行して進める必要があります。
「ユーザー視点が抜け落ちてしまう」「複雑すぎて運用できない」といった失敗を防ぐためには、シンプルで明快な体験設計を心がけましょう。事前の想定と現場の運用をすり合わせることで、スムーズな運用につながります。
インタラクティブ広告で成果を最大化するためのポイント
インタラクティブ広告を導入しただけでは、必ずしも成果が出るとは限りません。重要なのは、ユーザー体験の質や運用後の分析・改善を通じて、効果を最大限に引き出すことです。ここでは、効果を最大化するために意識したい3つのポイントを解説します。
ユーザー体験を重視した設計を行う
インタラクティブ広告の効果は、ユーザーにとって「わかりやすく魅力的な体験」が提供できるかどうかで決まります。広告がどれだけインタラクティブであっても、ユーザーが戸惑ったり、興味を持てなかったりすれば効果は期待できません。
ポイントはシンプルさと自然な操作感です。複雑すぎる構成や、説明のない動作は、離脱の原因になります。ユーザーが興味を持ったタイミングで適切な情報を提示し、最終的に購入やシェアなどの行動につながるような構成を心がけましょう。進行状況を示すUIや誘導メッセージの強化は、離脱防止に効果的です。ユーザーの行動心理を意識した構成を作ることで、より高いエンゲージメントと成果を得ることができます。
データを活用してPDCAを回す
インタラクティブ広告は、ユーザーの反応や行動データを詳細に取得できる点が強みです。このデータを基にPDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)を回すことで、施策を継続的に強化できます。例えば「動画内でどの選択肢が選ばれたか」「チャットボットの離脱ポイントはどこか」といったデータを分析すれば、ユーザーの関心領域や課題を明確化できます。
「成果が伸び悩む」「改善の方向性が見えない」といった問題は、分析体制が不十分なことが原因です。広告設計段階から測定項目を設定し、定期的にレビューする仕組みを整えることが欠かせません。データ活用は広告効果の向上だけでなく、社内への成果報告や次回施策の説得材料としても有効です。
最新トレンドを取り入れて継続的に改善する
インタラクティブ広告は、技術革新のスピードが早い分野です。新しいツールや表現手法が次々に登場するため、常に最新トレンドをキャッチアップし、施策に柔軟に取り入れる姿勢が必要です。
近年注目されているのは、生成AIによるパーソナライズ広告、音声インタラクション、WebARを活用した体験型プロモーションなどです。これらを柔軟に導入することで、ユーザーに新鮮な体験を提供し続けられます。
「広告が古く見えてきた」「競合が先に話題性を獲得している」と感じた時こそ改善のタイミングです。社内外から情報を収集し、施策を常にアップデートする姿勢が求められます。
インタラクティブ広告に関するよくある質問
ここでは、インタラクティブ広告について実際によく寄せられる質問とその回答を紹介します。
インタラクティブ広告はどんな業界に向いている?
インタラクティブ広告は、体験を重視する業界や、ビジュアル訴求が重要な業種に特に適しています。アパレル・化粧品・自動車・不動産・旅行・エンタメ・教育などは、顧客との関係性を深めることで価値が伝わりやすく、インタラクティブ要素の導入が成果につながりやすい分野です。
また、BtoCだけでなく、BtoBにおいても展示会や製品紹介、採用マーケティングなどに活用が進んでいます。製品のスペック比較や活用シーンをシミュレーションで体験させることで、導入検討の精度を高めることが可能です。
小規模企業でも導入可能?
インタラクティブ広告は、大企業だけのものと思われがちですが、現在では小規模企業でも十分に導入可能な環境が整ってきています。以前はコストや技術面のハードルが高く、導入をためらう声もありましたが、近年はテンプレート型のツールや低価格のサービスが登場し、初期費用を抑えた導入が現実的になっています。
インタラクティブ広告の制作期間はどれくらい?
インタラクティブ広告の制作期間は、コンテンツの複雑さや使用する技術、制作体制によって大きく異なります。一般的には、簡易な診断コンテンツやアンケート型であれば2〜4週間程度、本格的な動画インタラクションやAR・VRを活用する場合は2〜3ヵ月、場合によってはそれ以上かかることもあります。
インタラクティブ広告配信におすすめのプラットフォームは?
インタラクティブ広告の配信先は目的やターゲットに合わせて選ぶことが重要です。拡散性の高いInstagram・TikTok・X(旧Twitter)、動画体験に強いYouTube、幅広いリーチが可能な Google広告やMeta広告が代表的です。さらに、ゲーミフィケーション体験を提供できる Roblox、テレビ画面上での体験を実現するSamsung AdsやFuboのCTV広告 なども注目されています。目的やターゲットに合わせて複数のプラットフォームを組み合わせることで、より高い効果が期待できます。
従来のWeb広告との組み合わせは有効?
インタラクティブ広告は、従来型のWeb広告と組み合わせることで、相乗効果を生み出すことが可能です。認知拡大・比較検討・購入促進といったユーザーの検討段階ごとに、適切な広告形式を配置することで、広告全体の成果を底上げできます。
まとめ|インタラクティブ広告で顧客体験を進化させ、CVRを最大化しよう
インタラクティブ広告は、従来型広告では実現が難しかった「ユーザー参加型の広告体験」を可能にする手法として、近年ますます注目を集めています。双方向性を活かすことで、ユーザーの関心を引きつけ、エンゲージメントやブランド理解、そしてコンバージョンへとつなげやすくなるのが最大の魅力です。効果測定がしやすく、改善を重ねることで継続的に成果を高められるメリットがあります。
今後、AIやARなどの技術と融合しながら、より高度なインタラクティブ体験が求められる時代が到来するでしょう。ユーザーにとって魅力的な体験を設計し、最新技術を活かした施策を継続的に打ち出すことが、競争優位性の確立につながります。
まずは、自社の商材や目的に合った小規模な施策から始めてみるのがおすすめです。広告を「見せる」から「体験させる」ものへと進化させ、CVRの最大化を目指しましょう。