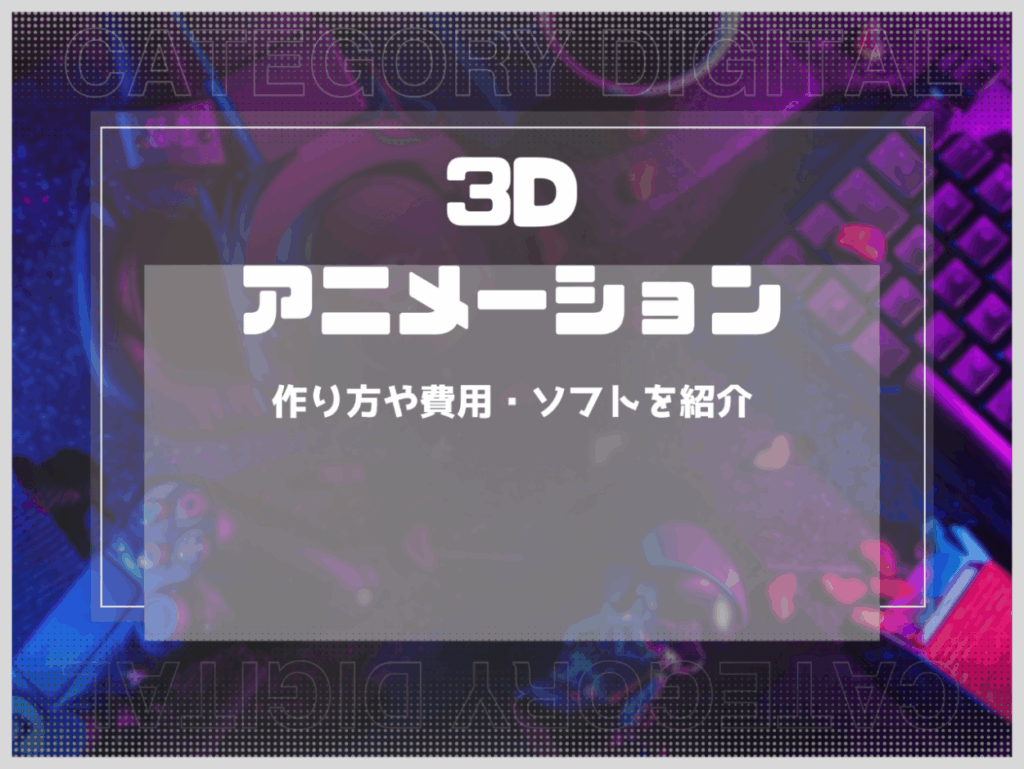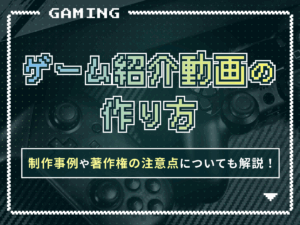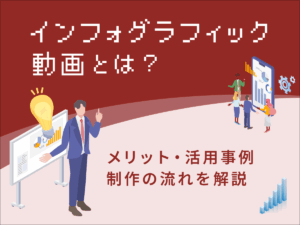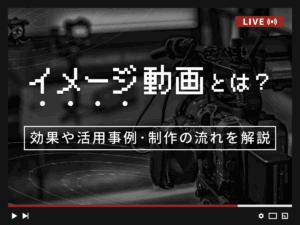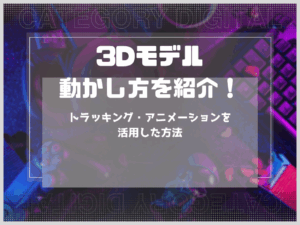3Dアニメーションは、実写では再現できない表現や、複雑な仕組みの可視化を可能にする映像表現です。近年では、企業プロモーションやeラーニング、メタバース空間など、幅広いシーンで活用が進んでいます。
3Dアニメーションを活用してみたいと思っても「どうやって作るの?」「費用はどれくらい?」「どこに依頼すればいいの?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、3Dアニメーションの仕組みや活用例から、作成手順、費用の目安、おすすめソフト、依頼先の選び方までわかりやすく解説します。最後まで読むことで、3Dアニメーションの可能性を最大限に引き出し、目的を達成するための道筋が見えてくるでしょう。
この記事でわかること
- 3Dアニメーションの特徴と活用シーン(企業PR/広告/教育/メタバースなど)
- 制作工程の流れ(三面図~モデリング~レンダリングまで)
- 制作費用の相場と、コストを左右する主な要因
- 目的に応じたおすすめ3D制作ソフト(Blender/Mayaなど)
- 依頼先を選ぶ際に見るべきポイント(実績/対応範囲/納品形式など)
3Dアニメーションとは
3Dアニメーションとは、コンピューター上で立体的な物体や空間を構築し、動きを加えて映像として表現する技術です。立体的な視点やリアルな質感、光の反射まで再現できるのが特徴で、2Dアニメーションでは難しい複雑な演出も可能になります。
たとえば、製品の内部構造や動作を視覚的にわかりやすく示したり、未完成の建物の完成予想をリアルに再現したりと、実写では難しい情報伝達を補う手段として活用されています。
こうした特徴から、3Dアニメーションは近年、さまざまなビジネスシーンや個人のクリエイティブ活動で広く活用されています。企業のプロモーション映像やサービス紹介、教育コンテンツの制作などはもちろん、VTuberのアバターに豊かな表情と動きを与える技術としても重要な役割を担っています。
また、一度制作した3Dモデルは、別のアニメーションやゲーム、メタバースなど、さまざまな媒体で繰り返し利用できる資産となる点も、長期的な視点で見ると大きなメリットといえるでしょう。
3Dアニメーションの活用シーン
3Dアニメーションは、ビジネスから教育、エンタメまで幅広い分野で活用されています。ここでは、代表的な5つの活用シーンと具体的な導入例を紹介します。
企業プロモーション
製品やサービスの魅力を視覚的に伝える手段として、3Dアニメーションは非常に効果的です。複雑な製品の仕組みや、目に見えないサービスの流れ、抽象的な概念も、3Dアニメーションを使えば直感的かつ分かりやすく視覚化できます。
実写では伝えきれない製品の魅力や、使用イメージを効果的に見せることで、視聴者の理解を深め、購買意欲を高めます。例えば、以下のような導入事例があります。
- サービス説明や製品の動作を3DCGで視覚的に表現
- 展示会、営業資料、Webサイト動画、SNS広告などで使用
- スマホアプリのUI動作、工業製品の内部構造説明
実際に、公式Webサイトやランディングページで導入している企業も多く、短時間でユーザーの理解と関心を得る工夫として浸透しています。
CM・ブランディング動画
テレビCMやWeb広告では、3Dアニメーションがブランドの世界観やコンセプトを印象的に伝える手段として使われています。例えば、以下のように活用されています。
- 実写では不可能な表現で企業の世界観・個性を演出
- 企業マスコット(バーチャルキャラクター)を使った広告展開
- テレビCM、Web広告、交通広告動画など幅広いメディアで活用
近年では特に、SNS広告やYouTubeプリロール広告で3Dアニメーションを活用する企業が増えており、特に若い世代へ高い訴求力が期待できます。短時間で視聴者の注目を集め、ブランドの印象を強く残せる点が大きなメリットです。
eラーニング・研修コンテンツ
教育・研修分野でも3Dアニメーションは学習効果を飛躍的に高めます。特に抽象的な概念や、通常は見ることのできない現象を可視化するのに適しており、以下のような場面で導入されています。
- 難解な概念や作業工程を3DCGビジュアルで解説
- 医療、建築、製造、介護など専門職向けの学習コンテンツとして活用
- 工場の安全教育、脳内構造の解説、ロールプレイ教材などに応用
例えば医療分野では、手術の手順や人体の内部構造を詳細に表現できるため、実習前の効果的な学習ツールとなっています。また、危険な作業の研修も安全に実施できる点もメリットです。
ゲーム・メタバースコンテンツ
ゲームやメタバースといった仮想空間のコンテンツ制作にも、3Dアニメーション技術は欠かせません。3Dアニメーションは、以下のようにプレイヤーやユーザーを没入させる魅力的な仮想空間やキャラクターを創り出すために役立ちます。
- キャラクター、ワールド、アイテムなどを3Dで構築可能
- UnityやUnreal Engineと連携してリアルタイム化も可能
- アバター用3Dモデル、ワールド制作、バトル演出などに活用
特に最近は、企業のバーチャルショールームやオンライン展示会など、ビジネス用途でのメタバース活用が進んでいます。顧客が実際に空間を歩き回るような体験を提供することで、従来の2D Webサイトとは異なる没入感を生み出せます。
イベント演出・舞台装置
リアルイベントにおいても、3Dアニメーションは会場の雰囲気を大きく変える演出として活用されています。3Dアニメーションを活用することで、以下のような魅力的な演出が可能です。
- デジタルサイネージ、プロジェクションマッピング、舞台背景として活用
- 実物と組み合わせてインパクトのある演出が可能
- ミュージカルの背景演出、企業周年イベント、ライブの背景映像などに使用
大型LEDビジョンやプロジェクターの普及により、会場全体を3Dアニメーションで彩ることが一般的になっています。特に企業の周年イベントや新製品発表会では、ブランドの世界観を空間全体で表現する手法として定着しつつあります。
3Dアニメーションの作成方法
3Dアニメーションは、いくつかの工程を順番に進めることで完成します。それぞれのステップには大切な役割があり、全体の流れを知ることで、どんな準備や工夫が必要かがわかります。ここでは、3Dアニメーションの作成方法をステップごとに詳しく解説していきます。
三面図の作成
3Dアニメーション制作の最初のステップは、三面図(正面・側面・上面)の作成です。これは、次のモデリング工程で立体的な形を作る際の精密な設計図となり、最終的な仕上がりやイメージのズレを防ぐために重要です。
キャラクターや製品などをデザインする際、一つの視点だけでは全体像を把握できません。三面図を作成することで、立体物としての整合性を確保し、モデリングの指針となります。プロの現場では、イラストレーターやデザイナーが作成した三面図をもとに、3Dモデラーが作業を進めていきます。
モデリング
モデリングとは、デザインや三面図をもとに3D空間上で立体的な形を作り上げる工程です。
点、線、面(ポリゴン)を組み合わせて立体物を形作り、最初はシンプルな形から始め、徐々に細部まで作り込んでいきます。近くで大きく表示されるキャラクターや製品など、ディテールが重要になるものほど、より細かく、正確なモデリング技術が求められます。
このモデリングの精度が、最終的な映像のリアルさやクオリティを大きく左右します。
マテリアル・テクスチャ
形が完成したら、次にその表面の質感や色、模様といった「見た目」を設定します。マテリアル設定では、「金属のように光る」「布のように柔らかい」「ガラスのように透ける」といった、物体の材質に応じた質感を定義します。
テクスチャ設定では、物の表面にある模様や細かい凹凸を画像データなどで貼り付けます。木目、肌のきめ、服のシワなどを表現し、モデルに生命感やリアリティを宿らせます。この工程で、モデルの印象は大きく変わります。
リギング
リギングは、3Dモデルに骨組み(ボーン)を入れて、動かせるようにするための工程です。これによってキャラクターの腕や足、指などを自由に動かせるようになります。製品モデルの場合も、可動部分にリグを設定して動きを再現できるようにします。この工程がしっかりしていると、次のアニメーション作業がスムーズに進みます。
スキニング
スキニングは、リギングで入れた骨組みとモデルの表面を関連づける工程です。キャラクターに自然で滑らかな動きをつけるためには、どこに関節を置き、その関節が動いたときにモデルの表面がどう変形するか(服のシワや体の凹みなど)を細かく、かつ正確に設定する必要があります。特に人間の複雑な動きを表現するには、技術と経験が非常に問われる工程です。スキニングの精巧さが、アニメーションの質を左右します。
レンダリング
最後は、作成した3Dモデルとアニメーションを映像として書き出す「レンダリング」です。光源の配置、カメラワーク、解像度の設定などを行い、一連のフレームを連続した動画として書き出します。
レンダリングは非常にパソコンへの負荷がかかる作業で、モデルの複雑さや映像の長さによって数時間から数日かかることもあります。レンダリング設定によって、写実的な表現にしたり、アニメのようなトゥーン調にしたりと、映像の最終的な見た目が決まります。最近では、クラウドレンダリングサービスを利用して時間短縮を図るケースも増えています。
3Dアニメーション制作にかかる費用
3Dアニメーション制作を検討するうえで、気になるものの一つが費用です。3Dアニメーション制作の費用相場は、内容や依頼先、クオリティによって大きく異なります。
個人クリエイターや小規模制作会社への依頼、または既存モデルやテンプレートを活用した簡易な3D動画であれば、数万円~80万円程度で制作可能な場合もあります。
一般的な制作会社やスタジオへ依頼する場合でも、映像の長さや複雑さによって費用は大きく変動します。
- 30秒程度のシンプルなビジネス向け映像であれば、約10万円~50万円程度
- 1分程度の一般的なプロモーション映像であれば、約50万円~150万円程度
- 高品質なオリジナルキャラクターアニメーションや、複雑な製品デモなどになると、約150万円~数百万円以上
上記のように、内容によって相場はさまざまです。特に、テレビCMやゲーム内ムービーのような最高レベルのクオリティや、長尺で非常に複雑な表現を追求する場合は、200万円~数千万円以上になることもあります。
費用の差が生まれる要素は、以下のポイントが挙げられます。
| 要素 | 低予算の例 | 高予算の例 |
|---|---|---|
| モデルの複雑さ | ・シンプルな形状のみ ・パーツ、ポリゴン数少なめ | ・複雑な形状 ・高ポリゴン、細部までのリアルな作り込み |
| アニメーション量 | ・単純な動きのみ ・シーン数少なめ | ・複雑な動き ・多数のシーン転換 |
| テクスチャ・質感 | ・シンプルな材質 ・基本的な色のみ | ・写実的な質感 ・複雑な光の反射 ・特殊エフェクト |
| レンダリング品質 | ・標準画質(HD程度) ・基本的な光源 | ・高解像度(4K) ・複雑な光源、影 |
| ナレーションや音声 | ・なし ・既存素材を活用 | ・オリジナル収録 ・BGM制作 |
| 企画・ディレクション | ・発注者が全て用意 | ・企画・演出・シナリオ含めフルサポート |
| 修正回数 | ・初稿のみ ・修正1回程度 | ・複数回修正 ・細かなカスタマイズ |
その他、制作会社による価格差もあります。実績豊富なスタジオや大手制作会社は、ノウハウや品質の分、費用も高くなる傾向です。一方で、個人クリエイターや小規模事務所の場合は、予算を抑えつつ柔軟な対応ができる場合もあります。
予算を抑えるためには、以下のポイントを特に意識しましょう。
- 映像の尺(長さ)やシーン数を見直す
- 既存モデルやテンプレートの活用を検討
- 必要最低限の動き・シンプルな演出に絞る
- 簡易的なアニメーションにとどめる
- 優先度の高いカットや機能に予算を集中させる
どこにこだわり、どこを簡易化できるかを明確にすることで、最適な予算配分が可能になるでしょう。
作りたい3Dアニメーションの費用を知りたい場合は、制作会社に概算見積もりを依頼しましょう。多くの制作会社では、無料で相談や見積もり依頼が可能。デジギアでは高品質3D/VTuberなど、目的や予算に応じて最適なプランを提案します。
3Dアニメーション作成におすすめのソフト
3Dアニメーションを自作したい場合、市販されている3D制作ソフトを活用することで、専門知識がなくても制作にチャレンジできます。ここでは、初めての方からプロを目指す方まで幅広く選ばれている主要ソフトを紹介します。
Blender
| 期間 | 費用(税込) |
|---|---|
| 無料 |
Blenderは無料で利用できる、高機能な統合型3Dソフトウェアです。モデリング、アニメーション、スカルプト、レンダリング、映像編集など、3D制作に必要なほとんどの機能をこれ一つに備えています。
オープンソースながら頻繁なアップデートがあり、最新の3D技術にも対応しています。世界中にユーザーが多く、無料とは思えないほどの高品質な映像制作が可能なことから、個人クリエイターや学生、趣味で3Dを始めてみたい方、スタートアップ企業などに人気があります。チュートリアルや解説動画も豊富に公開されているので、独学でも学びやすい環境が整っています。
多機能ゆえに覚えることは多いですが、「まずはコストをかけずに3D制作の世界に触れてみたい」「コミュニティの情報を見ながら自分で学びたい」という方にとって、最初の一本として最もおすすめのソフトといえるでしょう。
Maya
| 期間 | 費用(税込) |
|---|---|
| 月間プラン | 39,600円 |
| 年間プラン | 312,400円 |
Mayaは映画やゲーム、VFX(視覚効果)制作といったプロの現場で世界的に最も広く使われている業界標準の3Dソフトウェアです。Autodesk社が提供しており、月額または年額の有料サブスクリプション形式です。
特に高度で複雑なキャラクターアニメーションや、それに必要なリギング機能に強みを持っています。機能が非常に豊富で拡張性も高いため、大規模な商業プロジェクトにも対応できます。
高機能な分、操作は複雑で習得には時間がかかり、費用もかかります。しかし、「将来的にプロの3Dアニメーターやモデラーを目指したい」「業界標準のスキルを習得したい」「最高品質のキャラクターアニメーションを追求したい」といった、より専門的で高度な目的を持つ方にはおすすめです。多くの制作会社やスタジオがMayaを採用しているため、就職や案件獲得にも役立つでしょう。
3ds Max
| 期間 | 費用(税込) |
|---|---|
| 月間プラン | 39,600円 |
| 年間プラン | 312,400円 |
3ds MaxもMayaと同じAutodesk社が提供する有料ソフトで、特に建築、プロダクトデザイン、ゲーム開発(特に背景やレベルデザイン)などの分野で広く使われています。主にWindows環境での使用が一般的です。
直感的で扱いやすいインターフェースと、パラメトリックモデリングに強い点が特徴の一つです。建物や機械、家具といった正確なスケール感が求められるものや、建築パースのような写実的な静止画・アニメーション制作に適しています。
建築系のプラグインやライブラリも充実しており、特に建築関連やインテリア、工業製品のアニメーションを作りたい場合は、3ds Maxが適しているでしょう。
3Dアニメーション制作会社の選び方
3Dアニメーション制作を外部に依頼する場合、自社の目的や要望に合った制作会社を選ぶことが重要です。以下に、失敗しないための主なチェックポイントをまとめました。
制作実績・ポートフォリオ
制作会社を選ぶ際、まずは過去の実績やポートフォリオをチェックすることが重要です。過去にどのようなプロジェクトを手掛けてきたかを確認しましょう。
- 自社の業界や用途に近い事例があるか
- 表現力や映像のクオリティが希望に合っているか
- 動画サンプルや事例ページが充実しているか
特に、同業界や類似サービスの実績がある会社なら、専門用語や業界特有の要望にも柔軟に対応してくれる可能性が高いです。Web上に具体的な事例や動画サンプルを公開している会社は信頼性も高く、相談もしやすい傾向があります。
対応範囲
制作会社によって、対応できる範囲が大きく異なります。自社の要望と制作会社の対応範囲がマッチしているかを確認しましょう。
- 企画から一貫して任せたい場合 → ワンストップ対応が可能か
- 一部工程(例:モデリングのみ)だけ依頼したい場合 → 分業対応が可能か
- 社内リソースとの連携は必要か → 連携方法や中間納品の対応は可能か
事前に「どこまで任せたいか」「社内でどこまで準備できるか」を整理し、希望に合う会社を選びましょう。制作フローや進め方を最初にすり合わせることで、トラブルや行き違いも防げます。
料金体系
3Dアニメーションは、依頼する内容によって費用が大きく異なります。制作会社を選ぶ際は、提示された見積もりがどのような作業に対して、いくらかかるのかが明確に示されているかを確認しましょう。
- 「秒単価」や「工程別料金」などが公開されているか
- 予算に応じた柔軟な提案をしてくれるか
- 修正対応や追加費用の発生条件は事前に説明されているか
たとえば、30秒のプロモーション映像でも10万円〜50万円以上と幅があります。予算に合わせて品質やボリュームを調整できるかどうかも、重要なチェックポイントです。また、見積もりの段階で不明点があれば、遠慮なく質問することが後々のトラブル防止につながります。
得意ジャンル
3Dアニメーション制作にはさまざまな専門分野があり、会社ごとに得意とするジャンルが異なります。例えば、以下のような得意ジャンルがあります。
- VTuberやキャラクターアニメーションに特化している会社
- 建築や機械など、正確な工業製品のCGを得意とする会社
- 企業ブランディングやマーケティング映像の実績が豊富な会社
- プロジェクションマッピングやイベント演出に強い会社
各制作会社の得意ジャンルは、過去の実績や会社紹介から推測できることが多いです。
自社の求める表現に近いジャンルを得意としている制作会社を選ぶことで、よりクオリティの高い3Dアニメーションの制作が期待できます。また、業界特有の知識や表現ノウハウがあることで、制作過程でのアドバイスも得られる可能性があります。
納品形式
制作した3Dアニメーションをどのように活用するかを考慮し、適切な納品形式に対応しているかを確認しましょう。
- SNS用の短尺編集や、異なる解像度やアスペクト比への対応ができるか
- モーションデータや素材データを再利用できる形で納品可能か
- 長期的な活用に備えて元データの納品に対応しているか
将来的にデータを活用したい場合や、複数メディアでの展開を予定している場合は、事前の確認が重要です。将来的な利用の可能性について親身に相談に乗ってくれる会社は、長く付き合いやすいパートナーとなるでしょう。
おすすめの3Dアニメーション制作会社
ここでは、さまざまな特色を持つおすすめの3Dアニメーション制作会社を6つ紹介します。
- デジタルギア(DIGEAR)
- サンジゲン
- サブリメイション
- Flying Ship Studio
- 株式会社モックス
- 株式会社 NIXE
それぞれ得意分野や特徴が異なるので、目的に合わせて選びましょう。
デジタルギア
デジタルギア株式会社は、2023年設立の東京都港区芝に本社を置くデジタルエンターテイメント制作会社です。
2D・3DCG映像制作を中心に、VTuber向けのキャラクターモデリングや背景制作、3Dバーチャルライブ制作など幅広い実績があります。Maya、3ds Max、Blender、MotionBuilder、Unityなど多様なソフトを活用し、企画から制作までワンストップで対応可能です。
2025年9月には山口県岩国市に新たな制作拠点「デジタルラボ岩国」を開設し、地域連携による人材育成や雇用創出にも注力しています。少数精鋭のプロ集団による高品質な制作と、クライアントのニーズに沿った柔軟なサポート体制が特徴です。
費用は目的や内容に合わせて個別に提案しており、高品質ながらも柔軟に対応可能です。特に、高品質なVTuber関連や企業向けアニメーション、モーショキャプチャ収録を含む案件を依頼できます。
参考:デジタルギア
サンジゲン
株式会社サンジゲンは、2006年3月に設立されたアニメーション制作会社で、東京都杉並区に本社を構えています。
主に、TVアニメや劇場アニメを中心に3DCGアニメーション制作を手がけています。独自の技術で3DCGと手描きアニメーションを融合させ、滑らかでダイナミックかつ温かみのある映像表現を追求しています。『アルペジオ』『バンドリ!』シリーズなど、数々の人気アニメ作品で高い評価を得ており、アニメ分野における3DCGの最先端を担っています。
サンジゲンはアニメ作品が中心のため、主にシリーズや劇場版といった大型プロジェクト向けです。費用感は一般的なプロモーション等より高額となる傾向ですが、独特のセルルック表現を依頼できます。
参考:サンジゲン
サブリメイション
株式会社サブリメイションは、2011年7月設立の3DCGアニメーション制作会社です。東京都国立市に本社およびスタジオを構え、名古屋市や仙台市にも拠点を展開しています。
セルルック表現にこだわった3DCGアニメーション制作を得意としており、アニメーションの企画から制作、販売に加え、楽曲・音響制作まで幅広く手掛けます。『ドラゴンズドグマ』『ラブライブ!』『シキザクラ』など、国内外で評価される人気作品の実績を持ち、独自の映像スタイルでアニメ業界に貢献しています。
サブリメイションは、セルルック3DCGアニメ制作が強みで、企画や音響も含めたアニメーション制作を依頼できます。主にアニメ作品や、独特なCG表現を求めるプロジェクト向けとなり、費用感は内容により大きく変動します。
参考:サブリメイション
Flying Ship Studio
Flying Ship Studioは、アニメーション制作の全工程をワンストップで対応可能なスタジオです。企画、デザイン、モデリング、アニメーション、コンポジット、完成まで一貫して依頼できる他、一部工程のみの受託も可能です。
特に子供向けキャラクターアニメーション制作を得意としており、自社オリジナル企画も推進するなど、国内外に向けた幅広い活動を展開しています。公式サイトでは、イラストや動画、オリジナルキャラクターのドローイングも随時公開しています。
子供向けアニメ、オリジナルキャラクター、教育用コンテンツなどに強みがあり、一部工程のみを依頼したい場合にも相談可能です。
株式会社モックス
株式会社モックスは、2007年設立の3DCGキャラクターアニメーション制作会社で、東京都高田馬場駅近くに拠点を構えています。
主にコンシューマーゲームや映像作品向けの3DCGキャラクターアニメーション制作を専門とする会社です。キャラクターの演技付けや、モーションキャプチャデータの高度な編集を得意としています。セルアニメーションや人体構造の深い理解に基づいた、リアルで説得力のあるキャラクター表現に強みがあり、約200タイトル以上の制作実績を持ちます。
キャラクターアニメーション、特にモーショキャプチャ編集を伴うリアルな動きの表現依頼に適しています。ゲームや映像作品向けの専門性が高く、費用感は依頼内容や必要なモーションの量によって変動します。
参考:株式会社モックス
株式会社 NIXE
株式会社NIXE(ニクス)は宮城県仙台市を拠点とするデジタルクリエイティブ企業です。システム開発を主軸としつつ、2D/3Dアニメーション制作も手掛けています。
「技術」「誠実」「温和」を企業文化の柱とし、産業のデジタライゼーション推進やエンターテインメント分野での価値創造に取り組んでいます。多様なサービスを提供する中で、地域の発展にも貢献しています。
幅広いデジタル制作を手掛けており、さまざまなデジタルコンテンツ内でのアニメ制作を依頼できます。地域からの依頼や、システムと連携したCG案件に適しており、費用感はプロジェクト全体やCG部分のボリュームによります。
参考:株式会社 NIXE
3Dアニメーションに関するよくある質問
最後に3Dアニメーションに関するよくある質問をまとめます。
3Dアニメーションとは何ですか?
コンピューター上で立体的な物体やキャラクターに動きをつけて映像として表現する技術です。2Dアニメーションと違い、奥行きやリアルな質感、さまざまな視点からの映像演出が可能です。
2Dアニメーションとの違いは何ですか?
2Dは平面的な表現で、3Dは奥行きや立体感を持たせられる点が大きな違いです。また、カメラのアングルを自由に変えたり、光や影の効果をリアルに演出できる点も大きな違いです。
3Dアニメーションはどんな場面で使われますか?
商品PR、テレビCM、ゲーム、eラーニング、医療・建築の説明動画、メタバース空間、イベント演出など、幅広い用途で活用されています。
3Dアニメーションを作るには何が必要ですか?
三面図や企画書などの設計資料、3Dソフト(BlenderやMayaなど)、制作スキルや機材などが必要です。専門的な部分は外部の制作会社に依頼することもできます。
3Dアニメーションの制作費用はいくらくらいですか?
クオリティや内容によって異なりますが、30秒の映像で10万〜50万円程度が一般的な相場です。フル3DCGや高精度なレンダリングが必要な場合はさらに高額になることもあります。
3Dアニメーションの制作費用はいくらくらいですか?
クオリティや内容によって異なりますが、30秒の映像で10万〜50万円程度が一般的な相場です。フル3DCGや高精度なレンダリングが必要な場合はさらに高額になることもあります。
まとめ:3Dアニメーションをビジネスに活用しよう
3Dアニメーションは、企業プロモーションや商品説明、ブランディング、教育、メタバース、イベント演出など、さまざまな分野で活用が広がっています。従来の映像表現では伝えきれない魅力や複雑な情報も、3Dなら直感的に分かりやすく、印象的に伝えることができます。
3Dアニメーションの制作方法には自社で取り組む内製と、専門会社への外注があります。三面図の作成からレンダリングまでの流れや、BlenderやMayaなどのソフト選びを理解し、自社のリソースや予算に合った方法を選ぶことが大切です。
外部に依頼する場合は、実績・対応範囲・料金体系・得意分野・納品形式などを総合的に比較し、自社のニーズにぴったり合うパートナーを選びましょう。今回紹介した制作会社はそれぞれ強みや特徴が異なるので、目的やイメージに合わせて検討するのがおすすめです。
3Dアニメーションは最初に一定のコストがかかることもありますが、一度作ったモデルやアセットは繰り返し活用できるため、長期的には非常に効率的な投資となります。自社のビジネスに合わせた3Dアニメーション活用を検討し、競合との差別化を図りましょう。